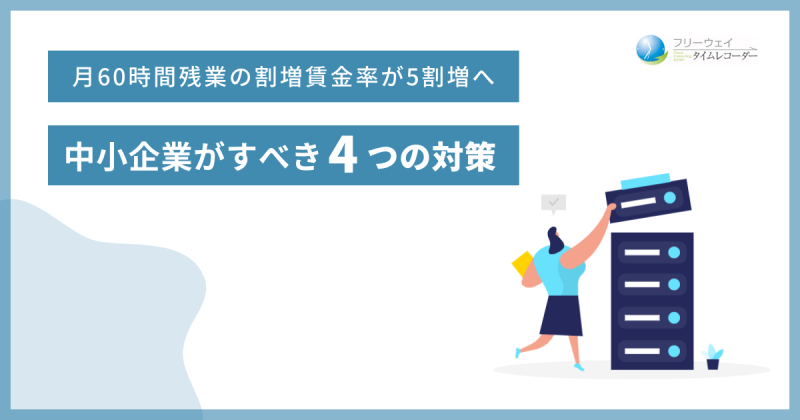
2023年4月から中小企業にも適用された「月60時間超の残業割増賃金率50%」への対応は、多くの人事・労務担当者にとって重要な課題となっています。この法改正により、これまで25%だった割増率が一気に倍増し、企業の人件費負担が増大するリスクが生じています。
本記事では、月60時間超の残業割増賃金率引き上げについて、制度の基本から実務対応まで、中小企業の担当者が押さえておくべきポイントを解説します。単なる法令解説ではなく、実際の計算例や具体的な対応策など、現場での混乱を最小限に抑えるための情報をお届けします。
制度改正をコストアップと捉えるのではなく、働き方改革の契機として、より健全で生産性の高い職場づくりを目指しましょう。
2023年4月から、中小企業にも「月60時間を超える残業に対して割増賃金率を50%に引き上げる制度」が適用されました。この制度変更は、中小企業の人事・労務担当者にとって、対応が欠かせない重要なポイントです。
この割増賃金率の引き上げは、企業の人件費に直接影響を与える法改正であり、計画的な対応が求められます。労働基準法では、長時間労働を抑制し、労働者の健康を守ることを目的として、時間外労働に対する割増賃金の支払いを義務付けています。今回の改正により、これまで猶予されていた中小企業も対象となり、対応の遅れは法令違反につながる可能性もあります。
具体的には、1日あたり平均2.72時間以上の残業が続くと、1か月で60時間を超える計算になります。たとえば月の稼働日が22日であれば、1日あたり約3時間の残業で60時間を超えることになり、多くの中小企業では繁忙期などに十分起こり得る水準です。そのため、残業時間の管理体制を見直し、抑制策を講じることが急務です。
この法改正は、単なるコンプライアンス対応にとどまらず、働き方改革を進めるよい機会でもあります。長時間労働の是正は、従業員の健康を守るだけでなく、業務の効率化や人材の確保・定着にもつながる重要な経営課題です。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働に対して、通常の賃金に加え25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。さらに、月60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率が適用されます。
この規定はもともと大企業に限られていましたが、2023年4月から中小企業にも適用範囲が拡大され、すべての企業が月60時間を超える時間外労働に対して、5割の割増賃金を支払う義務を負うことになりました。人事・労務担当者は、制度の正確な理解と社内ルールの整備が求められます。
月60時間の判定対象となるのは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた時間外労働のみです。法定休日労働(例えば、日曜に出勤するケース)は別カウントとなり、60時間には含まれません。ただし、法定休日労働にも別途35%以上の割増賃金が必要ですので、あわせて管理が必要です。
参考として、稼働日が月22日の場合、1日あたり約2.72時間以上の残業を続けると、1か月で時間外労働が60時間を超える計算になります。繁忙期などで日常的に残業が発生している企業では、対象となる社員が出ている可能性が高いため、早めの確認と対応が求められます。
今回の割増賃金制度の改正は、長時間労働の抑制を目的としています。
すでに大企業では、2010年の労働基準法改正により月60時間を超えた時間外労働について割増賃金率が50%以上に設定されています。ただし、中小企業についてはこれまで猶予期間が設けられ、その間割増賃金率は25%以上のまま据え置かれていました。
働き方改革関連法により猶予期間の廃止が決定したことで、2023年4月1日からは中小企業でも月60時間以上の時間外労働について割増率50%以上の割増賃金を支払う義務を負うこととなりました。
残業が多い企業にとっては、人件費の負担がこれまで以上に大きくなる可能性があるため、働き方そのものの見直しや、長時間労働の是正に向けた取り組みが重要なテーマとなります。
月60時間を超える残業の割増賃金は、具体的にどう計算すればいいのでしょうか?実際の計算方法を、わかりやすい例を使って解説します。
残業代の計算は、基本給をベースに割増率を掛け合わせるシンプルな仕組みです。ただし、月60時間を超える部分は割増率が25%から50%に上がるため、60時間までの部分と60時間を超える部分を分けて計算する必要があります。
例えば、月の残業が65時間になった場合、最初の60時間と残りの5時間では割増率が異なります。この違いをきちんと理解して計算しないと、従業員への支払いが不足したり、労働基準監督署の調査で指摘を受けたりするリスクがあります。
それでは、実際の計算方法を見ていきましょう。計算例を通じて、自社での実務に役立つ知識を身につけていただければと思います。
残業代の計算は、1時間あたりの賃金を基準にして、割増率をかけて支給額を計算します。
【例】月給30万円、所定労働時間160時間の場合
このように、同じ残業でも60時間を超えるかどうかで、1時間あたり約470円もの差が生じます。
※ 割増賃金の計算に用いる「1時間あたりの賃金」は、上記にあるとおり基本的には「月給 ÷ 所定労働時間」で算出できます。ただし、家族手当や通勤手当など労働基準法で割増賃金の基礎から除外される手当は含めないよう注意が必要です(労基法施行規則第21条)。また、固定残業代制を採用している場合は、割増賃金が別途支払われているか、支給方法が適正かも確認が必要です。
【例1】月65時間残業した場合
【例2】月80時間残業した場合
深夜や休日の残業については、さらに計算が複雑になります。
深夜残業の場合:深夜時間帯(22時〜翌5時)に行われた60時間超の残業は、通常の50%に深夜割増分25%が加わり、合計75%の割増になります。つまり、深夜の60時間超残業では、1時間あたりの賃金の1.75倍を支払う必要があります。
休日労働の場合:法定休日(週1日)の労働には原則35%の割増が適用されますが、この時間は月60時間のカウントには含めません。ただし、法定外休日の労働は通常の時間外労働として60時間のカウントに含まれます。
例えば、完全週休2日制を採用している企業で、日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日としている場合、土曜日に出勤した時間は「時間外労働」として扱われ、月60時間のカウント対象になります。
深夜+休日の場合:法定休日の深夜時間帯での労働は、35%+25%で合計60%の割増率となります。
月60時間超の残業対策として、割増賃金の支払いだけでなく「代替休暇制度」という選択肢もあります。この制度をうまく活用すれば、企業の人件費負担を軽減しながら、従業員の休息時間を確保することができます。
代替休暇制度は、従業員にとっても企業にとってもメリットがある「Win-Win」の仕組みといえます。従業員は追加の休暇を取得でき、企業は一部の割増賃金の支払いを抑えられます。特に、繁忙期と閑散期の波がある業種では、繁忙期の長時間労働を閑散期の休暇で相殺できるため、効果的な制度といえるでしょう。
ただし、この制度を導入するには、いくつかの条件を満たし、適切に運用する必要があります。制度設計や運用方法を誤ると、かえってトラブルの原因になりかねません。
それでは、代替休暇制度の詳細とポイントを見ていきましょう。
代替休暇制度とは、60時間を超える時間外労働に対する50%の割増賃金のうち、25%分を、有給の休暇で代替することができる制度です。簡単に言えば、割増賃金の一部を「お金」ではなく「休暇」として従業員に付与する仕組みです。
この制度を導入するには、以下の条件を満たす必要があります。
制度導入の際は、従業員にとってメリットがあることを丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。強制的な導入は避け、選択制にするなど配慮しましょう。
代替休暇の計算は少し複雑ですが、基本的には「50%の割増賃金のうち25%分」を休暇に換算します。
具体的な計算方法は以下の通りです。
代替休暇の時間数={(1か月の法定時間外労働時間)ー(60時間)}✕(換算率)
ここでの換算率は、「代替休暇を取得しない場合に支払う割増賃金率(50%)」から「通常の割増賃金率(25%)」を引いた値、つまり25%(0.25)となります。
例えば、ある月に70時間の時間外労働をした場合:
つまり、2.5時間分の代替休暇が発生することになります。
なお、代替休暇の取得単位は通常、1日または半日単位となっています。上記の例では2.5時間しか発生しませんが、この場合は年次有給休暇と組み合わせることで、半日または1日の休暇として取得できる仕組みになっています。
代替休暇制度を導入する際には、以下のような注意点や失敗例に気をつけましょう。
厚生労働省は、代替休暇を法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内の期間で与えることを定めるよう指示しています。
期間内に代替休暇が取得されなかったとしても企業側の割増賃金支払い義務はなくなりません。その場合は、休暇ではなく50%分の割増賃金の支払いが必要になります。
「休暇がもらえるなら嬉しい」と思っていた従業員が、実際には休暇と引き換えに一部の割増賃金が支給されないことを知らずに制度に同意し、後からトラブルになるケースがあります。制度の仕組みを丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。
代替休暇の発生時間、取得状況、期限切れなどを管理するのは意外と手間がかかります。勤怠管理システムを活用するなど、効率的な管理方法を検討しましょう。
代替休暇制度は正しく運用すれば、従業員のワークライフバランス向上と企業のコスト管理の両立に役立つ制度です。しかし、導入前にしっかりと準備し、丁寧な運用を心がけることが成功のカギとなります。
2023年4月からの法改正への対応は、単なる割増賃金の計算方法の変更だけでは不十分です。中小企業の人事・労務担当者は、法令遵守のために複数の実務対応が必要となります。
会社としての対応が遅れると、労働基準監督署の調査や従業員とのトラブルのリスクが高まります。特に就業規則の変更や36協定の見直しなどの法的対応は、優先度の高い取り組みといえるでしょう。
実務対応は大きく分けて「制度面の整備」「従業員への周知」「運用体制の構築」の3つが重要です。それぞれについて、具体的に何をすべきか、どのように進めるべきかを順に見ていきましょう。
2023年の法改正に伴い、就業規則や36協定の見直しが必要です。特に、代替休暇制度を導入する場合は、協定の記載内容を法令に沿って整備することが重要です。
そもそも時間外労働が60時間を超える可能性がある企業においては、特別条項付きの時間外・休日労働協定(36協定)を結び、就業規則に割増賃金率を記載する必要があります。限度時間(月45時間、年360時間)を超える特別条項を設ける場合は、その特別な事情や延長時間の上限も明記しなければなりません。特別条項を定めずに限度時間を超える時間外労働をさせた場合、労働基準法違反として指導・是正勧告を受ける可能性があります。
就業規則の記載例としては、厚生労働省と中小企業庁が公表している「 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」というリーフレットに具体例が示されています。この資料を参考にして、自社の就業規則を見直すとよいでしょう。
就業規則の見直しについては、「【2023年4月法改正】就業規則の見直しチェックリストと変更時の5ステップ」で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
実務で混乱が起きないよう、制度の背景と対応策を管理職や現場にしっかりと説明し、社内ルールとして定着させる必要があります。
特に現場の管理職は、部下の労働時間管理や残業承認の権限を持っていることが多いため、制度変更の内容を正確に理解してもらうことが重要です。研修やミーティングの場を設け、以下のポイントを説明しましょう。
また、従業員全体に対しても、社内報やイントラネット、掲示板などを通じて制度変更を周知しましょう。特に、残業が多い部署や従業員には、個別に説明することも検討してください。
法改正への対応と同時に、そもそも月60時間を超える残業が発生しないよう、勤怠管理体制を整えることも重要です。
具体的には、以下のような対策が効果的です。
勤怠管理システムを導入していない企業では、エクセルなどを活用した簡易的な管理ツールを作成し、定期的に残業時間をチェックする仕組みを作りましょう。
これらの対策を組み合わせることで、月60時間を超える残業の発生を未然に防ぎ、法令遵守と従業員の健康確保、さらには人件費の抑制にもつながります。
割増賃金率が変更されることはわかっていても、具体的にわからない部分も多いでしょう。月60時間残業の割増賃金率に関するよくある質問3つを取りあげて解説します。
変形労働時間制と管理監督者では、残業代の計算方法が大きく異なります。
変形労働時間制には、1年単位、1か月単位、1週単位の3種類があり、それぞれ残業時間の算出方法が異なります。
変形労働時間制の残業時間の算出方法
管理監督者の場合、1日8時間、週40時間を超えて働いても、法定時間外労働とはみなされず、時間外手当や休日手当は発生しません。ただし、深夜割増賃金は時間帯によって規定されているため、管理監督者でも受け取ることができます。
なお、ここでいう「管理監督者」とは単なる役職名ではなく、以下の条件を満たす必要があります。
いわゆる「名ばかり管理職」は管理監督者には該当せず、通常の従業員と同様に残業代が発生します。
労働時間を適切に把握しないと罰則の対象となる可能性があります。
2019年4月に施行された働き方改革関連法により、労働安全衛生法が改正され、事業主に対して労働者の労働時間の状況を客観的な方法で把握することが義務付けられました。これは、過重労働による健康障害を防止するための重要な措置です。
具体的には、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録など、客観的な記録に基づいて労働時間を把握する必要があります。自己申告制を採用する場合も、実態と乖離がないよう適切な措置を講じなければなりません。
労働時間の把握を怠った場合、労働安全衛生法違反として是正勧告の対象となります。
さらに、労働時間の把握を怠った結果、残業代の未払いが発生した場合は、未払賃金の支払いや付加金の支払い命令など、追加のペナルティを受ける可能性もあります。
これは少し複雑ですが、割増率ごとに分けて計算する方法と、統一した換算率を定める方法があります。
例えば、所定労働日の時間外労働に対する割増賃金を25%、法定休日以外の休日の労働に対する割増賃金率を35%と定めている場合で、これらを合計した時間外労働時間数が月60時間を超えたとします。
この場合、代替休暇の時間数の計算は以下の手順で行います。
なお、双方の換算率が同一となるように労使協定で定めることも可能です。
(参考: 改正労働基準法に係る質疑応答)
月60時間超の残業に対する50%割増賃金への対応について、人事・労務担当者の皆さんの負担を少しでも軽減できるよう、実務で使えるチェックリストをご用意しました。
以下の項目を一つずつ確認しながら、確実に法改正対応を進めましょう。
□ 36協定の特別条項は月60時間超の残業に対応できているか?
□ 就業規則の割増賃金率の記載を変更したか?
□ 就業規則の変更について従業員の意見を聴取したか?
□ 変更した就業規則を労働基準監督署に届け出たか?
□ 代替休暇制度を導入する場合、労使協定を締結したか?
□ 代替休暇制度を就業規則に明記したか?
□ 対象社員全員に制度変更の説明を行ったか?
□ 管理職に対する研修・説明会を実施したか?
□ 質問対応窓口を設置したか?
□ 勤怠システムで60時間の自動把握が可能か?
□ 給与計算システムの設定変更は完了したか?
□ 残業時間のアラート通知の仕組みを整備したか?
□ 部署別・社員別の残業時間の分析を行ったか?
□ 恒常的に月60時間超の残業が発生している部署への対策を講じたか?
□ 業務効率化・平準化の取り組みを開始したか?
□ 定期的な労働時間の確認体制を整備したか?
法改正への対応は、単なる割増率の変更だけでなく、複数のステップを確実に実行することが重要です。対応漏れがあると、労基署の調査や従業員とのトラブルの原因になりかねません。チェックリストを活用して、抜け漏れのない対応を進めましょう。
2023年4月から中小企業にも適用されるようになった「月60時間超の残業に対する5割の割増賃金」は、単なる法令対応にとどまらず、会社全体の働き方や労務管理体制の見直しを促す契機でもあります。以下の4つのポイントを特に意識して対応を進めましょう。
最後に、法令遵守はもちろん、社員の健康と生産性を守るためにも、正しい制度理解と実効性のある運用が求められます。本記事を参考に、自社の現状を見直し、早期対応を進めていきましょう。
| Q1.月60時間を超える残業の計算は暦月単位ですか?締め日がある場合はどうなりますか? |
|---|
|
月60時間超の残業割増賃金の計算は、会社の賃金締切期間(給与計算期間)で判断します。暦月(1日〜末日)ではなく、例えば「毎月16日〜翌月15日」といった締め日で運用している場合は、その期間内での時間外労働時間が60時間を超えるかどうかで判断します。法令上も賃金締切期間での管理が認められていますので、自社の給与計算サイクルに合わせて対応しましょう。 |
| Q2.固定残業代(みなし残業)制度を採用している場合、月60時間超の残業にはどう対応すればよいですか? |
|
固定残業代制度を採用している場合でも、月60時間を超える残業については50%の割増率を適用する必要があります。例えば、45時間分の固定残業代を支給している場合、45時間までは固定残業代でカバーされますが、46〜60時間は通常の25%割増、60時間超は50%割増で別途計算して支給する必要があります。固定残業代制度を採用している企業は、契約書や就業規則の規定を見直し、60時間超の残業に対応できる内容になっているか確認しましょう。 |