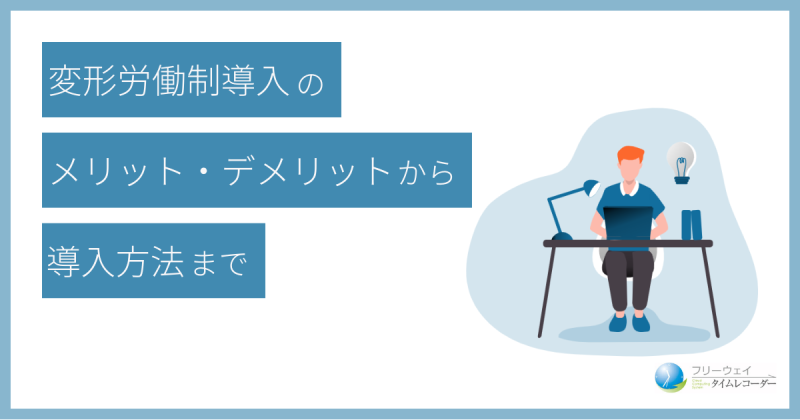
変形労働制とは、業務の繁忙期に合わせて「週・月・年単位」で労働時間を調整できる制度のことです。自社の実態に合わせ労働時間を変更できるため、状況に対応しながら柔軟かつ効率的に事業を進めることができます。従業員にとっても、ワークライフバランスを整えやすくなる点が魅力です。一方で導入に手間がかかったり、逆に従業員が不満を持ってしまう可能性があるなど、リスクも存在します。
そのため、変形労働制のメリット・デメリットを綿密にチェックし、自社の実態にマッチした判断を下すことが大切です。
本記事では、変形労働制導入のメリット・デメリットや導入方法をわかりやすく解説します。
目次
変形労働制とは、業務の繁忙期に合わせ、労働時間を「週・月・年単位」で調整できる制度のことです。1987年の労働基準法改正にて導入されました。
労働基準法では「1日8時間・1週間40時間を超える労働をさせてはならない」と定められています。しかし業種や企業によっては、特定の時期に申し込みや依頼が集中するなどの理由で、繁忙期と閑散期で必要な労働時間に差が出てしまうケースもあります。
そのようなケースでは、変形労働制を導入し、法定労働時間を1週間・1ヶ月・1年単位で調整して「多忙な年末だけ労働時間を延ばし他の時期は短縮する」といった勤務体系を実現することで、効率的かつ柔軟な事業運営が可能になります。変形労働時間制を採用する際の「変形期間」では、平均の労働時間が1週間で40時間を超えなければ、法定労働時間を超えて勤務でき、時間外労働としても扱われません。
変形労働制の種類としては、主に以下の「変形期間の長さに基づく3つ+フレックスタイム制」が挙げられます。
| 種類 | 概要 | 参照 |
|---|---|---|
| 1年単位の変形労働制 | 「1ヶ月を超える1年以内の一定期間」が変形労働の対象。変形期間内の平均労働時間が「1週間あたり40時間以下」となっていれば、一定限度内の特定の日・週について、法定労働時間を超えて労働させることができる。 | 厚生労働省|1年単位の変形労働時間制導入の手引 |
| 1ヶ月単位の変形労働制 | 1ヶ月以内において、「1週間あたりの平均労働時間が40時間以内」となるよう調整することで、特定の日は8時間、特定の週は40時間を超えて労働させることができる。 | 厚生労働省|1か月単位の変形労働時間制 |
| 1週間単位の変形労働制 | 労働が40時間を超えず、かつ1日10時間を上限として、1週間単位で毎日の労働時間を柔軟に変更できる。 | 兵庫労働局|1週間単位の非定型的変形労働時間制 |
| フレックスタイム制 | 期間別の変形労働制と異なり、1日の始業時間や就業時間をある程度自由に決められる。「法定労働時間を超えたから時間外労働扱い」「1日の標準労働時間に足りないから欠勤扱い」とならないため、柔軟に働き方を調整できる。 | 厚生労働省|フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き |
変形労働制と似た制度として、以下の2つが挙げられます。誤った認識のまま自社で採用しないよう、必ず確認してください。
| 類似制度 | 概要および違い |
|---|---|
| シフト制 | 労働契約の締結時点では、労働日や労働時間を確定させず、一定期間(1週間や1ヶ月など)ごとにシフトを作成し、初めて具体的な労働日や労働時間を確定させる。 |
| 裁量労働制 | 業務遂行の手段や時間配分を企業が指示することが難しい場合に、従業員個人の裁量で労働時間を決める。実働時間に関わらず、企業は「一定時間労働したもの」とみなして従業員へ給料を支払う。 |
関連記事: 裁量労働制とは?仕組みや対象職種、メリット・デメリット、導入方法などをわかりやすく解説
変形労働制の導入メリットを、まずは企業視点で解説します。
変形労働制では「繁忙期は延ばして閑散期は短縮する」というように、時期や企業の状況などに合わせ労働時間を柔軟に設定できます。忙しいタイミングで人員を増やせるため、繁忙期であっても十分な人手を確保し、効率的に業務を遂行可能です。
また、閑散期に労働時間を短縮し必要最低限の人員で業務を遂行できれば、従業員の負担を減らしメリハリある働き方を実現してもらいやすくなります。働き方のオン・オフを明確に分けて、従業員の仕事へのモチベーションを高めてもらえれば、最終的な企業全体の生産性向上を実現できるかもしれません。
変形労働制を活用すれば、繁忙期の所定労働時間の基準を延ばせます。この延ばした労働時間の範囲内であれば、従業員が残業しても残業代を支払う必要はありません。
企業視点でいえば、残業代の支払いを抑えられるに越したことはありません。そのため、変形労働制によって所定労働時間の基準を延ばせるというのは、大きなメリットです。
変形労働制を導入すると、従業員は「繁忙期を避けて長期旅行のスケジュールを立てる」「子どもの長期休み期間に合わせて労働時間を短縮する」というように、柔軟な働き方を実現しやすくなります。
こうした「柔軟な働き方を実現できる企業である」という印象を発信すれば、世間からのイメージアップにつながるかもしれません。世間からのイメージが高まれば、「消費者から自社商品を選んでもらいやすくなる」「採用活動での応募者増加が期待できる」といったメリットを実感しやすくなります。
変形労働制によって労働時間を柔軟に調整できれば、上記で解説したように、従業員は自分のプライベートと仕事を両立しやすくなります。閑散期にまとまった休みを確保できるため、日頃の疲れもじっくり癒せるはずです。
このように従業員が働きやすい職場環境を構築することで、企業への満足度が高まり、仕事のモチベーションアップを期待できます。モチベーションが上がり、従業員が自発的に「仕事を効率化するにはどうすればよいか?」「もっと成果を残すには何をやるべきか?」などを考えられるようになれば、最終的な業績向上や定着率の改善も実現しやすくなります。とくに人材不足で悩む企業からすると、従業員の定着率が上がるというのは大きなメリットです。
一方で、変形労働制には以下のようなデメリットがあります。
変形労働制を導入する際は、以下のような負担が発生します。
労働基準法で定められた「1日8時間・1週間40時間」という原則と異なるルールを設けるため、導入や運用に大きな手間がかかります。とくに従業員の働き方を管理する人事労務担当者は、業務量の増大が避けられません。
なるべく担当者の負担が膨らみすぎないよう、企業は「制度が定着するまで部署の人数を増やして対応する」といった方法でフォローしてください。
変形労働制では労働時間が変わるため、従業員が不公平感や不満を持つ可能性もゼロではありません。例えば、特定の部署Aのみで導入した場合、「部署Bが働く中で部署Aの従業員が先に帰る」という事態が起こり得ます。こうしたことが続けば、「なぜ自分の部署だけ帰れないのか?」と不満を抱いても伏木ではありません。
また、変形労働制では労働時間の基準が延びるため、繁忙期に残業してもなかなか残業代が増えない可能性があります。残業代で収入を高めていた従業員からすると、「繁忙期に長時間働いても残業代があまり増えない」というのは大きなネックとなります。
こうした不満を従業員が抱かないよう、企業は各部署の働き方の実態を正確に調査し、全社で変形労働制の意義を共有したうえで慎重に導入することが求められます。
続いて、従業員視点で見たときの変形労働制のメリットを解説します。
従業員のメリットも把握することで、変形労働制のメリットを十分に説明できるようになり、納得してもらいやすくなるかもしれません。
変形労働制では、各時期の業務量に応じて労働時間を柔軟に延ばしたり短縮したりできます。そのため、「業務が少ない閑散期なのに所定の時間内は職場にいなければならない」といったストレスを軽減し、仕事量に応じた適切な働き方を実現可能です。従業員の希望や現場の実態にマッチすれば、「閑散期は週休3日制でOK」という調整もできます。
変形労働制を利用すれば、業務量が少ない閑散期に以下のような対応が可能です。
閑散期に心置きなくリフレッシュできるため、働き方にメリハリをつけて仕事へのモチベーションを高められます。繁忙期ならではの「休日に緊急連絡が入るのでは?」「人手が足りずいきなり出勤を命じられるのでは?」といった不安から解放されて、思い切り休日を楽しめるというのは、従業員にとって大きなメリットです。
変形労働制では「繁忙期はプライベートの確保が難しいが閑散期は早く帰れる」といったことが決まっています。そのため、「閑散期に長期旅行の計画を立てる」「子どもの長期休みに合わせて早く帰る」など、プライベートの予定も立てやすい点が魅力です。
一方で、従業員視点でも以下のようなデメリットがあります。
制度を導入するにあたり、従業員との認識違いによるトラブルを防ぐには、デメリットも正しく共有し適切に判断してもらうことが必要です。
変形労働制を導入すると、閑散期は労働時間を短縮したり休日を増やしたりできます。しかし一方で、繁忙期は基準となる労働時間自体が延びるため、残業がさらに増えるかもしれません。
当然ですが、従業員全員が「繁忙期が忙しくても閑散期にまとまって休めればOK」と考えるわけではありません。「時期ごとに偏るのではなく毎月安定して休みたい」と考える従業員もいます。そのため、繁忙期に残業が増える可能性も考慮し、可能な限り幅広い従業員の意見を反映することが大切です。
繁忙期に労働時間が延びても、「変形労働制で定めた範囲内」の場合は原則として残業と扱われません。そのため残業代が減少し、最終的な従業員の手取り額に影響を与える可能性があります。閑散期にまとまった休みを取れるとはいえ、手取りが減る可能性というのは従業員からすると痛手です。
特定の部署のみで変形労働制を導入すると、他部署と稼働時間が合わず「新商品の打ち合わせを行いたいが予定が合わない」などが起こりやすくなります。部署間の足並みが揃わなければ、業務の進行に影響を与えてしまい、最終的な生産性の低下を招くかもしれません。
また、顧客の稼働時間とも合わなくなれば、「問い合わせを受けたが担当者が不在だった」といったケースが発生しやすくなります。もちろん、従業員の休日を守ることは大切です。とはいえ、顧客へのレスポンスが悪くなると、自社の信頼性に影響を与えるかもしれません。
上記のようなコミュニケーションの取りにくさを減らすには、「従業員同士のスケジュールをリアルタイムにチェックできる仕組みを整える」「自社の働き方について顧客へ説明し理解を得ておく」といった対策が必要です。
変形労働時間制の具体的な導入方法は、以下の通りです。
導入前に、必ず時期ごとで従業員の労働時間や勤務実態、業務量などをチェックし「本当に制度を導入すべきか?」を精査してください。現場の実態にマッチしない変形労働制を導入すると、従業員へ余計な負担を与えるリスクがあります。
例えば、繁忙期と閑散期でほとんど業務量の差がない部署で変形労働制を導入すると、「閑散期なので周囲は早帰りしているが自部署はタスクがあるので残業しないといけない」という状況が発生しかねません。
実態にそぐわない制度は、従業員のストレス要因となるだけでなく生産性低下も招くため、必ず現場の勤務実態を調査してください。
導入を決定したら、制度の要件を定めます。具体的には、以下の項目を明確にしてください。
「業務量が多い繁忙期→所定労働時間を延ばす」「業務量が少ない繁忙期→所定労働時間を短縮する」という考え方が基本です。
各項目のより具体的な決め方は、以下の資料をご覧ください。
変形期間の所定労働時間は、平均が法定労働時間を超えないよう、以下の計算式で求めます。
| 40時間×(変形期間の暦日数)÷7 |
|---|
上記をもとにすると、変形期間の暦日数ごとにおける労働時間の総枠は以下のようになります。
| 変形期間の暦日数 | 労働時間の総枠 |
|---|---|
| 28日 | 160時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 31日 | 177.1時間 |
| 92日(3ヶ月) | 525.71時間 |
| 122日(4ヶ月) | 697.14時間 |
| 183日(6ヶ月) | 1045.71時間 |
| 365日(1年) | 2085.71時間 |
変形労働制の具体的な要件を決めたら、就業規則の内容を見直し、必要に応じ修正してください。変形期間の労働時間や対象要件などを誰でも理解できる形でまとめておけば、従業員との認識違いによるトラブルを防ぎやすくなります。
就業規則の見直し方法については、「【2023年4月法改正】就業規則の見直しチェックリストと変更時の5ステップ」で詳しく解説しています。
変形労働制を導入する際は、労使協定の締結が必要です。 労使協定とは、企業と従業員間で取り決めた「労働条件に関する契約」を指します。労使協定を締結することで、変形労働制を導入し自社の実態にマッチした働き方を推進できます。労使協定によって変形労働制を導入する場合は、労働基準監督署への届出も必要です。
労使協定の締結手順や運用のポイントなどは、「労使協定とは?36協定との違いや種類、締結ステップなどをわかりやすく解説!」をご覧ください。
制度を制定したら、変形労働制の詳細や就業規則の内容を従業員へ周知してください。以下のように、誰もが目につく形で周知することが必須です。
変形労働制を導入・運用する際は、以下の点に注意してください。
変形労働制を導入すると、どうしても繁忙期に業務が偏らざるを得ません。一時期であっても、過度に従業員の負担が増えれば、職場に不満を感じ離職する可能性もあります。
そのため、繁忙期における従業員の負担を解消できるよう、企業が積極的に以下のような取り組みを行うことが大切です。
変形労働制を導入したとしても、従業員が「事前に定めた労働時間の総枠」を超えて働いた場合、超えた部分について別途で残業代の支払いが必要です。 具体的には、以下の3パターンが当てはまります。
詳細は「厚生労働省|1か月単位の変形労働時間制をとる場合の時間外労働の考え方」にまとめられています。
従業員の実働時間が所定の労働時間を越えたとしてもときは、余剰分を翌日または翌月に繰り越すことはできません。
例えば、フレックスタイム制の清算期間における総所定労働時間を1ヶ月150時間と設定したとします。このとき、1ヶ月の実働時間が180時間であった場合、超過した30時間分の賃金は、当月に時間外手当として支払われなければなりません。翌月の総労働時間の一部に充当することはできません。
変形労働制の運用開始後に、「やはり別の時期に適用したい」「労働時間を修正したい」といった変更はできません。そのため、導入前に社内の勤務実態を綿密に調査し、以下のような項目を細やかに検討することが大切です。
可能な限り、時期ごとの残業時間や顧客への影響度合いなどを数値化し、根拠を持って検討すると失敗確率を下げられます。
変形労働制では、時期や導入部署ごとなどで勤怠管理が異なる可能性があります。同じ時間だけ働いても「繁忙期は残業代の計算は不要だが閑散期は必要」といったことになるため、勤怠を管理する人事労務担当者の負担はどうしても膨らむはずです。
こうした勤怠管理の手間を少しでも軽減するためにも、勤怠管理システムの導入を検討してみてください。勤怠管理システムとは、従業員の出退勤時間や休憩時間、残業時間、有給取得日、シフトなどを管理できるシステムのことです。勤怠管理システムでは、ICカードやブラウザなどを利用して手軽に労働時間を記録できます。手書きのタイムカードで起こりやすい勤怠記録の書き換えも防止できるため、従業員の働き方を問わず正確な管理が可能です。
また、変形労働制の導入前から勤怠管理システムを導入すれば、記録データをもとに「どの部署で残業が多いのか?」「閑散期はいつなのか?」などを分析し、検討時に役立てられます。
「勤怠管理システムとは?機能や導入メリット、初めての方でも迷わない選び方のポイントなどを詳しく解説」では、具体的な製品の機能や選び方などを解説しているため、製品の導入を検討している場合はぜひ活用してください。
変形労働制を導入すると、「業務効率化を実現できる」「従業員のモチベーションアップにつなげられる」といったメリットがあります。繁忙期と閑散期で労働時間を変更できるため、時期に合わせて働き方を柔軟に調整したいと考える企業にとっては魅力的です。一方で「制度の導入に手間がかかる」「不公平感を持つ従業員がいるかもしれない」といったデメリットもあります。
そのため、制度を導入する際はメリット・デメリットの両方を丁寧にチェックし、自社の勤務実態も照らし合わせたうえで検討してください。
| Q1.変形労働制のメリット・デメリットは? |
|---|
|
企業・従業員、それぞれの視点で見た際のメリット・デメリットは、以下の通りです。 【企業視点のメリット】
【企業視点のデメリット】
【従業員視点のメリット】
【従業員視点のデメリット】
|
| Q2.変形労働制の導入方法は? |
|
変形労働時間制の導入方法は、以下の通りです。
|
| Q3.変形労働制で働く時間は? |
| 変形労働制で働く時間は、企業が独自に設定できます。現場の実態に合わせて労働時間を決定することが重要であり、導入前にヒアリングしたり勤怠管理システムのデータをチェックするのがおすすめです。 |
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員10人まで永久無料の勤怠管理システム「フリーウェイタイムレコーダー」を提供しています。フリーウェイタイムレコーダーはクラウド型の勤怠管理システムです。ご興味があれば、ぜひ使ってみてください。