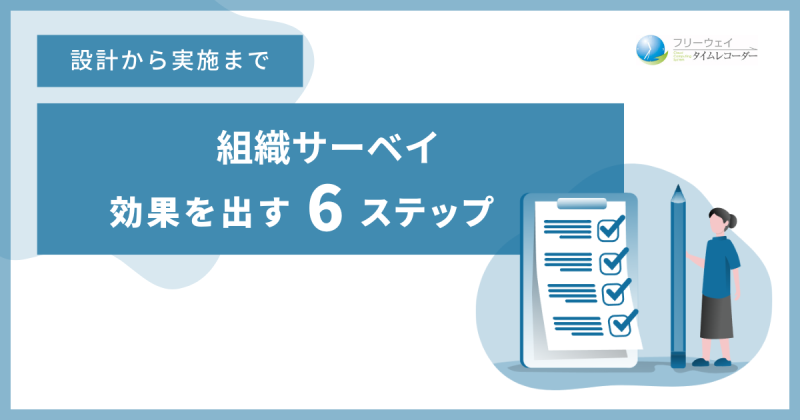
「組織の課題を把握したいが、具体的に何を調査すればよいかわからない」「離職率が高まっているが、その原因を明確にできていない」
このような悩みを抱える企業は少なくありません。組織の状態を正確に把握し、適切な対策を講じるためには、データに基づいた分析が不可欠です。
そこで有効なのが「組織サーベイ」です。組織サーベイを実施することで、従業員の意識や職場環境に関するデータを収集し、課題の特定、改善施策の立案、経営判断の精度向上につなげることができます。
本記事では、組織サーベイの種類や手法、実施するメリット、注意点、導入すべき企業の特徴などを詳しく解説します。
組織サーベイとは、企業が組織の現状を可視化し、課題を明確にするための調査手法です。集計・分析を行い、その結果をもとに適切な施策を検討・実施し、再度サーベイを行うことで、継続的な組織改善につなげるサイクルを構築します。
また、従業員の意識に関するデータを収集し、職場の雰囲気やコミュニケーションの実態、価値観を分析することで、組織課題の明確化を図り、組織開発の方向性を決定する役割も担います。
近年のビジネス環境の変化に伴い、企業は従業員の意識やモチベーションの把握を重視するようになっています。特にリモートワークの普及により、従業員の働き方や意識の変化を把握する必要性が高まっており、組織サーベイの活用が広がっています。
組織サーベイの種類は2つあります。
エンゲージメントサーベイは、従業員が主体性や情熱をもって仕事に取り組み、組織目標の達成にどの程度関与しているかを測定するための調査です。
エンゲージメントとは、企業への愛着や貢献志向のことを指し、働きがいに転じえます。そのため、生産性を向上させたい企業には重要な指標となります。
実際、厚生労働省の令和元年版「労働経済の分析」からは、ワーク・エンゲージメントスコアが高いほど生産性が向上する傾向があるとわかります。

引用:厚生労働省『令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-』
そのため、エンゲージメントサーベイは、組織の活性化や、従業員個人と組織全体の成長を促進する目的で実施されることが多い調査です。
モラールサーベイは、従業員の士気やモチベーションを評価するための調査です。働きやすい職場環境の構築を目的とし、従業員満足度、不満要素、職場の士気などを把握するのに活用されます。
モラールサーベイでは、従業員の満足度を測定し、ストレス要因を特定することで、企業が適切なサポートや環境改善を行うための指針となります。特に、離職率の高さが課題となっている企業では、職場環境の改善に向けた具体的な対策を講じるために不可欠な手法です。
組織サーベイの実施方法は2つあります。
センサスサーベイは、半年~1年に1回程度の頻度で実施され、設問数が多く、詳細な分析が可能な調査方法です。組織の長期的な課題を明らかにするのに適しています。
パルスサーベイは、1週間~1カ月に1回程度の頻度で実施される短期的な調査手法です。少ない設問数で迅速に組織の現状を把握し、素早く対策を講じるのに有効です。
これまで組織サーベイについて説明してきましたが、実際にどのようなメリットがあるのでしょうか。本章で解説します。
1つ目のメリットは、組織内課題の早期発見です。
組織サーベイを活用することで、従業員の意識や職場環境に関するデータを収集・分析し、組織の問題点を早期に発見できます。これにより、迅速に適切な対策を講じることが可能になります。
また、従業員のストレスや不満の蓄積を未然に防ぎ、企業の健全な成長を促す役割も果たします。問題が大きくなる前に対応することで、組織全体の安定性を確保できます。
2つ目のメリットは、離職防止とそれに付随する生産性の向上です。
サーベイ結果を基に職場環境を改善し、社内制度を見直すことで、従業員満足度を向上させ、離職率の低下や生産性の向上につなげることができます。
特に、適切なフィードバックと施策の実施によって、従業員が働きがいを感じられる職場を構築することが可能になります。従業員が安心して働ける環境を整えることで、チームの結束力も高まり、業務効率の向上につながります。
3つ目のメリットは、データに基づいた科学的な経営判断の実現です。
組織サーベイによって得られたデータを活用することで、感覚や経験則に頼らない科学的な経営判断が可能となり、組織全体の戦略策定や施策実行の精度が向上します。これにより、組織の現状を正確に把握し、戦略的な意思決定の精度を向上させることができます。
例えば、離職率の増加が問題になっている場合、従業員の満足度や働き方に関するデータを分析し、具体的な原因を特定することができます。その結果に基づいて、福利厚生の見直しやワークライフバランスの改善策を講じることが可能になります。
また、従業員の意識調査を継続的に実施することで、組織の成長に伴う課題を事前に把握し、適切な対策を講じることができるようになります。このように、データに基づいた科学的なアプローチが、企業の持続的な発展につながります。
組織・従業員双方にメリットをもたらす組織サーベイですが、実施する際に注意点があります。
1つ目の注意点は、コストと従業員の負担です。
組織サーベイの実施にはコストや時間がかかるため、計画的に進めることが重要です。調査の設計・実施・分析・フィードバックまでのプロセスを確実に管理しないと、うまく調査が進まない、調査しても結果が的確に収集できないということがあります。
また、従業員の負担も考慮しなければなりません。特に、従業員50人以上の事業場では、厚生労働省の定めるストレスチェック制度が義務化されており、これと組織サーベイが重複すると、従業員に負担がかかる可能性があります。そのため、すでに実施している調査との統合や、頻度の調整を行うことで、調査疲れを防ぐ工夫が求められます。
2つ目の注意点は、データの信頼性を確保できるようにすることです。
組織サーベイの結果が正確であるためには、従業員が率直に回答する環境を整えることが不可欠です。特に、匿名性を確保しないと、従業員が本音を隠したり、組織に対する批判を避けるために意図的に回答を調整するケースが発生します。
そのため、アンケート実施前に「回答は個人を特定しない」ことを明確に伝え、従業員が安心して本音を述べられるような環境を整備することが大切です。また、外部の第三者機関に調査を依頼することで、より信頼性の高いデータを収集することも選択肢の一つです。
3つ目の注意点は、フィードバックとそれをもとにした改善策の実行です。
組織サーベイを実施しただけで終わらせず、結果を分析し、適切な改善策を講じることが最も重要です。サーベイ後に適切なアクションが取られなければ、従業員の不信感を招き、次回以降のサーベイへの協力意欲が低下する可能性があります。
そのため、調査結果は可能な限り迅速に従業員と共有し、改善計画を明示することが重要です。加えて、改善策の進捗を定期的にフォローし、再度のサーベイを通じて施策の効果を検証することが、組織改善の成功につながります。
この章では、組織サーベイを導入すべき企業と、そうした企業が選ぶべきサーベイの種類を説明します。
エンゲージメントサーベイは、従業員の組織への関与度や主体性を測定し、企業文化の強化や従業員のモチベーション向上に貢献します。
以下のような目標をもった企業に適しています。
▼導入が特に有効なケース
モラールサーベイは、従業員の士気や満足度を測定し、職場環境の改善やストレスマネジメントに役立ちます。
以下のような目標をもった企業に適しています。
▼導入が特に有効なケース
この章では、実際に組織サーベイを実行する際の手順を紹介します。
まず、サーベイの目的を明確に定義し、経営陣や人事部が抱えている課題を整理します。例えば、離職率の低下、エンゲージメントの向上、業務プロセスの改善など、目的に応じて調査の方向性を決定します。
続いて、既存のデータ(勤怠、業績評価、離職率など)を活用し、組織の課題やその原因を仮説として設定します。この段階で、どのようなサーベイ項目を設けるべきかを決定するための指針を作ります。
いよいよ調査設計です。仮説に基づき、調査項目を決定します。エンゲージメントサーベイであれば、仕事の意義や組織のビジョンへの共感度を測定する設問を含めるなど、目的に応じた質問を設計します。また、調査方法(オンラインアンケート、個別インタビュー、グループディスカッションなど)を選定します。
調査設計が完了しても、すぐに実行はしません。サーベイを実施する前に、従業員に対して目的やメリットを説明し、協力を得ることが重要です。匿名性が確保されていることや、フィードバックを行う予定であることを明確に伝えることで、より正直な回答を得られる可能性が高まります。
サーベイ終了後は、得られたデータを分析し、傾向や問題点を明らかにします。従業員にも結果を共有し、サーベイを通じてどのような気づきを得たのか、どのような対策を講じるのかを説明することで、従業員の理解と協力を得やすくなります。
最後に、分析結果をもとに具体的な改善策を策定し、実行します。改善策の進捗を追跡し、定期的なフォローアップを行うことで、継続的な組織改善を実現できます。
組織サーベイは、企業の持続的な成長を支える重要な取り組みです。適切な調査方法を選び、得られたデータを活用することで、従業員の満足度向上、組織のエンゲージメント強化、そして経営の意思決定の質の向上を実現できます。
定期的なサーベイの実施と改善サイクルの確立により、組織の強化と発展を図り、より良い企業文化の構築を目指しましょう。
| Q1.組織サーベイとは? |
|---|
| 組織サーベイとは、企業が組織の現状を可視化し、課題を明確にするための調査手法です。集計・分析を行い、その結果をもとに適切な施策を検討・実施し、再度サーベイを行うことで、継続的な組織改善につなげるサイクルを構築します。 詳しくは「組織サーベイとは」の章をご覧ください。 |
| Q2.組織サーベイの種類は? |
| 組織サーベイの種類は、エンゲージメントサーベイとモラールサーベイの2種類があります。 前者は従業員の企業に対する貢献志向や仕事への積極性をはかるもので、企業と従業員の結びつきをはかるものです。 後者は従業員の満足度や不満を調査するものです。働きやすい職場を目指す企業が多く用います。 詳しくは「組織サーベイの種類」の章をご覧ください。 |