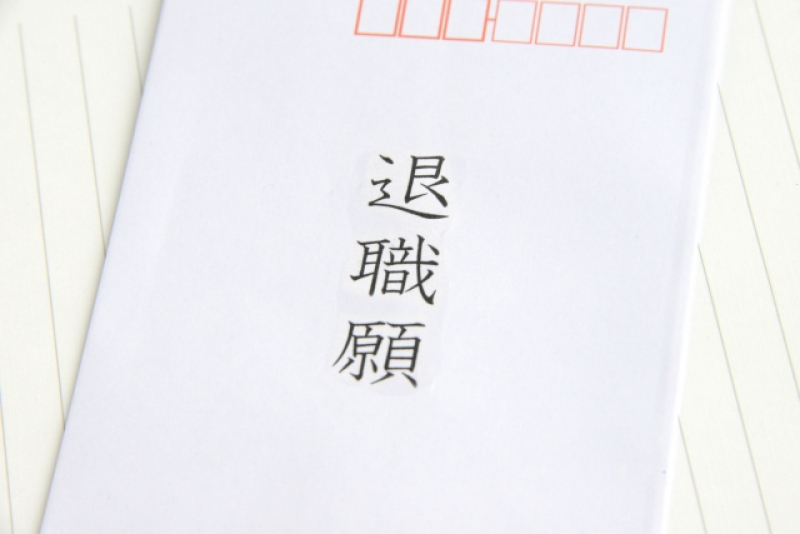
企業が組織の人件費削減や最適化を図るために導入を検討している早期退職制度は、定年前に従業員に一定の優遇措置を設けることで自発的な退職を促す制度です。
「企業の若返りを促進して活性化を図る」「従業員のセカンドキャリアを支援する」といったポジティブな目的で運用されます。
早期退職制度には、企業と従業員、それぞれにメリットがあります。例えば、企業であれば「組織の活性化を実現できる」、従業員であれば「退職金を割増で受け取れる」などです。ただし、双方にデメリットもあるため、両方を考慮し自社にマッチした制度を設計することが重要です。
今回の記事では、早期退職制度の概要やメリット・デメリット、導入ステップ、運用ポイントなどを解説します。
目次
早期退職制度とは、後述の希望退職制やリストラとは異なり、定年前に従業員が退職を希望できる制度のことです。主に以下を目的として実施します。
従業員に退職金割増のような優遇措置が設けられることがあり、福利厚生の一環として早期退職制を整備している企業もあります。
早期退職者の対象条件は、以下のように企業が自由に設定可能です。
年齢設定も自由ですが、「キャリアを活用して再就職や独立などを視野に入れられる」「人件費の大幅な削減につなげやすい」といった理由で、40〜50代を対象にすることが一般的です。
早期退職制度と類似している制度として、以下の2つが挙げられます。
「定年前の従業員が自発的に退職するか選べる」という点は、早期退職制度と同じです。しかし、以下のように目的が異なります。
| 早期退職制度 | 希望退職制度 | |
|---|---|---|
| 目的 | 従業員のキャリア支援を含め、福利厚生の一環として運用 | 業績悪化や事業縮小など、企業の都合に伴う人員整理の一環で行う。リストラの前段階で実施するイメージ |
| 退職時の扱い | 「自己都合退職」として扱われることが一般的 | 「会社都合退職」として扱われることが一般的 |
| 実施する時期 | 福利厚生として設定されているため時期を問わない | 企業の業績に合わせ時期を限定して行う |
希望退職制度も「従業員の希望に応える」という形を取っていますが、リストラの前段階として実施することが一般的です。そのため企業の事情で退職する側面が強く、「会社都合退職」として扱われます。
実施時期についても、企業の業績状況や組織再編の必要性などに合わせるため、早期退職制度と異なり限定的です。
選択定年制(早期退職優遇制度)とは、定年の年齢を企業と従業員本人が話し合って決定する制度です。主に以下の違いがあります。
| 早期退職制度 | 選択定年制(早期退職優遇制度) | |
|---|---|---|
| 実施内容 | 一定の優遇措置を設け、定年前の従業員に自発的な退職を促す制度 | 従業員と話し合い、定年の年齢を決めてもらう制度 |
| 退職時の扱い | 「自己都合退職」として扱われることが一般的 | |
定年の年齢は「60〜65歳」の間で決めることが一般的です。
定年の年齢の選択時期や具体的に選べる年齢などは、企業によって異なります。例えば、過去には「55歳で制度を説明→57歳で定年の年齢を選択→59歳で最終確認」という企業がありました。
自分の意思で定年の年齢を決めるため、「自己都合退職」として扱われることが一般的です。
早期退職制度には、「企業視点・従業員視点」の両方でメリットとデメリットがあります。制度を導入する場合は、それぞれを比較・検討し、本当に自社の実態にマッチしているか判断してください。
まず「企業視点」における早期退職制度のメリットは以下の通りです。
早期退職を実施し、一定年齢(主に40〜50代)以上の従業員が退職することで、空いたポストに若手が就任しやすくなります。組織の新陳代謝が促されることで、「職場の雰囲気を一新する」「若手ならではの視点で事業に新たな発想を取り入れる」といったことができるため、企業の成長につなげることが可能です。
さらに組織を若返らせることで、自社の「若手人材」にも大きなメリットを与えられます。若手人材からすると、努力次第で出世できるチャンスが広がるため、仕事へのモチベーションも高まります。若手が活躍してスキルを身に付け、早い段階でさらに次の世代を育成できれば、企業の成長も早まるはずです。
日本は年功序列を採用している企業が多いため、勤続年数が高いほど従業員の給料も高くなる傾向にあります。そのため、勤続年数の長い40〜50代が早期退職することで、企業は大幅に人件費を削減可能です。
削減した人件費を「成果を出している若手に回す」「新規事業への投資に回す」など別の部分へ投下できれば、将来的な企業の成長促進も期待できます。
解雇によって従業員を退職させる場合、「何度注意しても遅刻が改善されない」「意図的な命令違反によって企業に多大な損害をもたらした」というように、社会常識と照らし合わせて納得できる理由が必要です。そのため人件費の削減や若返りに向けて解雇が必要でも、実施のハードルが高く、従業員とトラブルになる可能性も0ではありません。
早期退職制度を活用すれば、従業員自身が納得したうえで退職するため、上記のようなトラブルのリスクを大幅に削減し円満退職を実現できます。
次に「従業員視点」における早期退職制度のメリットは以下の通りです。
制度を設ける際、メリットを従業員へ丁寧に説明することで、円滑な制度利用や退職を促せるため、事前に確認しておきましょう。
早期退職制度を利用した従業員は、退職金が割増で支払われるケースが一般的です。具体的な割増金額に関する法的ルールはありませんが、一般的には「3ヶ月〜1年半分」程度を上乗せします。
企業によっては、早期退職制度の利用者に向けて「該当従業員へのキャリアカウンセリング」「人材紹介会社と連携した再就職先の紹介」といった再就職支援を提供しています。
早期退職者へ適切な支援を提供していることをアピールできれば、従業員も勇気を持ってセカンドキャリアの構築に踏み切れるはずです。企業としても、「早期退職する従業員へのサポートが手厚い」と対外的にアピールできるため、ブランドイメージ向上につながります。
早期退職することで、しばらくの間は自由な時間を楽しめます。もし、退職金や貯金額が十分にあり、今後の収入について目処が立っていれば、早期リタイアも実現可能です。
企業としても、こうした「自由な時間を楽しみたい」といった早期退職者の希望を叶えられるよう、なるべく退職金の割増支給などで要望に応えることが理想です。
一方で、早期退職制度には以下のようなデメリットもあります。
まず「企業視点」における早期退職制度のデメリットは以下の通りです。
基本的に早期退職制度は、従業員が希望すれば退職できます。そのため、自社にとって重要な戦力となっていた人材が退職する可能性も0ではありません。もし企業の中核を担っていた従業員が退職してしまうと、企業の業績に直接影響をもたらします。
特にスキルや経験が豊富な優秀な人材であれば、ある程度年齢を重ねても、より好条件で再就職できる可能性は大いにあります。そのため、早期退職制度を設計する際は、以下のように「優秀な人材から魅力的に思われるための職場環境作り」も意識することが大切です。
退職した人材数が想定以上である場合、一時的に業務が回らなくなり、企業の生産性を低下させるリスクがあります。残った従業員に業務負担が偏ってしまうと、モチベーションの低下を招き、さらに生産性を下げるかもしれません。
特にスキルが高い従業員が退職した場合は、生産性が大きく低下します。こうした想定外の事態に備え、企業は「マニュアルを整備しスムーズに業務を引き継げるよう準備する」「複数の配置転換パターンを考えておく」などの対策を行うことが重要です。
早期退職制度によって退職者が出ることで、企業は人件費の支払いを削減できるため、長期的にはコストカットを実現できます。
しかし「退職者への割増退職金の支払い」「再就職支援に必要な経費(キャリアカウンセラーの人件費など)の支払い」といった要因で、一時的にコストが膨らむ可能性があるため、注意が必要です。
特に、上記のように想定以上の退職者が出た場合は、企業の資金繰りを一時的に悪化させる可能性もあります。
早期退職制度は本来、組織の若返り実現や従業員のセカンドキャリア支援など「ポジティブな目的」で運用するものです。しかし、従業員からすると「企業の業績が悪化したので人員整理をしたいだけでは?」と思う可能性も0ではありません。
こうしたネガティブなイメージが社内に広がり「自分が人員整理の対象になるのでは?」と不安を与えてしまうと、従業員の仕事のモチベーションに悪影響を与えます。
早期退職制度を設計する際は、必ず「従業員のキャリアにプラスの影響を与えるために制定した」という目的を明確に伝えることが大切です。
次に「従業員視点」における早期退職制度のデメリットは以下の通りです。
40〜50代で転職する場合、若手と異なり「過去の実績や具体的なスキル」を重視される傾向にあります。そのため、目に見える実績を残せなかった従業員が早期退職した場合、必ず転職できるとは限りません。
割増退職金があるとはいえ、無収入の期間が長引くことは従業員としても避けたいはずです。とくに「自分の年齢的に空白期間を伸ばしたくない」と考えている場合、不安は大きくなります。
今まで組織に貢献してきた従業員がこうした不安を抱えないよう、企業は早期退職者に対し全力で転職支援を行うことが大切です。
退職金の割増金額は企業が設定できるため、従業員の想定より少ないケースがあります。もし、退職金の割増額をアテにして退職後の計画を立てていた場合、プランが崩れるかもしれません。なるべく従業員の退職後のプランを豊かにするためには、可能な範囲で割増金額を増やすことが大切です。
また、早期退職制度を社内で周知する際、退職金額の割増についても明確に共有してください。
早期退職して空白期間がある場合、厚生年金の加入期間が短くなるため、将来受け取る年金額は減少します。とくに空白期間が長くなるほど、年金額の減少は大きくなるため要注意です。
受け取る年金額の減少を抑えるためにも、企業は従業員がスムーズに再就職できるよう、手厚い転職サポートを行ってください。
早期退職制度を導入する際は、以下のステップを参考にしてください。どのような流れで進めればよいのか具体的に解説します。
最初に「早期退職の対象者」「優遇措置」を決めます。それぞれで以下のような内容を検討してください。
早期退職の対象者については、実施目的である「組織の若返り」「セカンドキャリアの応援」などを踏まえて、適切に定めてください。人員不足に陥ったり優秀な人材が抜けたりするリスクを減らすためにも、制度の対象者を明確化してある程度の制限を設けることが大切です。
また、制度実施後の社内の年齢構成や人員配置も踏まえて設計してください。例えば「◯◯部門は平均年齢が高いので早期退職者の枠を増やして若返りを図る」といったイメージです。
優遇措置については、退職金の割増や手厚い再就職サポートといった魅力的な内容を整備することで、制度利用を促進できます。
制度の大枠を定めたら、従業員の意見を集めます。社内説明会や対象となりうる従業員との面談、アンケートなどを通じて、制度への要望や優遇措置への改善点などをヒアリングすることが大切です。
早期退職制度は従業員の将来に関わる制度であるため、企業が一方的に条件を決めることは避けるのがよいでしょう。
従業員の意見も参考にして制度の内容が確定したら、取締役会での決議を行います。早期退職制度の策定は、会社法第362条4項に基づく「重要な業務執行」に該当するため、取締役会の決議が必要です。
制度の内容が決定したら、以下のような方法で従業員へ周知してください。
周知する際は、以下のような点を従業員へ理解してもらうことが大切です。
特に、制度の目的が社内に周知されず「ネガティブな制度」であると浸透してしまうと、従業員のモチベーション低下を招いたり優秀な人材に見切りをつけられたりするリスクがあります。そのため、複数の方法で十分に制度の詳細を周知し、従業員からの疑問点には真摯に回答することが大切です。
最後に、制度の内容に合わせて就業規則を改訂し、運用を開始します。退職関連の項目は、就業規則の「絶対的必要記載事項」に該当するため、早期退職制度を制定したら必ず記載してください。
実際に運用する際は、以下の点を心がけることが大切です。
就業規則の具体的な改訂方法は「【2023年4月法改正】就業規則の見直しチェックリストと変更時の5ステップ」で詳しく解説しています。
最後に、早期退職制度のスムーズな運用のために必要なポイントをまとめました。
トラブルなく運用するためにも、必ず上記のポイントは押さえるのがよいでしょう。
「早期退職制度への応募条件」「早期退職者の優遇措置」は必ず明確化してください。応募条件に曖昧な部分があると、従業員は自分が利用できるのか判断できず、なかなか申請に踏み出せません。また、優遇措置についても、具体的な退職金額や受けられる再就職サポートの内容などがわからなければ、今後の生活の見通しを立てにくくなります。
上記のような曖昧な部分を「企業に確認する」というのは、意外と手間です。そのため、従業員の手間を少しでも省き自発的に制度利用を促せるよう、応募条件や優遇措置は必ず明確化してください。
早期退職制度を実施する際は「従業員が納得したうえで退職する」ということが大前提です。従業員と十分に話し合い疑問をすべて解消したうえで、円満に早期退職してもらう必要があります。決して企業が退職を強制してはいけません。
早期退職する従業員は、長年の勤務経験をもとにした豊富なスキルや経験を持っています。そのため、もし「独立時にノウハウを流用する」「再就職先で顧客情報を流用する」といった事態が起きると、自社にとっては大きなダメージです。
こうした自社の重要情報が漏洩しないよう、必ず「守秘義務・競業避止義務」に関する認識をすり合わせてください。
具体的には、以下のような内容を書面で取り交わすことが大切です。
基本的に早期退職制度は、希望した従業員であれば利用可能です。とはいえ、対象従業員の早期退職を無制限に認めてしまうと、優秀な人材が流出するリスクも高まります。
優秀な人材の早期退職を防ぐには、制度の利用条件に「企業の同意」を盛り込むことが有効です。企業の同意を条件化することで、優秀な人材が早期退職を申し出た際に、交渉の余地を残せます。
もちろん、一番優先されるべきは従業員の意思であるため、強引な引き止めはNGです。あくまで「企業から交渉する余地を残す」という意味で、企業の同意を盛り込んでください。
残った従業員の業務負担を減らせるよう、事前に業務の引き継ぎをサポートできる体制も整備してください。具体的なサポート体制として、例えば以下が挙げられます。
早期退職者が出たことによる「残った従業員への負担」を放置すると、モチベーション低下を招きます。残った従業員の負担が少しでも軽減されるよう、企業はスムーズな引き継ぎ体制を構築できるようサポートしてください。
早期退職制度は、以下のように企業と従業員、それぞれの視点でメリット・デメリットがあります。
| 企業視点 | 従業員視点 | |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
運用前に上記のメリット・デメリットを踏まえて慎重に検討し、運用後は従業員の意見も参照しながら、制度を改善し続けることが大切です。
従業員の意見を反映させた魅力的で利用しやすい制度を設計できれば、「組織の新陳代謝の促進」「人件費の大幅な削減」などを実現し、企業に大きなメリットをもたらします。
早期退職制度の導入を検討している企業は、ぜひ今回の記事を参考にして、自社に最適な制度を設計してください。
| Q.1 早期退職のメリット・デメリットは? | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
企業と従業員、それぞれの視点でメリット・デメリットがあります。
|
|||||||||
| Q.2 早期退職したら「自己都合or会社都合」のどちらで扱われる? | |||||||||
|
従業員本人の希望で退職するため、基本的に「自己都合」として扱われます。 |
|||||||||
| Q.3 早期退職の年齢は? | |||||||||
|
企業にもよりますが、40〜50代の間で設定することが一般的です。 |
|||||||||
| Q.4 早期退職すると退職金はどれくらい割増される? | |||||||||
|
企業にもよりますが、「3ヶ月〜1年半分」程度を上乗せすることが一般的です。 |
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員10人まで永久無料の勤怠管理システム「フリーウェイタイムレコーダー」を提供しています。フリーウェイタイムレコーダーはクラウド型の勤怠管理システムです。ご興味があれば、ぜひ使ってみてください。