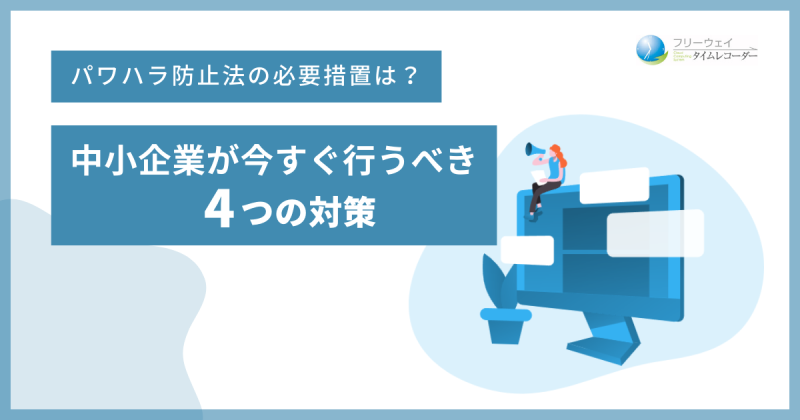
パワハラ防止法とは、企業に対して「パワハラ防止に向けた対策の実施」を義務付けた法律です。2022年4月からは、全企業が義務化の対象です。
パワハラ防止法では、これまで曖昧だった「職場内のハラスメント基準」を定め、明確な防止措置を企業に義務化することで、ハラスメント対策の強化を促進しています。
しかし、パワハラ防止法で必要な措置を実施しようとしても、以下のような悩みによって躓く企業も多いはずです。
この記事では、パワハラ防止法を遵守して企業と従業員を守れるように、パワハラ防止法の概要や定義、法律で規定された項目、具体的な対策内容などを解説します。
「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」とは、職場内のハラスメント基準を定めたうえで、企業に明確な防止措置を実施するよう義務化した法律です。パワーハラスメント(パワハラ)以外にも、セクシュアルハラスメント(セクハラ)や職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて、認定基準や防止措置を定めています。
現状では、パワハラ防止法自体に厳しい罰則は設けられていません。しかし、パワハラ基準や企業への対策義務化を法律で明文化したことで、職場における「いじめ・嫌がらせ」などを防止できると期待されています。
参照:厚生労働省|職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
パワハラ防止法は、2022年4月から「中小を含めた全企業」を義務化の対象と定めています。
とくに規模が小さい中小企業では、つい目の前の仕事で手一杯になり、法律への対応が遅れることがあるかもしれません。しかし、パワハラを防止し従業員を守ることは、健全な企業運営を実現するうえで欠かせない要素です。
決して「罰則がないから対応しなくてよい」と考えるのではなく、従業員が安全な職場で快適に働けるよう、必ずパワハラ対策を実施してください。
パワハラ防止法が制定された背景には、「現在でもパワハラを受ける人が発生している」という側面が挙げられます。
2024年3月に発表された「令和5年度厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(概要版)」によれば、「過去3年間でパワハラに関する相談を受けた」と回答した企業は64.2%でした。
また、厚生労働省の「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によれば、ハラスメント全体の相談件数は4年連続で120万件を超えており、高止まりを続けています。
相談に至っていないハラスメントも含めれば、もっと件数は増えるはずです。
このように、ハラスメントに関する話題が取り上げられるようになった昨今でも、パワハラの数はなかなか減っていません。パワハラ防止法は、こうしたハラスメントが放置されている現状を改善するために制定されました。
厚生労働省では、以下3つの要件すべてに該当する行為を「パワハラ」と定義しています。
参照:厚生労働省| 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!p.3
以下のように、「不快な言動に対し抵抗(拒絶)できない」という状況を利用して行われるパワハラのことを指します。
例えば「人事権を握っているベテラン上司に悪口を言われる」「営業成績トップの同僚から暴言を受ける」などの状況が当てはまります。
また、上司や先輩だけでなく「同僚や部下から」酷い言動を受けた場合もパワハラに該当します。そのため企業は、従業員のポジションに捉われず、職場で不快な言動が行われていないかチェックしてください。
一般的に見て、明らかに「業務上で必要な範疇や限度を超えて行われている行為」を指します。
例えば「顧客とのミーティングに無断で遅れた部下を叱責する」という行為は、一般的に見て適切です。だからといって、「”遅刻をするから無能で価値がない”といった人格否定にまで及ぶ」「暴力を振るう」といった行為は、明らかに業務で必要な範疇を超えています。
上記のような言動がパワハラであるかを判断する際は、以下のようにさまざまな要素を考慮してください。
ただし、従業員に問題行動があっても、「人格を否定する」「国籍の話を持ち出す」などの行為は業務で必要な範疇を超えているため、パワハラに該当する可能性は大いにあります。
当該の言動によって従業員が身体的あるいは精神的苦痛を感じ、結果として「著しく就労意欲が低下した」「業務に専念できない状況になった」といった場合、パワハラに該当します。具体的には「毎日過度に叱責を受け続けた結果、上司の顔色を過剰に気にして業務に臨める状態ではなくなる」などです。
とはいえ「どこまで相手の言動に耐えられるか?」という部分は、人によって異なります。そのため、判断する際は「社会一般の従業員が同じ言動を受けた際に仕事でどの程度の支障が発生すると考えられるか?」という部分を基準としてください。
基本的に「言動の頻度」「継続期間」を考慮します。しかし「明らかに強い身体的・精神的苦痛を与えている」と認定されれば、1回でもパワハラに該当するケースもあります。
より詳しく「パワハラに該当すると考えられる例」および「該当しないと考えられる例」をまとめました。
| 代表的なパターン | 該当すると考えられる例 | 該当しないと考えられる例 |
|---|---|---|
| 身体的な攻撃 |
|
|
| 精神的な攻撃 |
|
|
| 人間関係からの切り離し |
|
|
| 過大な要求 |
|
|
| 過小な要求 |
|
|
| 個の侵害 |
|
|
身体的な攻撃や暴言はもちろん、「実力を過大(過小)評価して適切ではない仕事を与える」「意図的に職場の人間関係から切り離す」「過度にプライベートを侵害する」といった行為も、パワハラに該当する可能性があります。
もちろん、上記の6パターンは絶対的な指針ではありません。「6パターンに該当しないがパワハラ認定される」というケースもあります。
そのため企業は、パターンに固執しすぎることなく、職場環境に注意深く気を配り、不快な思いをしている従業員がいないか注視してください。
参照:厚生労働省| 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!p.4
パワハラの定義を確認したら、具体的に「パワハラ防止法で企業に義務付けられた10項目」もチェックしてください。以下にチェックリスト形式でまとめたので、パワハラ対策を検討する際の参考としてください。
| □ | 「職場におけるパワハラの内容」「パワハラを行ってはならない」という方針を明確化し、従業員に周知・啓発する |
| □ | 「ハラスメントを行った従業員に対して厳しく対処する旨」「対処内容」を就業規則などの文書で規定し、従業員に周知・啓発する |
| □ | 相談窓口を定めて従業員に周知する |
| □ | 相談内容や状況に応じ相談窓口担当者が適切に対応できる体制を整えている |
| □ | ハラスメントが起きた際に事実関係を迅速かつ正確に確認できる体制を整えている |
| □ | ハラスメント被害者に対する配慮措置を速やか、かつ適切にできる体制を整えている |
| □ | ハラスメントの事実確認後、加害者に対し適切な措置を行う体制が整っている |
| □ | 再発防止に向けた措置を行う体制が整っている |
| □ | 相談者や加害者などのプライバシー保護に必要な措置を行い、周知する |
| □ | 「相談したことなどを理由に不利益な取扱いを行ってはならない」という旨を定め、従業員に周知・啓発する |
チェックマークがつかない企業は、法律で必要なパワハラ対策が不十分かもしれません。
確かに現状では、パワハラ防止法に違反しても直接的な罰則は受けないため、後回しにしている企業があるかもしれません。しかし、パワハラを放置し被害者の心に深い傷を残せば、そのまま働き続けることは難しくなります。さらに職場環境の悪化も招くため、とても健全な状態とはいえません。
こうした事態を防ぐためにも、次の項目で紹介する「具体的に行うべき対策」を確認し、自社で実施体制を整えることが大切です。
参照:厚生労働省| 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!p.20
パワハラ防止法で定められた10項目の措置を満たすために、具体的に以下のような対策を行なってください。
パワハラに関する方針を明確化したうえで就業規則に規定し、周知することが必要です。例えば、以下のような内容を記載してください。
就業規則に記載したうえで、社内報や自社ホームページ、パンフレット、ポスター、勉強会、研修、講習などを通じて、確実に従業員へ周知します。
厚生労働省の「あかるい職場応援団」に、周知に使えるポスターサンプルなどがあるため、活用してください。「他の企業はどうしてる?」では、実際にパワハラ対策を行った企業へのインタビューが掲載されているため、チェックしてください。
就業規定を変える際のステップは、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:【2023年4月法改正】就業規則の見直しチェックリストと変更時の5ステップ
以下のような施策を行い、従業員からのハラスメント相談に対応できる体制を整え、社内に周知してください。
もちろん「窓口を設ける」といった施策を行っても、形骸化しては意味がありません。「電話やメールでも相談できるようにする」「必要に応じて上司や人事担当者と連携する」なども行い、確実に運営できる体制を整えてください。
また、担当者がハラスメント相談に適切な対処を提供できるよう、「担当者向けのマニュアルを作成する」「対応方法に関する研修を行う」といったアクションを起こすことも大切です。
以下で、相談体制を整えるフローの一例を記載しているので、参考にしてください。

相談マニュアルやチェックシートは、とくに注力して作成することをおすすめします。パワハラを受けた従業員が安心して相談できるだけでなく、「相談がパワハラにあたるかどうか?」を客観的に判断するためにも重要です。
確実に窓口を運営できるよう、各ステップを抜かりなく遂行してください。
窓口に相談が寄せられた際、被害者・加害者に対し、スムーズに以下のような対応を行うことが重要です。

パワハラ被害者への配慮としては、例えば以下が挙げられます。
「パワハラが事実である」と断定できた場合は、加害者へ「警告・減給・降格・解雇」といった処分を行ってください。
万が一、職場でパワハラが発生した場合、以下のような再発防止策を行なってください。
もし「事実関係が正確に把握できなかった」「パワハラの事実が確認できなかった」という場合も、そもそも「相談が発生したこと自体」をリスクと見なし、上記のような対策を実施してください。
当然ですが、パワハラを相談した当事者が、以下のような不利益を被ってはいけません。
上記のような行為が行われると、相談者にさらなる追い打ちをかけることになります。職場内でも「パワハラを相談できない」という空気が蔓延し、労働環境の悪化を招きかねません。
パワハラで苦しむ従業員が勇気を持って声を上げられるよう、対象者が不利益を被る行為は、絶対に行わないでください。
2024年時点で、パワハラ防止法に違反した企業への明確な罰則は設けられていません。しかし、以下のような制裁が行われるケースもあります。
| 想定される罰則 | 内容 |
|---|---|
| 刑事罰 | 重大なパワーハラスメントが行われた場合、懲役や罰金が科される可能性がある |
| 民事罰 | 「企業がパワハラの実態を知っていたが放置していた」といった場合、安全配慮義務違反に問われ、民法上の不法行為責任を問われる可能性がある |
| 行政処分 | 勧告や改善命令、罰金などの行政処分を下される可能性がある |
| 企業名の公開 | 対策の措置を行っても改善されない場合、企業名が公表される |
このように、パワハラ防止法自体に罰則はありませんが、結果的に何らかの形で制裁を受けることになります。
そもそも、パワハラが発生すると「従業員の心身への悪影響」「人間関係の悪化による人材の流出」などを引き起こす可能性があります。そのため、罰則の有無に関わらず発生させないことが理想です。
もし「パワハラを放置した」という事態になると、従業員のモチベーション低下を招き、最終的に企業の業績に悪影響を与えるかもしれません。実際に「令和5年度厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」でも、「パワハラを相談したが何もしてくれなかった」と回答した人の割合は53.2%に達しています。
従業員にとって働きやすい職場環境を作るためにも、罰則の有無に関わらず、企業は必ずパワハラ防止対策を行ってください。
他社のパワハラを巡る裁判例については、厚生労働省の「あかるい職場応援団|裁判例を見てみよう」で公開されています。
パワハラへの対策を行い、健全な職場環境を構築するために、企業は以下のポイントを意識してください。
もし、現在の職場が以下のような状態になっている場合、早急に改善しなければなりません。
上記のような状況が続くとストレスが溜まり、鬱憤を発散するためにパワハラが起きる可能性もあります。そうした状態でパワハラ対策を行っても、また別の事案が起きてしまい、根本的な解決につながりません。
パワハラを継続的に防止し働きやすい風土を作るには、以下のように「根本の職場環境を改善する施策」を行い、ストレスなく働ける環境を整えることが必須です。
パワハラ被害を広げないために、事実確認は相談があってからスムーズに実行することが大切です。とはいえ、スピードを重視するあまり事実確認を誤り、「一般的な範囲内で指導した上司を加害者認定してしまう」といった事態を起こすことは避けてください。
万が一、パワハラの事実認定でミスがあると、無実にも関わらず加害者とみなされた従業員からの信頼を大きく失います。
スムーズかつ正確に事実確認できるよう、事前に対応の担当者を定めたうえで、両者の意見や関係者の話を入念にヒアリングすることを心がけてください。
「パワハラが事実である」と認定されたら、加害者には程度に応じた適切な処分を下してください。具体的な処分の例としては、以下が挙げられます。下に行くほど、処分が重くなります。
参照:厚生労働省|どのような言動がどのような処分に相当するかを記載した懲戒規定の例
パワハラに対する毅然とした態度を示すことで、被害者だけでなく周囲の従業員も職場を信頼できるようになります。
パワハラ防止法では、以下のように従業員に対しても「パワハラ防止に向けた責務がある」と認定しています。
企業はパワハラ防止対策を行うにあたり、上記の内容を従業員に共有してください。「就業規則に記載する」「勉強会や面談で共有する」「社内報やパンフレットなどに掲載する」といった方法がおすすめです。
従業員の協力を得られれば、「企業は気付かなかったパワハラの前兆を報告してもらう」などが可能になり、より健全な職場環境作りを促進できます。
参照:都道府県労働局|2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!p.3
パワハラだけでなく、以下のハラスメントも防止できるよう努力してください。
上記のようなハラスメントを防ぐ際も、先ほど解説した「ハラスメントへの企業の方針を周知する」「相談窓口を設置し迅速な対応体制を整える」といった施策が有効です。
参照:厚生労働省|職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!p.7〜
パワハラ防止に向けた施策を行い、健全な職場環境を構築することで、従業員が働きやすくなることはもちろん、企業にも大きなメリットをもたらします。
企業がパワハラ対策へ毅然とした対応を行なえば、従業員は「ここでなら安全に働ける」と信頼できます。
信頼度が増し、従業員が積極的に業務へ取り組める環境が整えば、企業の業績アップにつながる可能性もあります。
また、企業が「パワハラの定義」「従業員への正しい接し方」などを管理職クラスへ共有すれば、部下と良好な関係を築きながら適切なマネジメントを行えるようになります。
厚生労働省の調査でも、以下のように「ハラスメント防止策を行った結果として副次的な効果が得られた」と回答した企業が多くありました。

画像引用:厚生労働省|令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書p.91
このように、パワハラ対策を行うことは企業に多くのメリットをもたらすため、積極的に推進してください。
パワハラ防止法とは、職場内のパワハラを未然に防止できるよう、適切な対策の実施を企業に義務付けた法律です。中小を含めた全企業が義務化の対象になっています。
厚生労働省では、以下3つの要件すべてに該当するものをパワハラと定義しています。
パワハラを防止することは、従業員の心身を守るだけでなく、企業にも「生産性が向上する」「管理職が正しくマネジメントできるようになる」など、多くのメリットをもたらします。
現状では法律に違反しても罰則はありません。しかし罰則の有無に関わらず、快適な職場環境を構築して「従業員・企業」の双方がメリットを実感できるよう、積極的にパワハラ対策に乗り出すことが重要です。
| Q.1 パワハラを防止するために企業はどんな対策を行うべき? |
|---|
|
以下の対策を行ってください。
|
| Q.2 パワハラ防止法で定めている内容は? |
|
以下の10項目を満たす対策を行うことを定めています。
|
| Q.3 パワハラに該当する事例および該当しない事例は? |
|
一例ですが、それぞれ以下のような事例が該当します。
【該当しないと考えられる例】
|
| Q.4 パワハラ防止法に違反した場合の罰則は? |
|
パワハラ防止法自体に、違反時の罰則は設けられていません。ただし、企業の対応によっては民事罰や行政処分などの制裁が行われる可能性があるため注意してください。 |
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員10人まで永久無料の勤怠管理システム「フリーウェイタイムレコーダー」を提供しています。フリーウェイタイムレコーダーはクラウド型の勤怠管理システムです。ご興味があれば、ぜひ使ってみてください。