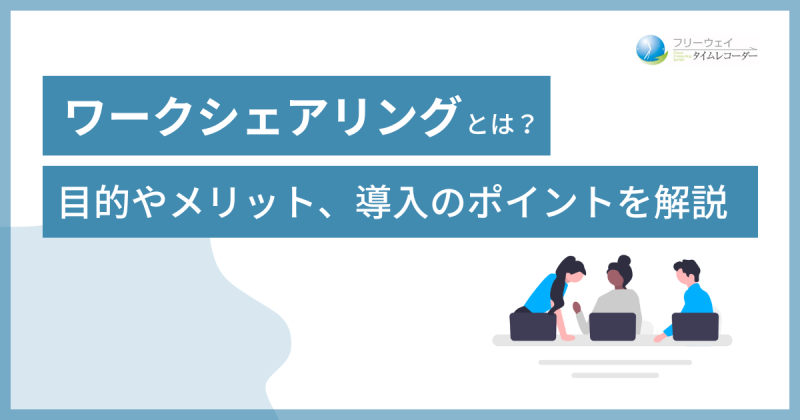
人事担当者として、「人員削減を避けたい」「多様な働き方に対応したい」「業務の属人化を解消したい」と悩んでいませんか?これらの課題を効果的に解決する方法として、ワークシェアリングが注目されています。
本記事では、ワークシェアリングのメリットや、実際に導入するための具体的ステップを解説します。「検討はしているけれど、どう始めれば良いかわからない」という方も、この記事を参考に、自社に最適なワークシェアリングの形を見つけてください。
ワークシェアリングとは、従来一人で担当していた業務を複数人で分担し、一人あたりの労働時間を短縮することで、雇用の維持・創出と働き方の多様化を実現する仕組みです。
厚生労働省の資料「ワークシェアリングに関する調査研究報告書」によると、「ワークシェアリングとは、雇用機会・労働時間・賃金という3つの要素の組み合わせを変化させることで、一定の雇用量をより多くの労働者の間で分かち合うことを意味します。」と定義されています。
単なる「仕事の分担」ではなく、働き方改革や雇用政策としての側面を持つ点が特徴です。
ワークシェアリングを導入することでハードワークの緩和や多様化する働き方への対応など、労働環境の課題解決に役立ちます。ここでは、企業視点と従業員視点に分けてワークシェアリングのメリットを紹介します。
業務の属人化防止
一人の従業員が専属で仕事を担当するとスキルアップできるものの、情報共有やマニュアル作成をすることもなく、ずっと一人で抱え込むことになります。病欠や退職などで担当者がいなくなったときに業務がスムーズに引き継がれないと、生産性が大きく低下してしまいます。
あらかじめ仕事を分担して取り組めば従業員同士で情報共有や補い合いができ、流れが止まることなく仕事が進みます。
社内環境の改善
従業員の残業削減や休日増加によって労働環境が改善すると従業員の負担が減り、心身の健康が保たれやすくなります。従業員のワークライフバランスが整うと心身ともに余裕が生まれ、職場の雰囲気も改善します。
従業員のモチベーションがアップすると生産性の向上や人材の定着が期待できます。
コスト削減効果
長期的な目線で見ると、離職率の低下による採用・教育コストの削減、残業代の削減、健康経営による休職者減少などのコストメリットが期待できます。
また、助成金制度の活用ができることも効果の一つです。ワークシェアリングは雇用創出や維持、生産性向上を実現できることから、厚生労働省でも推進されています。ワークシェアリングを導入することで、企業は以下の助成金を申請できるメリットもあります。
ワークシェアリング導入で活用できる助成金制度については後ほど説明します。
心身の健康維持
業務を自分一人で抱え込むと「期日までに終わらせなければならない」というプレッシャーがあるほか、進捗状況が芳しくないがゆえの残業が発生しタスク以上の負担がかかります。
ワークシェアリングを導入することで複数の働き手と仕事を分担できるため、業務に対して柔軟に取り組めるメリットがあります。
モチベーションの向上
仕事を複数人で分け合うことで心身ともにストレスが軽減して働きやすくなり、仕事に対するネガティブな感情が減る可能性があります。
また、労働時間が減少するとワークライフバランスが向上し、生活の質が向上します。家族と過ごす時間や趣味を満喫する時間が増えることでモチベーションが向上し、労働生産性アップにもつながります。
雇用の安定
ワークシェアリングの導入によって、雇用が維持される点も従業員の大きなメリットです。経営悪化によって業務量が減少した場合、従業員によっては「割り振られる仕事がない」といった状況になる可能性があります。
しかしワークシェアリングを導入すれば一人ひとりの仕事が確保されるため、予期せぬ失業の心配がありません。また、育児・介護などのライフイベントや体力面の変化があっても、働き方を調整することでキャリアを継続できます。
日本でワークシェアリングが注目されたのは、バブル崩壊後の雇用危機がきっかけです。2002年には政労使合意が成立し、「雇用維持・創出」「労使の合意」「多様な働き方の推進」など5つの原則が定められました。こうした背景を踏まえ、現代の日本企業でもワークシェアリングの重要性が高まっています。
20年以上前に始まったワークシェアリングですが、現代社会では、少子高齢化や働き方の多様化、業務の属人化防止、ベテラン人材の活用など、企業はさまざまな課題に直面しています。こうした背景から、持続可能な組織づくりに向けて、ワークシェアリングの必要性はますます高まっています。
現状、国内企業におけるワークシェアリングの現状は、導入率・普及率ともにまだ低い状況です。
詳しくは後述しますが、解雇を避けるための「雇用維持型」のワークシェアリングの場合、労働時間が短縮されるぶん賃金が減少する可能性があります。従業員の間で減給への不満や反発が生じるため、なかなか導入・取り組みが進まない状況です。
また、ワークシェアリング導入のひとつの障壁として、日本の多くの企業で残業を前提とした業務量を設定していることが挙げられます。残業前提での働き方をやめ、標準時間内で終わる業務量や業務プロセスの見直しを図ることが求められます。
欧州におけるワークシェアリングの導入は1980年代で、なかでもオランダの成功事例が広く知られています。オランダでは、1982年に成立した「ワッセナー合意」に基づき、企業はパートタイム労働の促進や賃金抑制で雇用を確保し、政府は従業員の所得減少を緩和するために減税と社会保障負担の削減を実施しました。これにより経済危機を克服し、オランダの失業率は1983年の11.9%から2001年に2.7%にまで低下し、世界中から注目を浴びました。
また、ドイツでも1980年代から業績悪化に対する措置としてワークシェアリングが導入され、フランスでは2000年前後に雇用創出を目的として、オブリ法による週35時間労働制が導入され、ワークシェアリングが実施されました。
参考:内閣府「平成13年度 年次経済財政報告」、 欧州におけるワークシェアリングの現状 -フランス、ドイツ、オランダを中心に-
ワークシェアリングには4つの形態があり、厚生労働省は以下のように分類しています。
| 種類 | 目的 |
|---|---|
| 雇用維持型(緊急避難型) | 一時的な景況の悪化を乗り越えるため、緊急避難措置として、従業員1人あたりの労働時間を短縮し、社内でより多くの雇用を維持する。 |
| 雇用維持型(中高年対策型) | 中高年層の雇用を確保するために、中高年層の従業員を対象に、当該従業員1人あたりの労働時間を短縮し、社内でより多くの雇用を維持する。 |
| 雇用創出型 | 失業者に新たな雇用機会を提供することを目指して、国または企業単位で労働時間を短縮し、より多くの労働者に雇用機会を与える。 |
| 多様就業対応型 | 正社員について、勤務の仕方を多様化し、女性や高齢者をはじめとして、より多くの労働者に雇用機会を与える。 |
緊急避難型ワークシェアリングは、経営危機を乗り切るための一時的な雇用維持策です。景気悪化や業績不振などの緊急事態に、従業員の解雇を避けるために導入されます。全社員の労働時間を短縮し、その分給与も減額することで、人件費を削減しながら雇用を守る緊急措置といえます。
具体的な実施方法:
雇用維持型(中高年対策型)ワークシェアリングは、ベテラン社員の知識・経験を活かしながら、負担を軽減する働き方を提供するモデルです。特に50代以上の社員を対象に、フルタイム勤務から短時間勤務へと移行することで、体力的な負担を軽減しつつ、企業が貴重な人材を維持できるようにする制度です。定年後の再雇用やシニア層の活躍の場を広げる目的で導入されることが多く、企業にとって人材確保や労働力の安定化にも寄与します。
具体的な実施方法:
雇用創出型ワークシェアリングは、既存社員の労働時間を短縮し、新たな雇用を生み出すモデルです。企業は労働時間削減により浮いた人件費を新規雇用に活用します。これにより失業者に就業機会を提供し、社会全体の雇用増加を促進します。既存社員の負担軽減にもつながります。
具体的な実施方法:
多様就業対応型のワークシェアリングは、個々のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を提供するモデルです。育児・介護・自己啓発などの理由で従来の働き方が難しい人に対し、短時間勤務や在宅勤務、隔日勤務などの選択肢を提供して働きやすい環境を整えます。
厚生労働省によると、この多様就業対応型は日本の労働市場において、労働力の減少に対応する有効な方法の一つとされています。
具体的な実施方法:

まずは自社の現状を正確に把握することから始めましょう。データに基づいた現状分析なしにワークシェアリングを導入すると、効果が限定的になったり、かえって混乱を招いたりする恐れがあります。以下の項目を丁寧に確認していきましょう。
進めていくと「時間の無駄」「業務の重複」「属人化のリスク」などが見えてくるはずです。これらの課題は、ワークシェアリング導入の重要な動機付けとなります。また、データに基づいた現状把握があれば、後の経営層や従業員への説明時も説得力が増します。
自社の状況に最適なワークシェアリングモデルを選びましょう。把握した課題に基づいて、どのタイプのワークシェアリングが自社に適しているか、そしてどの範囲から導入するかを決定します。
最初から全社導入ではなく、特定部署でのパイロット導入から始めることで、リスクを抑えながら効果を検証できます。また、計画段階から人事部門だけでなく、現場のマネージャーも巻き込むことで、実施段階での協力が得られやすくなります。
ワークシェアリングを支える制度と仕組みを整備しましょう。ワークシェアリングの成功には、就業規則の改定や評価制度の見直しなど、制度面のサポートが欠かせません。
特に重要なのは評価制度の見直しです。短時間勤務者が不当に評価で不利にならないよう、「時間当たりの生産性」や「アウトプットの質」を重視する評価基準に変更することが重要です。また、業務の標準化・マニュアル化は複数人での業務分担の前提条件となります。
丁寧な説明と対話で、従業員の理解と協力を得ましょう。ワークシェアリングは働き方の大きな変化を伴うため、従業員の納得と協力なしには成功しません。特に給与減が発生する場合は、十分な説明と対話が必要です。
「なぜ導入するのか」「どのようなメリットがあるのか」を丁寧に説明し、従業員の不安を取り除くことが重要です。給与減に対する懸念には、福利厚生の充実や副業の許可などの対応策を明確に示しましょう。また、制度は一律に強制するのではなく、可能な限り従業員の希望に沿った形で進めることがポイントです。
定期的な検証と改善を通して、持続可能なワークシェアリング制度に育てましょう。計画通りに導入を始めたら、定期的に効果を測定し、問題点を改善していくことが重要です。
導入直後は業務効率が一時的に低下することが多いです。最低でも3か月は継続し、その間に発生する課題を丁寧に解決していくことが重要です。また、成功事例を社内で共有することで、全社展開への弾みとなります。初期の「うまくいかない」場面も貴重な学びとして記録し、改善に活かしましょう。
生産性の向上や働き方改革への対応を目的にワークシェアリングの導入を検討しているものの、「社内体制の変化により何らかの弊害が生じるのでは」と不安を抱いている方もいると思います。ここでは、ワークシェアリングを導入するにあたって生じうる課題と対策を解説します。
仕事を複数人で分担することで一人あたりの労働時間が減少すると給与も減り、従業員に不満が生じる可能性があります。この場合、プライベートの時間が確保できるメリットについて説明するほか、副業を許可するのも1つの方法です。
また、企業の采配次第ではあるものの、ワークシェアリングをすべての従業員に強制しなければ、不満を持つ人には従来通り勤務してもらうこともできます。国の助成金をうまく活用するとともに、業務の生産性向上を図りバランスを取ってみてください。
解決策:
業務の「見える化」と情報共有の仕組みづくりが成功の鍵です。
複数人で業務を分担すると、情報の共有不足や引継ぎの不備が発生しやすくなります。業務の質を維持するためには、以下の対策が効果的です。
解決策:
成果主義への転換と公平な評価制度で複雑化を克服できます。
勤務形態が多様化すると、管理や評価が複雑になりがちです。「時間」ではなく「成果」に基づく評価への転換が効果的です。
解決策:
ワークシェアリング導入時の負担を軽減するために、助成金制度を活用しましょう。ワークシェアリングを導入する際には、各種助成金を活用することで財政的な負担を軽減できます。ここでは、主な助成金制度とその申請のポイントを解説します。
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。この助成金は、事業主が従業員の雇用を守るための重要な支援策です。
助成金の支給額や支給期間は、事業主が実施する雇用調整の内容や規模によって異なります。詳しくは「厚生労働省|雇用調整助成金」をご覧ください。
2020年4月1日から、中小企業に対して時間外労働の上限規制が適用されています。この助成金は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業の事業を支援するものです。
詳しくは「厚生労働省|働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」をご覧ください。
この他にも、人材開発支援助成金という、人材育成や事業展開などさまざまな用途に対応した助成金があります。詳しくは「厚生労働省|人材開発支援助成金」をご確認ください。
ワークシェアリングは、単なる雇用維持策ではなく、企業の持続的成長と従業員の働きやすさを両立させる経営戦略です。導入を成功させるには、経営層の明確なビジョン、丁寧な準備と段階的導入、そして継続的な効果測定が不可欠です。
少子高齢化による労働力不足や多様な働き方へのニーズが高まる現代において、ワークシェアリングは「雇用を守る」だけでなく、「多様な人材の能力を最大限に引き出す」手段となります。
人事担当者は、ワークシェアリング制度導入を通じて「時間ではなく成果で評価する」新しい組織文化への変革を主導する重要な役割を担っています。まずは業務分析と従業員の希望調査から始め、ワークシェアリングの小さな一歩を踏み出してみてください。
| Q1.ワークシェアリングの種類は? |
|---|
|
ワークシェアリングには、雇用維持型(緊急避難型)、雇用維持型(中高年対策型)、雇用創出型、多様就業対応型の4種類があります。 詳しくは「4種類のワークシェアリング」の章をご覧ください。 |
| Q2.ワークシェアリングで活用できる助成金は? |
|
ワークシェアリングを実施する企業は、雇用調整助成金、働き方改革推進支援助成金、人材開発支援助成金などの助成金が活用できます。各助成金において支給要件が設定されています。 詳しくは「ワークシェアリング導入で活用できる助成金制度」の章をご覧ください。 |