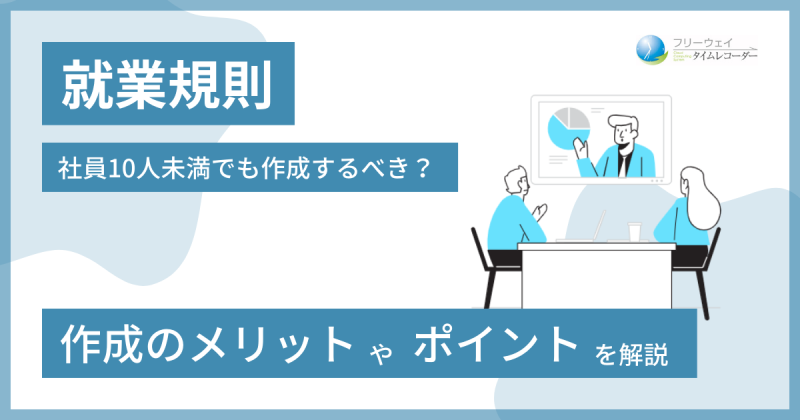
10人未満の事業所では、就業規則の作成は義務化されていません。しかし就業規則を作成しておくことで、社員の定着率改善や労使間のトラブル防止、ブランディングイメージの向上など、さまざまなメリットを実感できます。今回の記事では、10人未満の事業所で就業規則を作成するメリットや手順、運用時のポイントなどを解説します。
目次
就業規則とは、社員の雇用条件や職場のルールなどについてまとめた規則のことです。職場内におけるルールブックと捉えてください。
就業規則の必要性の有無は、雇用している社員の人数によって変わります。「社員数が10人未満の事業所」では、就業規則の作成・届出が義務付けられていません。法律でも以下のように規定されています。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
引用:e-Gov法令検索
しかし、あくまでも「法律で義務付けられていないだけ」であり、希望すれば社員数10人未満の事業所でも就業規則は作成できます。
むしろ、就業規則を制定すると以下のメリットを受けられるため、規定の社員数に達していない事業所もぜひ検討してください。
就業規則には、以下のように社員にとって重要な項目を記載します。
上記のような有給や働き方に関するルールが明文化されていると、社員は「まだ小さい会社だが自分の権利を確実に守ってくれる」と実感できます。こうした安心感を持って働ける環境であれば社員の満足度は高まり、最終的な職場への定着率改善につなげられます。
とくに10人未満の小規模な事業所の場合、ひとりでも社員が抜けてしまうと業務に大きな影響を与えかねません。そうした「人材不足に陥る状況を防げる」というのは、企業からすると大きなメリットです。
就業規則を作成しておくと、社員との認識ズレによる「労働条件に関するトラブル」を避けられます。
例えば、問題行動を起こした社員への懲戒解雇処分を検討している場合、処罰内容の範囲は法律で定められた「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」というルールに従う必要があります。
条文にある「客観的な理由」「社会通念上」といった概念の解釈は人によって異なるため、社員が「懲戒解雇の事由に該当しない」と主張した場合、スムーズな手続きが難しくなるかもしれません。
しかし、就業規則で解雇の条件を詳細に定めておけば、こうした認識ズレによるトラブルを防ぐことに繋がります。
他にも、以下のような項目を就業規則で明文化しておくと安心です。
さらに、ルールを明文化しておくことで、社内秩序の維持にも役立ちます。
就業規則では、上記のような労働条件や解雇だけでなく、日頃の服装規定や身だしなみ、遅刻・欠勤への対応などについても規定できます。ルールがなかったり曖昧だったりすると、企業の方針にそぐわない服装で出社したり、社用PCでプライベートなサイトを閲覧したりする社員が現れ、社内秩序が乱れるかもしれません。
職場内の規律を正して全員が気持ちよく働ける環境を整えるためにも、就業規則を作成し社員に理解してもらうことが大切です。
社員数が少ない段階から丁寧に就業規則を制定しておくことで、世間に対し「社員の働きやすさを考えている」「法律に沿って有給や労働条件などの働き方をしっかり決めている」という印象を与えられます。こうした印象を世間に広めることで、企業のブランドイメージがアップし、消費者が積極的に自社商品やサービスを活用するきっかけになるかもしれません。
また、採用活動においては、応募者から「ぜひここで働きたい」と思われる可能性が高まります。応募者の母数が増えれば優秀な人材と出会える確率も上がるため、より効率的な採用活動を実現可能です。
10人以上の社員を雇用してから慌てて就業規則を作成すると、手続きが間に合わなかったり申請を失念したりして、意図せず法律違反になるかもしれません。
さらに、企業の規模が大きくなると「幼い子どもがいるのでフレックス出勤をしたい」「リモートワークに切り替えたい」など、さまざまな事情や要望を持つ社員も増えます。要望が増えてから対応していると、就業規則の制定前にトラブルが発生するかもしれません。
10人未満の状態で就業規則を定めておくと、雇用人数が増えても慌てずに済みます。
あとから就業規則の制定にリソースを割く必要がないため、引き続き安定して自社のコア業務に注力できる点も魅力です。
雇用関係の助成金には、申請要件として「指定の就業規則を盛り込むこと」を定めているケースがあります。現在は必要ない場合でも、いざというときに活用できるよう、就業規則を設けておくことがオススメです。
例えば働き方改革推進支援助成金の場合、支給対象となるには「有給に関する就業規則が必要である」と明記されています。
全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
就業規則の制定が定められている助成金としては、他にも「キャリアアップ助成金」「人材開発支援助成金」が挙げられます。
ただし「就業規則を設定していれば必ず助成金の支給対象になる」というわけではありません。各助成金が定める細かい用件に沿った就業規則でなければ、申請対象とならない可能性があります。
実際に、以下のような失敗事例も挙げられています。そのため、漠然と就業規則を設けるのではなく、助成金に合わせた内容であるかを精査することが大切です。
このように社員10人未満の事業所でも、就業規則を制定しておくことで「従業員の定着率を改善できる」「社員とのトラブルを防げる」など多くのメリットを実感できます。
実際に制定する際は、就業規則の定義を確認してください。押さえるべき定義は、主に以下の2つです。
「事業所」とは、企業全体ではなく、本社・支店・営業所などを場所ごとに指す言葉です。例えば「本店A・支店B・支店C・支店D」に分かれた企業の場合、本店A・支店B・支店C・支店Dのそれぞれが「事業所」とみなされます。
「常時10人以上」とは、上記で定めた事業所ごとに雇用している社員が10人以上いることを指します。雇用形態(契約社員・パート・アルバイト)は問わず、企業と従業員間で直接雇用契約を結んでいれば、人数にカウントされます。
例えば「正社員6名・アルバイト2名・パート2名」という場合は、合計で10名になるので就業規則が必須です。あくまでも雇用している人数であり、「職場に10人以上が常時出勤している状態」ではないため注意してください。
「時短勤務をしている」というケースでも、常時10人以上を雇用しているなら就業規則の作成が必要です。例えば「正社員7名・1日5時間勤務のアルバイト2名・週2日勤務のパート1名」という場合も、やはり合計で10名になるので就業規則が必須です。
また、企業が本社と支社で分かれている場合は、各事業所単位で「常時10人以上の社員と契約しているか」という点で判断します。組織全体の雇用人数が10人以上であっても、各事業所単位の雇用人数が10人未満の場合、就業規則の作成義務はありません。
例えば「支店Aの雇用人数は5人・支店Bの雇用人数は7人・支店Cの雇用人数は11人」という場合、支店Cにのみ就業規則の作成義務が課されます。
一方で、以下のようなケースは「常時10人以上」とカウントされないため、就業規則の作成義務はありません。
繰り返しになりますが、社員10人未満の事業所に就業規則の制定は義務付けられていません。
しかし、あくまでも義務付けられていないだけであり、就業規則を制定することはできます。また、10人未満の事業所で就業規則を制定しても、もちろん問題なく効力を発揮します。
むしろ就業規則を制定することで、従業員満足度の向上やブランドイメージのアップなどにより健全な企業運営を実現できるため、人数にこだわらず作成しておいてください。
就業規則は以下の手順で作成してください。
まずは現状の労働条件を元に就業規則の原案を作成します。原案を作成する際は、以下の「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」を必ず確認してください。
絶対的必要記載事項(必ず記載すべき事項)
|
相対的必要記載事項(事業所で定めがある場合に記載すべき事項)
|
万が一「絶対的必要記載事項が抜けてしまった」「ボーナスの支払いがあるのに記載していなかった」などが起きると、社員とのトラブルになりかねません。
法律に則り正しい原案を作成するためにも、総務関連のコンサルティング企業や弁護士、法務担当者など専門知識を持つ人物も交えて決めてください。
就業規則の原案を作成したら、社員代表者と話し合い意見を求め、内容を適宜調節してください。
就業規則を作成する際は、必ず社員代表者の意見を聞く必要があります。代表者の意見を聞かなければ、企業に都合のよい労働条件となるリスクがあるためです。
労働基準法第90条でも「就業規則の作成や変更時は必ず社員代表者の意見を聞く必要がある」と定められています。社員代表者とは、以下の条件に該当する人物です。
場合によっては代表者の意見を参考にして、原案を修正することもあります。話し合いの内容を参考にして、改めて就業規則を策定してください。
就業規則の作成では、社員代表者の署名あるいは記名押印した意見書の提出が必須です。就業規則を社員代表者が確認し、問題なければ意見書を作成してください。意見書は企業単位ではなく「本店・支店などの事業所単位」で作成します。
ただし、代表者は必ずしも同意する必要はありません。内容をチェックして修正してほしい部分があれば、就業規則に対する反対意見を書いてもよいです。こうした擦り合わせを行い、企業と社員の双方が納得できる就業規則を目指してください。
署名・捺印が完了したら、各事業所を管轄する労働基準監督署に届け出ます。各事業所を管轄する労働基準監督署は「全国労働基準監督署の所在案内」から確認できます。就業規則の内容が「本社と各事業場で同じ」という場合は、本社の管轄監督署にまとめて届け出ることも可能です。
いずれの書類も1部は労働基準監督署に渡すため、自社での保管用も兼ねて、必ず2部ずつ準備してください。
労働基準監督署に届け出る書類
就業規則(変更)届および意見書は、各都道府県の労働局公式サイトからダウンロードできます。提出期限はとくにありませんが、規則の策定(変更)から1ヶ月程度が目安です。
就業規則の新規作成ではなく「変更」の場合は、変更届を提出します。2023年4月から中小企業を対象に労働関係法令が改正された影響もあり、就業規則の見直しが必要な企業も増えているはずです。変更の際も新規作成と同じように、社員代表者へのヒアリングが必須です。
法改正に伴う就業規則の見直しを検討している企業は、「【2023年4月法改正】就業規則の見直しチェックリストと変更時の5ステップ」も参考にして見直すべき点をチェックしてみてください。
最後に従業員へ就業規則を周知してください。法律でも「企業は社員に就業規則の内容を周知しなければならない」と定められています。
周知する手段は、以下のように従業員全員が閲覧できる状態であれば、どのようなものでも構いません。
就業規則を作成する際のポイントは以下の通りです。
大前提として、就業規則は必ず労働基準法に沿った内容を制定してください。労働基準法はすべての労働のベースとなるため、以下のように法律に違反する就業規則は認められません。
就業規則は確かに企業におけるルールブックですが、決してすべてを無制限に企業が決めてよいわけではありません。
就業規則は、事業所内のすべての社員がチェックするため、誰が読んでも正しく理解できるよう平易な言葉でまとめてください。「専門用語ばかりで内容を理解できない」「内容が抽象的なため読み手の解釈次第で結論が変わってしまう」という場合、認識ズレによるトラブルを引き起こすかもしれません。
例えば、ボーナスについて「算定対象期間:1月1日~6月30日・支給日:7月20日」と定めた場合、「4月1日に入社した人は受け取れるか」「6月30日に退職してもボーナスを受け取れるか」などの細かい部分が曖昧です。
そのため「算定対象期間:1月1日~6月30日・対象:算定対象期間のすべてに在籍した従業員・支給日:7月20日(支給日に在籍している社員に限る)」などで明文化したほうが、より条件が明確化されトラブルを防止できます。
就業規則では、「正社員・契約社員・アルバイト・パートタイム」など、自社と雇用契約を結んでいるすべての社員の事情に対応できる内容を定めてください。派遣労働者は自社と契約関係にないため、適用範囲外です。
「正社員とは別でパートタイム労働者専用の規則を設けたい」など、通常と異なる労働条件を定める場合は、別途で就業規則を定めてください。例えば、パートタイムの人のみに適用される「パートタイム労働者規則」などです。
別途で就業規則を設ける場合は、メインの就業規則に以下の2点を記載してください。
業種によっては、以下のように特殊な状況が発生するケースもあります。
就業規則を作成する際は、上記のような現場の状況を確認したうえで、自社にあった就業規則を作成してください。現場の状況にマッチしないルールを作ると、社員が上手く運用できず不満を溜める原因になりかねません。
労働基準法第89条では、以下のように就業規則に必ず記載しなければならない項目が定められています。自社で定めるルールに従い、必ず要件を満たしているか確認してください。
絶対的必要記載事項(必ず記載すべき事項)
|
相対的必要記載事項(事業所で定めがある場合に記載すべき事項)
|
就業規則を作成する際は、厚生労働省が用意している「就業規則作成支援ツール」という支援ツールも活用してください。フォームの内容に沿って必要項目を入力していけば、届出の要件を満たした就業規則を作成できます。また、「社会保険労務士事務所へ相談する」「労働基準行政の相談窓口を活用する」などもオススメです。
就業規則は企業と社員の両方に大きな影響を与えるため、こうしたサポートをフル活用し、法律に沿って正しいルールを制定してください。
就業規則は、作成後も定期的な見直しが必須です。
就業規則は原則として、労働基準法内容をもとに作成します。労働基準法を参考にするため、法改正が実施されれば就業規則も変更しなければなりません。とくに労働基準法は、直近でも以下のような改定が実施されています。
目まぐるしく変わる法改正に対応できず、就業規則が古いままでは法令違反となる可能性があるため、常に動向をチェックして定期的に見直してください。
就業規則の作成が義務付けられているのは「労働者数が10人以上」の事業所です。
しかし10人未満の事業所であっても、就業規則の作成によって社員の定着率を高めたり労使間のトラブルを防止したりなど、さまざまなメリットを受けられます。人数が増えてから慌てないよう、早い段階で就業規則を策定しておくことが大切です。就業規則を定める際は、必須事項の漏れがないように注意してください。
| Q1.就業規則は10人未満の事業所でも作成が必要? |
|---|
| 10人未満であれば作成は義務ではありません。しかし、労使間のトラブル防止や社内環境を整備するために、早めに設定することがオススメです。具体的なメリットについては「社員10人未満の事業所に就業規則の制定義務は無いが作成メリットは多い!」の章をご覧ください。 |
| Q2.就業規則の作成時に注意すべきポイントは? |
| 「絶対に記載すべき事項を漏らさないようにする」「就業規則を作成したあとも定期的に見直す」などです。詳しくは「就業規則を正しく作成・運用するためのポイント」の章をご覧ください。 |
| Q3.10人未満の事業所が就業規則を制定して効力はある? |
| 効力はあります。人数によって就業規則の効力が変わるようなことはないため、安心してください。 |
| Q4.「従業員を常時10人雇用する」とはどういう意味? |
| 「事業所ごとで自社と雇用関係にある社員を10人以上雇用している」という意味です。例えば、自社が支店A・支店B・支店Cで分かれており、各事業所の直接雇用の人数が「支店Aは5人・支店Bは7人・支店Cは11人」という場合、支店Cにのみ就業規則の作成義務が課されます。 |