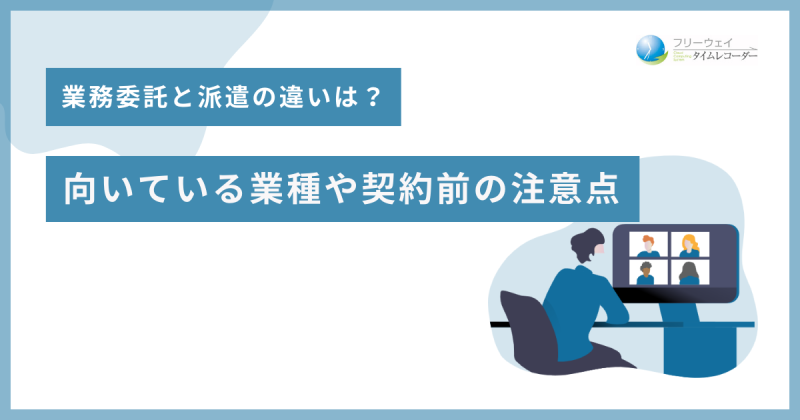
人材不足や働き方の多様化に伴い、正社員以外の雇用形態として「業務委託」と「派遣」を活用する企業が増えています。業務委託と派遣はどちらも、自社の業務を切り出して外部に依頼するアウトソーシングですが、法的位置付けや契約形態に大きな違いがあります。
活用目的、指揮命令権の有無、報酬体系、契約内容など、重要な差異を理解せずに導入すると、予期せぬトラブルや法令違反のリスクが生じます。
本記事では、業務委託と派遣の仕組みの違いや、それぞれのメリット・デメリット、適している業務タイプや契約時の注意点を詳しく解説します。これらの知識を身につけることで、自社の事業特性や目的に最適な外部人材活用の形態を選択できるようになります。
業務委託や派遣を検討していてどちらにするか悩んでいる、または、トラブルやリスクを最小限に抑えてアウトソーシングを活用したいと考える企業経営者や人事担当者の方はぜひご覧ください。
企業がおさえておくべき業務委託と派遣の違いを、図と表をもとに簡単に説明します。
業務委託と派遣の仕組み

業務委託と派遣の違い
| 業務委託 | 派遣 | |
|---|---|---|
| 指揮命令権 | なし | あり |
| 給与形態 | 月額固定報酬型 成果報酬・出来高払い型 単発・スポット報酬型 |
月給制 日給制 年俸制 派遣会社を経由して支払われる |
| 契約内容 | 業務の完了・成果物の納品 | 労働者の派遣 |
| 契約期間 | 業務ごとに異なる | 同じ職場では3年が上限 |
| 契約当事者 | 委託者と受託者(個人/法人) | 派遣元、派遣先、派遣労働者 |
| 適用法令 | 下請代金支払遅延等防止法、フリーランス新法など | 労働者派遣法、労働基準法など |
業務委託とは、自社から業務を切り出し、外部の企業や個人に委託する契約形態です。業務委託を受ける企業・個人は、発注者から委託された業務を完成させることで報酬を得ます。
このとき、業務委託を受ける企業・個人は独立した事業主として扱われ、発注者から作業内容や手順、勤務時間・場所についての指揮命令を受けることはありません。
また、基本的には労働基準法などの労働者に適用される保護を受けることはできません。報酬体系は、月額固定報酬型、成果報酬・出来高払い型、単発・スポット報酬型のいずれかになる場合が多いです。
ただし、業務委託を利用する際にも遵守すべき法律があります。
まず、大企業が中小企業に業務を委託する場合は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」です。支払い期日や発注書面の交付などのルールを守る必要があります。
下請法で定められている規制内容は以下の通りです。
次に、2024年11月1日に施行された「フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」です。これによりフリーランスへの業務委託において以下の内容が定められました。
参照:フリーランスの取引に関する 新しい法律が11月にスタート!
これらの法令を理解し、適切に対応することが企業には求められています。
一方、派遣とは、派遣元(派遣会社)の従業員を、派遣先企業に一定期間派遣する契約形態です。つまり、雇用関係は派遣元にあり、指揮命令は派遣先が行うという関係の分離が特徴と言えます。
派遣労働者は派遣先の指示や監督を受けながら、指定された場所や業務内容に沿って働きます。
派遣労働者への給与は派遣会社が支払い、労働条件の管理も派遣会社が行います。派遣先企業は、派遣労働者の保険料や税金を直接負担することはありませんが、派遣労働者に支払う報酬に加え、派遣会社への手数料を払うことになります。
ただし、労働者派遣法のもと、派遣会社と派遣先企業は、派遣労働者の待遇や安全衛生管理などの責任を共有し、法的に責任を分担することが定められています。
契約期間については詳細な規定があるため、さらに解説します。
業務委託と派遣では、定められる契約期間の法的枠組みに違いがあります。
業務委託の場合は、通常業務委託を結ぶ際に、以下の事項を当事者間で合意して定めます。
業務委託契約時に決める事項
一方、派遣の場合、同じ派遣労働者を派遣先事業所の同一の組織単位(課やグループなど)に派遣できる期間は、原則として最大3年と法律で定められています(2015年の労働者派遣法改正)。例外を除き、派遣先が同一の組織単位での派遣を3年を超えて継続しようとする場合は、過半数労働組合などからの意見を聞く必要があります。
派遣期間制限の対象外となる従業員
派遣期間が上限に達した後も同じ派遣労働者を継続して雇用したい場合は、正社員・契約社員・無期雇用派遣社員などの雇用形態に切り替える必要があります。
これは派遣労働者の雇用安定を図るための規定であり、派遣先企業の企業規模や業種に関わらず遵守が求められます。
なお、業務があるときだけ派遣会社と雇用契約を結ぶ「登録型派遣(一般派遣)」の場合でも、派遣契約終了後に派遣先が派遣労働者を直接雇用することは可能です。ただし、紹介予定派遣を除くケースでは、派遣会社に紹介手数料の支払いが発生する場合があるため契約内容の確認が必要です。
また、労働者派遣契約が派遣先の都合により途中で解除される場合、派遣先には派遣労働者の新たな就業機会の確保に向けた配慮や休業手当相当額の負担などの義務が労働者派遣法において定められています。

引用:厚生労働省・都道府県労働局『派遣会社の事業所の皆様へ』
企業が業務委託や派遣を利用する最大のメリットは、必要なスキルを持った人材に必要なときだけ働いてもらえることです。
たとえば、繁忙期の人材確保をしたい場合や新たなシステム設計を行いたいが自社にスキルがある人材がいない場合など、業務委託や派遣が選ばれます。業務委託や派遣で依頼すれば、自社で正社員として雇用する場合に比べて、採用や研修のコストも抑えられます。
その一方、長期的に見れば、帰属意識が生まれにくい・安定した人材確保ができないといったデメリットも存在します。
業務委託と派遣のメリット・デメリット
| 業務委託 | 派遣 | |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
業務委託の主なメリットは、人件費を変動費化できることや、採用・教育にかかるコストを削減できるといった点です。
正社員や派遣社員とは異なり、業務委託では必要な業務だけを外注できるため、人件費を固定費から変動費に転換することができるためです。特に繁忙期と閑散期の差が大きい業種や、プロジェクト単位の業務が多い企業にとって大きなメリットとなります。
また、専門知識やスキルを持った人材を即戦力として活用できるため、採用コストや長期間の教育研修費用を削減できます。自社では保有していない専門性を必要なときだけ調達できるため、社内リソースの最適配分が可能になり、本業への集中度も高まります。さらに、成果物の納品を前提とした契約となるため、業務の目的や納期を明確化しやすく、プロジェクト管理の効率化にもつながります。
業務委託のデメリットには、指揮命令関係の制限、品質管理の難しさ、情報セキュリティリスクなどがあります。
最も注意すべき点は、発注者から直接の指揮命令ができないことです。業務の進め方や勤務時間・場所を細かく指定すると「偽装請負」とみなされ、労働関係法令違反となるリスクがあります。そのため、緊急対応や柔軟な業務変更が必要な場合に制約が生じることがあります。
また、業務の進捗管理や品質コントロールが難しくなる点も課題です。特に初めて取引する相手との業務委託では、期待する品質基準や納期を明確に契約書に盛り込むことが重要になります。
加えて、社外の人材が企業の機密情報を扱うことによる情報漏洩リスクも考慮すべきです。機密保持契約(NDA)の締結だけでなく、アクセス権限の制限や情報管理ルールの徹底など、包括的な情報セキュリティ対策が不可欠です。
派遣のメリットには、迅速かつ柔軟な人材確保、雇用管理負担の軽減、専門スキルの一時的活用などが挙げられます。
繁忙期対応や期間限定のプロジェクト期間中、育休・産休の代替要員など、一時的に人手が必要な場合でも、即戦力となる人材を短期間で確保できます。マニュアルが整備されているような定型業務との相性がいいのも特徴です。
社会保険や給与計算などの雇用管理実務は派遣会社が担うため、受入企業の人事・労務管理の負担が軽減されます。派遣契約終了時の雇用調整も比較的柔軟に行えるため、人員配置の最適化が図りやすい点もメリットです。
さらに、派遣労働者への指揮命令が可能なため、業務内容や進め方を細かく指示できる点も、業務委託との大きな違いです。
派遣のデメリットには、コストの高さ、ノウハウの蓄積の難しさ、法的制約による対応の複雑さ、などが挙げられます。
派遣料金には派遣会社のマージンが含まれるため、短期間の活用では効率的でも、長期的に同じ業務を任せる場合は正社員雇用より高コストになる可能性があります。
また、2020年4月から大企業、2021年4月から中小企業に適用された同一労働同一賃金の原則により、派遣労働者の待遇改善コストが増加している点も考慮が必要です。人材活用の期間や目的を明確にした上で、コスト面の判断が必要不可欠です。
派遣期間の制限(原則最長3年)があるため、業務知識や経験が社内に蓄積されにくく、長期的な人材育成が難しい点も課題です。そのため、企業の中核業務や機密性の高い重要業務には不向きな面があります。
また、派遣労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、派遣元の36協定の締結に加え、派遣先と派遣元の間で時間外労働に関する合意が必要です。36協定の範囲を超えて時間外労働などを行わせた場合、派遣先が労働基準法違反となります。さらに、派遣先にも派遣労働者の安全配慮義務があるなど、労務管理面で正社員とは異なる対応が求められます。
業務委託と派遣は就業形態や法的位置付けに大きな違いがあるため、どちらが適しているかは依頼したい業務や業種の特性によって判断する必要があります。この章では、それぞれが向いている業務と具体例を紹介します。
業務委託が向いている業務と例
例
株式会社みらいワークスが2022年に行った「企業の業務委託利用」に関する実態調査 によれば、業務委託に求める業務で最も多いのはエンジニア(36.7%)、次に多いのがPM/システム企画開発(28.0%)でした。

引用:株式会社みらいワークス:「企業の業務委託利用」に関する実態調査
人材確保が困難な専門職や、一時的な需要に対応するためのリソース調達として、業務委託は重要な選択肢となっています。特に労働市場がタイトな状況下では、正社員として採用が難しい専門人材を業務委託で確保する企業が増加傾向にあります。
派遣が向いている業務と例
例
厚生労働省の「令和4年派遣労働者実態調査の概況」によれば、派遣労働者が最も多く従事しているのは「製造業」(23.6%)で、次いで「情報通信業」(23.1%)となっています。

業務委託に比べて専門性やスキルよりも、比較的標準化された業務や、指示に基づいて遂行する業務での活用が多い傾向にあります。
業務委託と比較すると、派遣は「指揮命令関係の有無」という点で大きく異なります。派遣では細かな業務指示が可能であるため、定型業務や即時対応が必要な業務との親和性が高いといえるでしょう。
業務委託や派遣の契約は、労働者派遣法や労働契約法、民法などの複数の法律によって規制されています。自社でこれらの契約形態を導入する際は、法令を遵守し、違反リスクを回避することが重要です。
特に注意すべきなのが、「偽装請負」と「二重派遣」です。これらは重大な法令違反となるため、契約を結ぶ前に該当しないか十分に確認する必要があります。

「偽装請負(ぎそううけおい)」とは、実質的には労働者派遣に該当するにも関わらず、形式上は請負や業務委託契約として処理する行為のことです。たとえば、業務委託契約を結んでいても、発注者が受託者に対して直接的な指揮命令を行っている場合は、偽装請負とみなされる可能性があります。
業務委託では労働基準法などの労働法令が適用されないため、偽装請負は労働者保護の観点から問題とされ、労働者派遣法および職業安定法によって明確に禁止されています。
偽装請負と判断された場合、発注者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。違法性の判断は契約書の形式ではなく実態に基づいて行われるため、以下のような指示命令は業務委託では禁止されています。
業務委託で禁止されている指示命令
業務委託契約では、委託される企業・個人が業務遂行の時間・場所・方法について決定権を持ち、指揮命令関係が存在しないことを契約書に明記することが重要です。
参考までに、偽装請負をめぐって企業が処分を受けたケースと、偽装請負とは認定されなかったケースを付記します。業務委託を依頼したい企業は一度確認しておくと良いでしょう。
偽装請負をめぐる裁判の例
| 偽装請負として企業が処分を受けたケース | ナブテスコ事件 被告会社の子会社と業務委託契約を結び、親会社の班長の指示を受け、同じ作業服を着て親会社の従業員と共に業務を行った。 |
| 裁判所の判断 子会社が親会社からは独立した法人であるとしたうえで、原告らの主張を認め、実質的には親会社から直接作業上の指揮命令を受けて労務に従事しており、親会社が実施的に原告らに賃金を支払っている。親会社と黙示的な労働契約を成立させているといえる。 |
|
| 偽装請負と認定されなかったケース | センエイ事件 下請け企業で働く従業員は、業務遂行過程で相手方企業から指揮命令を受けていた。また、出来高払いという形式ではあったが、実際は従業員が働いた時間に応じて請負代金が支払われていた。 |
| 裁判所の判断 指揮命令関係があったが、下請け企業には他企業との業務契約や労働者派遣の実績がなかったため、企業としての独立性が認められず、相手方企業との黙示的な労働契約関係が認められた。 |

二重派遣とは、派遣先企業が派遣社員をさらに別の企業(自社の取引先や子会社など)へ再び派遣し、労働させる行為を指します。これは職業安定法第44条に違反する違法行為です。
通常の派遣契約では、派遣社員は派遣元企業と雇用契約を結び、派遣元と派遣先の間で労働者派遣契約が成立しています。この関係において、派遣先が派遣社員に業務指示を出すことは合法です。
しかし、派遣先がさらに派遣労働者を第三の企業で就労させた場合、その企業とは雇用契約も派遣契約も存在しないため、法的に無効な労働関係が発生します。これが二重派遣に該当し、労働者保護の観点から厳しく禁止されています。
派遣労働者を活用する際は、自社の取引先企業や関連会社での就労を指示することがないよう、事前に業務範囲を明確にし、管理監督者や現場責任者に周知徹底することが重要です。
企業が外部人材を活用する際、勤怠管理の方法は契約形態によって大きく異なります。適切な報酬支払いと法令遵守のために、業務委託と派遣それぞれの勤怠管理の特性を理解しておく必要があります。
業務委託では、原則として勤怠管理は行いません。成果物の完成や業務の遂行が報酬の基準となるため「何時間働いたか」よりも「契約した業務が完了したかどうか」が重要です。就業時間や場所、業務遂行方法などは基本的に受託者の裁量に委ねられています。
発注者が労働時間を管理したり、出退勤を厳格に定めたりすると、実質的に雇用関係に近い状態となり、「偽装請負」と判断されるリスクが高まります。
ただし、以下のような場合には業務遂行やセキュリティの観点から一定の管理が必要になることもあります:
これらは勤怠管理ではなく、業務の進行管理や契約履行の確認を目的とした管理です。過度に細かい管理や日常的な指示は「偽装請負」と見なされるリスクがあるため適切なバランスを保つことが必要です。
派遣労働者には労働基準法が全面的に適用されるため、適切な勤怠管理が法的に要求されます。
主な勤怠管理項目は、次の3つです。
重要なのは、派遣先企業は日々の勤怠管理を行いますが、労働時間管理の最終的な法的責任は派遣元企業にあるという点です。そのため、派遣先は正確な勤怠情報を漏れなく派遣元と共有し、労働時間の適正管理に協力する義務があります。
業務委託と派遣はどちらも外部リソースを活用する手法ですが、法的位置付けや運用方法に大きな違いがあります。これらを正確に理解せずに活用すると、意図せず法令違反を犯すリスクがあります。
自社で外部人材を活用する際は、以下の点を考慮して最適な契約形態を選択しましょう:
適切な契約形態を選択し、法令を遵守しながら運用することで、外部人材の能力を最大限に活かしつつ、トラブルを未然に防ぐことができます。特に近年は働き方改革関連法や同一労働同一賃金の導入など、労働法制が大きく変化しているため、最新の法令動向にも注意を払いながら運用することが重要です。
| Q1.業務委託と派遣の違いは? |
|---|
| 業務委託と派遣はどちらも外部リソースを活用するアウトソーシングですが、法的位置付けと契約形態に違いがあります。具体的には、活用の目的、指揮命令権の有無、報酬体系、契約内容などです。これらの違いを知らずに業務委託・派遣を運用すると、偽装請負や二重派遣などの法令違反リスクが高まり、罰則の対象となる可能性があります。 それぞれの特徴や法的枠組みの詳細について詳しくは、業務委託と派遣の違いの章をご覧ください。 |
| Q2.業務委託と派遣それぞれに向いている業務は? |
| 業務委託は専門性の高い業務や明確な成果物が定義できる業務に適しています。IT開発、Webデザイン、コンサルティング、専門調査、マーケティング企画など、特定の専門スキルを必要とする分野で多く活用されています。 一方、派遣は指揮命令関係のもとで業務を遂行する形態であり、一般事務、データ入力、受付業務、コールセンター対応、小売店スタッフなど、比較的標準化された業務や、直接的な指示のもとで行う業務との親和性が高いです。 詳しくは、業務委託・派遣それぞれに向いている業務と例をご覧ください。 |
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員10人まで永久無料の勤怠管理システム「フリーウェイタイムレコーダー」を提供しています。フリーウェイタイムレコーダーはクラウド型の勤怠管理システムです。ご興味があれば、ぜひ使ってみてください。