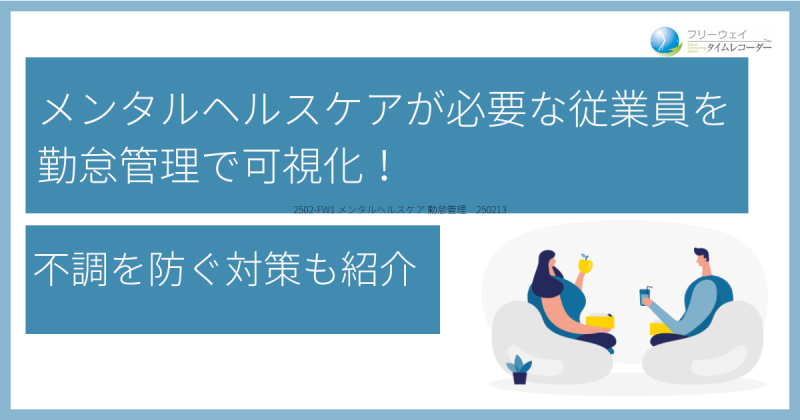
メンタルヘルスケアが必要な従業員は、勤怠管理の内容からも把握できます。たとえば、急に時間外労働や遅刻、欠勤が増えた場合は、要注意です。既にメンタルヘルス不調を発症している可能性があります。他にはどのような点を確認するべきでしょうか。
この記事では、メンタルヘルスケアが必要な従業員を勤怠管理で把握するポイント、体調不良者を防ぐ対策などに関して、紹介します。
人事労務担当者の方、メンタルヘルス不調が原因での求職者や離職者の増加にお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
従業員のメンタルヘルスケアの一環として、既に多くの企業でストレスチェックが義務化されています。労働安全衛生法にもとづき、従業員が常時50人以上働く事業場は毎年1回、ストレスチェックを実施しなければなりません。
ストレスチェックによってメンタルヘルス不調に悩む従業員を早期に発見し、休職や離職を防ぐことが目的です。ストレスチェックの結果は従業員に直接伝えられ、本人から同意が得られない限り、経営者に結果は公開されません。
メンタルヘルスに不調を抱えていると判断力や注意力、集中力が低下することがあり、最悪の場合は休職や離職にも繋がるため、従業員のメンタルヘルスを適切にケアすることは、円滑な企業運営にとても重要な要素です。
そこで、以下の見出しではストレスチェックの実施義務のない企業でも勤怠管理を通じて、メンタルヘルスケアが必要な社員を把握できる方法をお伝えします。
勤怠管理や従業員の行動に以下のような傾向がみられた場合、メンタルヘルス不調を発症している可能性があります。
上記のケースに該当する従業員を発見したら、すぐに対応することが重要です。
長時間労働が慢性化すると心身を休める時間が減り、体調不良を招くリスクが高まります。同じ部署で働く他の従業員と比較して明らかに残業時間が長い従業員がいる場合は、注意が必要です。特に、クレーム対応や顧客の繁忙期など明らかな理由がないにも関わらず通常よりも残業時間が長い場合、メンタルヘルス不調を発症している可能性があります。
残業時間が多い従業員を見つけた際は、以下の不調を感じていないか、確認しましょう。
上記に加えて「疲れが取れない」や「緊張状態が続いている」などの不調を感じている場合も、休暇の取得を勧めましょう。
また、従業員本人が不調を申告しなくても、別の従業員が異変を素早く察知し、対応することも重要です。
責任感が強く、担当業務に真摯に取り組んでいる従業員に勤怠の乱れが出た場合は、注意が必要です。既に適応障害やうつ病などのメンタルヘルス不調を発症し、遅刻・早退・欠勤を繰り返している可能性があります。
突然、勤怠に乱れが生じた従業員を発見した際は、業務量の調整や休暇の取得、メンタルケアを実施し、重症化を防ぎましょう。
休日出勤を命じた場合は割増賃金の支払いに加えて、代休や振り替え休日の取得を命じる必要があります。労働基準法35条にもとづき、従業員には最低1週間に1回の休日を与えなければなりません。
代休や振り替え休日の取得が遅れると、連日の業務によって疲労やストレスが溜まり、心身の不調を招く可能性が高まります。体調の悪化や、それによる休職・離職を防ぐためにも、休日出勤を命じる際は事前に代休や振り替え休日の取得日を決めておくことが重要です。
また、業務プロセスのデジタル化などによる効率の見直し化、業務の外注など、従業員に休日出勤を極力命じないような体制作りも必要になります。
勤怠管理システム上では残業時間が少ないにも関わらず、実際には頻繁に残業をしている従業員のケースです。「周囲に迷惑をかけたくない」「時間内に終わらず申し訳ない」といった気持ちから、サービス残業をしている可能性が考えられます。
責任や仕事を抱え込みすぎると、うつ病や適応障害などを発症する可能性が高くなります。重症化を防ぐためにも、管理職は自身の部下の勤怠データと実際の行動が一致しているか、確認が必要です。
勤怠データと行動の不一致は責任感が強く、真面目な従業員にみられるケースが比較的多いです。終業時刻が過ぎても残業している従業員を頻繁に見かけた際は、声をかけましょう。
これまでは出退勤時刻の打刻漏れやミスがなかった従業員に、勤怠でのミスが急増している場合、注意が必要です。メンタルヘルス不調の発症によって精神的に余裕がなくなり、集中力や注意力が低下している可能性が考えられます。
その背景には、業務量の多さや職場での人間関係など、さまざまな原因が考えられます。まずは従業員の直属の上司が面談の機会を持ち、体調や業務量に問題がないか、確認することが重要です。
従業員と上司の関係がうまくいっていない場合は、人事労務担当者が面談を担当しましょう。また、業務過多が原因でメンタルヘルス不調を招いている場合は、業務量の削減や担当変更など、業務負担を減らす取り組みが必要です。
厚生労働省では、企業が取り組む従業員へのメンタルヘルス対策の基礎としてメンタルヘルスケアをどのように進めていくか、取り組み内容や方針などをまとめた「心の健康づくり計画」を策定することを推奨しています。
さらにその後は、計画に基づき、以下4つのメンタルヘルスケアを実施します。
それぞれの内容を見ていきましょう。
心の健康づくり計画とは、従業員のメンタルヘルスケアを推進するため、自社の基本方針や取り組みをまとめたものです。
メンタルヘルスケアは単発ではなく、中長期的な視点での取り組みが求められます。仮に多くの従業員がメンタルヘルスの不調で休職や離職をした場合、事業運営や商品・サービスの提供にも支障を来してしまうため、企業にとって非常に重要です。
従業員がストレスや疲労で体調を崩さないよう、計画的なメンタルヘルスケアの推進や職場環境の整備が求められます。
心の健康づくり計画を策定する際は、事業場内に設置した衛生委員会において、十分に時間をかけて内容を固めていくことが重要です。また、以下の事項は計画に盛り込みましょう。
心の健康づくり計画は、厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」においても、策定が推奨されていますが、法的に計画の策定が義務付けられているわけではありません。
しかし、従業員のメンタルヘルスを守り、円滑な企業運営を行っていくためにも積極的に取り組むとよいでしょう。
セルフケアは従業員自身がストレスや疲労の度合いを把握し、メンタルヘルス不調を自身で予防する取り組みです。自身の体調に合わせて睡眠時間やプライベートな時間を確保し、心身のリフレッシュに努めます。
プライベートな時間では運動や趣味に没頭し、ストレスを発散します。企業側は従業員が正しい方法でセルフケアを実践できるよう、メンタルヘルスに関する研修や情報提供を積極的に実施することが重要です。
また、メンタルヘルスケアが必要な従業員を早期に発見するには、管理監督者や経営者も知識を習得しなければなりません。研修や情報提供の場を通じて、ストレスへの対処やメンタルヘルスケアの重要性などに関して、学びましょう。
ラインケアは同僚や先輩、上司など、横や縦のつながりを活かしたメンタルヘルスケアです。特に管理職は、部下の勤務態度や仕事への取り組み方を確認できる立場にあるため、ラインケアで重要な役割を担います。
また、管理職は業務量の調整や担当変更、シフト調整など、業務上の命令を部下に出せる立場でもあります。部下のメンタルヘルス不調を早期に発見できるよう、日頃から部下の行動を観察しておくことが重要です。
そして、以下のような傾向にある従業員を見つけたら、有給休暇の取得や人事担当との連携、産業医との面談などを実施し、重症化を防ぎます。
事業場内産業保健スタッフとは、産業医や保健師、衛生管理者などが該当します。人事労務担当者も含め、職場のメンタルヘルスケアに関する研修や企画の立案・運用を担当する方々のことです。
事業場内産業保健スタッフの役割は、有効なセルフケアやラインケアを実施できるよう、職場環境を整備することです。また、従業員がメンタルヘルス不調を原因に休職や離職しないよう、従業員への個別対応も実施します。
事業場内産業保健スタッフがおこなう具体的なケアに関して、以下の表にまとめました。
| 職場全体 | 従業員への個別対応 |
|---|---|
|
|
また、事業場内産業保健スタッフは、継続的なメンタルヘルスケアに不可欠な「心の健康づくり計画」の策定でも、中心的な役割を担います。
病院やクリニック、精神保健支援センターなど、外部の医療機関や専門家を活用して行うメンタルヘルスケアです。ケアの内容は、医師との面談やメンタルヘルスの診断、職場への復帰支援などがあげられます。
また、事業場で働く従業員数が50人未満の場合、産業保健総合支援センターを活用するのもおすすめです。産業保健総合支援センターでは、事業場内の産業保健スタッフに対し、メンタルヘルスケアに関する情報提供や研修などのサポートを受けられます。
従業員数が50人未満の事業場であれば無料でサービスを提供しており、研修だけでなく従業員と医師の個別面談なども含めた、幅広い支援が受けられます。
産業保健総合支援センターは、全国47都道府県に設置されている機関です。事業場内産業保健スタッフの人手不足に悩んでいる場合、一度相談してみましょう。
職場のメンタルヘルス対策は、以下の3段階に分類できます。
メンタルヘルス不調が原因での離職を防ぐには、すべての予防策が重要です。
一次予防は従業員がメンタルヘルス不調に陥らないよう、未然に防ぐ取り組みです。セルフケアやラインケアの実施が該当します。従業員が積極的にセルフケアやラインケアを実践できるよう、情報提供や研修機会の場を設けることが重要です。
また、ストレスチェックの実施は一次予防に大きな役割を担いますが、企業側には分析結果を次の対策に反映していく姿勢も求められます。単にストレスチェックを実施するだけではなく、分析結果をもとに職場環境の分析や問題点の抽出に努め、改善策を実施していきましょう。
二次予防はメンタルヘルス不調を発症した従業員を早期に発見し、重症化を防ぐための取り組みです。産業医や保健師、病院の医師など、事業場内外の専門家に従業員の健康状態を診断してもらい、現状把握に努めます。
産業医や外部の医師から従業員の体調が深刻と報告された場合、数日間の有給休暇取得や配置転換、休職などを検討します。
三次予防とはメンタルヘルス不調が原因で休職中の従業員が、スムーズに職場復帰できるように支援する取り組みです。従業員と定期的に連絡を取りながら、職場復帰に向けたスケジュール調整やリワークプログラムの作成をおこないます。
また、職場復帰後の再発を防ぐ取り組みも重要です。職場復帰からすぐにフルタイムで勤務するのは心身への負担も大きく、メンタルヘルス不調を再発する可能性が高まります。短時間勤務や試し勤務など、徐々に体を仕事に慣らしていく処置を取りましょう。
長時間労働の慢性化は、メンタルヘルス不調を招く大きな原因の1つです。睡眠不足が続くと自律神経のバランスが乱れ、頭痛や吐き気、めまいなどに悩まされます。また、健康時と比べて感情のコントロールが不安定になり、不安や抑うつを感じる傾向が強まります。
つまり、メンタルヘルスケアが必要な従業員を減らすには、業務負担軽減や生産性向上につながる取り組みを実践することが重要です。
職場環境を改善する方法には、以下6つの対策があげられます。
自社の課題や業務体制などを考慮し、実践する対策を選びましょう。
人手不足などによって従業員が慢性的に長時間労働をせざるを得ない環境にある場合は、業務プロセスのデジタル化を推進する必要があります。
人手不足解消の手段の1つである新規採用は、求職者の安定志向や採用費の高騰など、中小企業にとって厳しい状況が続いています。労働人口も減っており、自社の求める人材を短期間で採用できる保証はありません。
そのため、まずは従業員の負担軽減のためにITツールの導入を検討しましょう。ITツールの導入によって業務のデジタル化が進むと、業務効率を大幅に改善できます。
導入するITツールは、労務管理システムやSFA(営業支援ツール)、タレントマネジメントツールなど、部署や自社の課題に応じて判断しましょう。
また、製造業の場合は産業用ロボットを導入するのも1つの方法です。導入費用は高額ですが、人間が記録した手順通りに作業を再現し、長時間稼働してもパフォーマンスが落ちる心配もいりません。
アウトソーシングサービスとは、業務の一部を外部の専門企業に委託できるサービスです。営業事務や総務、コールセンター業務など、バックオフィス業務を中心に幅広い業務の代行を依頼できます。
アウトソーシングサービスを利用するメリットは、業務の効率性と正確性を高いレベルで保てる点です。豊富な実務経験や知識を持つ方が業務を代行するため、正確かつ素早い仕事ぶりが期待できます。
サービスを利用し続ける限り、一定水準以上の業務品質を確保できるため、新たに人材を採用する必要はありません。また、営業や商品開発など、売上に直結する業務に自社の従業員を優先的に配置できるようになります。
アウトソーシングサービスは人手不足に悩んでいる企業、人件費を削減したい企業に、おすすめの選択肢です。
慢性的な長時間労働も従業員がメンタルヘルス不調を発症する原因の1つです。残業で睡眠時間の不足が続くと、過労によってめまいや吐き気、頭痛などの症状に悩まされます。残業時間を減らすには業務体制の変更に加え、人事制度の見直しが必要です。
具体的には、残業時間の多さを肯定的に評価しない人事制度へ整備する必要があります。残業を肯定的にとらえる企業文化が残っていると、終業時刻までに仕事を終わらせる意識が従業員の間で浸透しません。
組織全体の残業時間を減らすためにも、成果や能力を重視する成果主義への切り替えを検討しましょう。
タレントマネジメントシステムとは従業員の能力や成果、職務経歴など、従業員一人一人に関する情報を一元管理できるシステムです。
ストレスチェックやアンケートなどの機能を搭載しているものもあり、従業員のメンタルヘルスを確認するツールとしても活用できます。
また、評価シートや組織図の作成、人事異動のシミュレーション機能なども搭載しているものであれば、人事業務の効率化も図れます。
人事担当者の負担を軽減したい企業、手軽にストレスチェックを実施したい企業におすすめの方法です。
首都圏に拠点を置く企業の場合、満員電車で勤務先に通勤する従業員も多いでしょう。従業員の通勤負担を軽減するため、テレワークを導入するのも1つの方法です。
満員電車での通勤は、車内の温度やにおい、他人との密着などの不快要素が多く、ストレスや疲労が蓄積します。心身の疲労は業務効率や正確性の低下に加え、メンタルヘルス不調を招く原因になります。
自宅やコワーキングスペースなどで働ける環境が整えば、通勤でのストレスが原因でメンタルヘルス不調を発症する心配はいりません。
また、テレワークは従業員と企業側、双方にとって多くのメリットをもたらす働き方です。以下の表にメリットの内容をまとめました。
| 従業員側 | 企業側 |
|---|---|
|
|
従業員側は通勤の負担軽減やプライベートな時間の増加などが主なメリットにあげられます。半面、テレワークを導入すると、オフィスワークよりもコミュニケーション不足に悩まされる可能性が高まります。
従業員間のコミュニケーション不足が心配な場合は、オフィスワークとテレワークを併用するハイブリッドワークを併用するのがおすすめです。
週に数日は従業員同士が顔を合わせる機会を設けられるため、業務の進捗状況や課題を共有しやすくなります。
すべての従業員にメンタルヘルスケアの重要性を理解してもらうため、積極的に研修の機会を設けましょう。外部の研修会社または産業保健総合支援センターに依頼して実施するのがおすすめです。
どちらも研修の経験が豊富なため、スムーズな進行とメンタルヘルスケアに関する最先端の知識習得も望めるでしょう。
また、部下への指導機会が多い管理職を中心に、ハラスメント研修への参加も検討しましょう。度重なるハラスメントもメンタルヘルス不調を招く原因の1つです。
特に職場で発生しやすいパワハラやセクハラに関しては、どのような言動が該当するのか、理解を深めることが重要です。
人事労務担当者のなかには、メンタルヘルス不調に悩む従業員を減らすにはどのように対応すべきか、わからない方もいるでしょう。対策に悩んでいる場合、社労士に相談するのがおすすめです。
人事評価制度の見直しやハラスメント、テレワークでの労務管理など、職場環境に関するさまざまな内容に関して相談できます。プロの視点から自社の職場環境を分析してもらえるため、今まで気づかなかった課題が見つかる可能性もあります。
また、勤怠管理や給与計算など、労務関連全般の業務を依頼できる点も魅力です。社労士は労働関連の法律や制度に精通した専門家です。豊富な知識を活用して正確かつ素早い仕事ぶりが望めるため、人事労務担当者の負担も軽減できます。
メンタルヘルスケア対策に悩んでいる方、労務管理業務の効率化を図りたい方は、社労士に相談しましょう。
メンタルヘルス不調に苦しむ従業員は、ストレスチェックだけでなく勤怠管理のデータからも可視化できます。今まで勤怠に乱れがなかった従業員に、遅刻・早退・欠勤が増えている場合は、要注意です。業務過多にともなう睡眠不足が原因で、うつ病や適応障害などを発症している可能性があります。
同じ部署の従業員と比べて、時間外労働の多さや入力ミスが目立つ場合も注意が必要です。メンタルヘルス不調を発症した従業員に対しては、事業場内外の医師や専門家を活用し、心身のケアや職場復帰の支援を実施します。
また、メンタルヘルス不調に苦しむ従業員を減らすには、生産性向上に向けた取り組みが必要です。ただし、どこから対策を進めていいかわからない方もいるでしょう。対策に迷っている場合は、社労士に相談するのがおすすめです。
客観的な視点から職場環境を分析してもらえるため、自社の課題や改善策を指摘してもらえます。メンタルヘルスケアや職場環境の改善にお悩みの方は、社労士への相談を検討しましょう。
| Q1.メンタルヘルスケアは何段階で実践しますか? |
|---|
| 一次予防・二次予防・三次予防の3段階です。メンタルヘルス不調が原因での離職者を減らすには、すべての段階で対策を充実させる必要があります。どの段階でどのようなケアをするのか、正確に理解しておきましょう。 |
| Q2.ストレスチェックが義務化されている企業とは? |
| 常時働く従業員数が50人以上の事業場です。ただし、義務化の対象外の事業場でも、メンタルヘルスケアは非常に重要です。従業員のメンタルヘルスを保てれば、業務の効率性や品質を高いレベルで両立できます。業務へのモチベーションや帰属意識も高く、ストレスによってメンタルヘルス不調を招く可能性も低いでしょう。 |