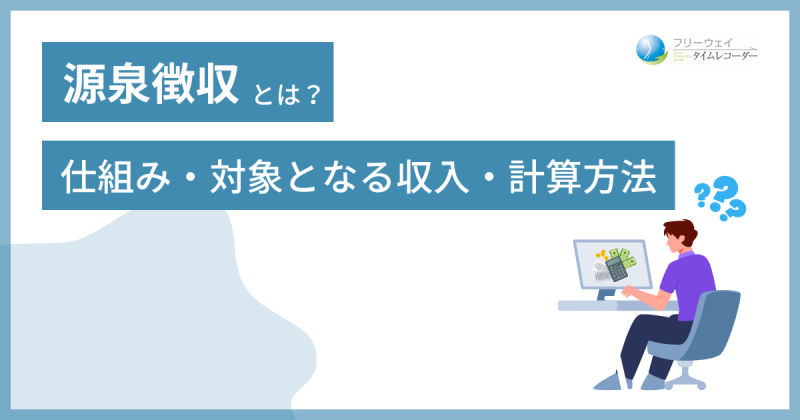
「給料から引かれている税金って何?」「源泉徴収って自分で計算する必要があるの?」
初めて給与明細を受け取ったとき、手取り額が予想より少なくて驚いた経験はありませんか?その差額の大きな部分を占めているのが「源泉徴収」です。
この記事では、源泉徴収の仕組みから計算方法まで、初めての方にもわかりやすく解説します。新社会人の方はもちろん、フリーランスや個人事業主になったばかりの方、小規模事業者として初めて人を雇う方も、この記事を読めば源泉徴収について理解できます。
源泉徴収とは、給与や報酬を支払う側(会社など)が、あらかじめ所得税を差し引いておき、本人に代わって国に納める制度です。
これにより、受け取る側の給与所得者は自分で税金を計算して納める必要がなくなります。
すべての人が自分で税金を計算して納税するとなると、個人にとって大変な負担となり、納税漏れのリスクがあります。
源泉徴収制度があることで:
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除・給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設、「扶養親族等の所得要件」の改正が行われました。
この改正は2025年12月1日に施行され、2025年分以後の所得税計算の対象になります。
年末調整の具体的な手続きについては、2025年8月末以降、国税庁のホームページに順次掲載予定です。
2024年1月から、電子取引で受け取った請求書や領収書などは、データのまま保存することが義務化されました。これにより、紙の保存が不要となり、業務効率の向上が期待されています。
電子データで保存していなかったからと言っても、すぐに青色申告が取り消されることはありませんが、義務化であるため、会社法第976条における帳簿や書類の記録・保存に関する規定に違反する可能性があり、注意が必要です。
源泉徴収の基本的な流れは以下のとおりです。
源泉徴収を行う義務がある人や組織を「源泉徴収義務者」といいます。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
小規模でも、従業員に給料を支払う場合は、源泉徴収義務がありますが、以下のような例外があります。
給与所得者が最も身近に感じやすいのは給与からの源泉徴収ですが、実は様々な所得が源泉徴収の対象になります。
これは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続き1年以上居所する個人が対象です。
以下は源泉徴収の対象となる主な所得です。
国税庁「令和7年版源泉徴収のしかた」より
フリーランスや個人事業主が受け取る報酬には、源泉徴収の対象になるものと対象外のものがあります。源泉徴収の対象となる報酬は、所得税法第204条に基づき、以下のように定められています。
(国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」より)
一方で、以下のような報酬は源泉徴収の対象外とされています。
これらの報酬は、源泉徴収の対象外であるため、支払者が所得税を差し引く必要はありません。詳細は、国税庁の「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」をご参照ください。

国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収税額表」を使用します。支払形態(月給・日給・賞与)によって税額表が異なります。
給与支給額から以下の控除を差し引きます。
控除後の金額が分かれば、税額表の該当部分を参照し、税額を確定できます。
具体例:月給30万円(控除後)の単身者の場合
さらに詳しく知りたい方へ:国税庁「No. 1100 所得控除のあらまし」をご参照ください
源泉徴収した所得税は、給与支払い月の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄する税務署へ納付します。納付方法は以下の5つがあります
納付期限内に納付しないと、延滞税や不納付加算税などの追徴課税が課せられます。
そのため、納付期限に関しては確認しておきましょう。
給与計算は一度覚えれば個人でも対応可能ですが、毎月の作業は煩雑で時間がかかります。特に手作業で計算していると、ミスのリスクが高まり、本業に集中しにくくなることもあります。こうした負担を軽減するには、専用の給与計算ソフトの導入がおすすめです。
フリーウェイジャパンのクラウド型給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」は、初心者でも扱いやすく、ダウンロードやインストールも不要です。シンプルな操作性と分かりやすいデザインで、気軽に導入できます。
また、料金も従業員5人までは無料で利用可能。それ以上の人数でも月額1,980円の定額料金で、コストパフォーマンスが高い点も魅力です。給与計算の効率化とミス防止にぜひ検討してみてください。
源泉徴収は、私たちの給与や報酬に直接関わる重要な税制度です。この記事では、初めて源泉徴収に触れる方にも理解しやすいよう、基礎から2024〜2025年の法改正情報までをお伝えしました。
特に注目すべき法改正には、
があり、これらの変更は源泉徴収事務にも影響します。最新の税制情報は国税庁のホームページで確認し、不明点は専門家に相談しましょう。
源泉徴収の計算や納付が負担に感じられる場合は、クラウド型の給与計算ツールを活用することで、業務効率化とミス防止につなげられます。
初めて社会人になった方も、フリーランスや個人事業主になったばかりの方も、小規模事業者として初めて人を雇う方も、源泉徴収の基本を理解することで、適切な経済計画や事業運営ができるようになります。複雑に感じる源泉徴収も、基本を押さえて専用ソフトを活用すれば、安心して対応できます。
| Q1.会社員と個人事業主で何が違うの? |
|---|
| 最大の違いは確定申告の必要性です。 会社員:会社が年末調整を行うため、基本的には確定申告は不要。ただし、副業収入がある場合や、医療費控除などは確定申告が必要になることもあります。 個人事業主:自分で所得や経費を計算し、毎年確定申告が必要です。 |
| Q2.アルバイトも源泉徴収されるの? |
| はい、アルバイトやパートも正社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて、あらかじめ所得税が差し引かれる(源泉徴収される)のが一般的です。勤務先が給与を支払う際に行います。 |