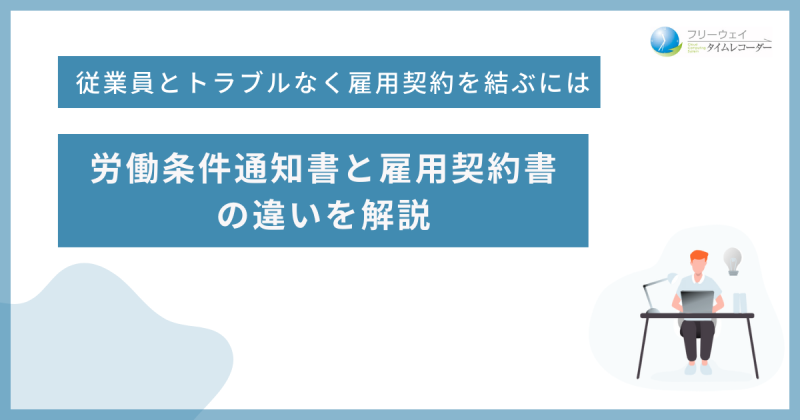
労働条件通知書と雇用契約書には、大きく以下の違いがあります。
従業員とトラブルなく雇用条件を結ぶには、「労働条件通知書は法律で締結が義務付けられているが雇用契約書に締結の義務はない」といった違いを把握したうえで、適切に運用することが大切です。
本記事では、労働条件通知書と雇用契約書の違いや作成方法、運用時のポイントなどを解説します。
目次
労働条件通知書と雇用契約書には、大きく以下4つの違いがあります。
「労働条件通知書」は、従業員の労働条件を記載した書類のことです。労働基準法第15条1項では、以下のように記載されています。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
引用:e-GOV法令検索
労働条件通知書は、正社員や契約社員、準社員、アルバイト、パートなど、雇用する全従業員への交付が必要です。派遣社員は直接雇用ではないため、労働条件通知書の交付は必要ありません。あくまでも「通知」が目的であるため、従業員による署名捺印は不要です。
「雇用契約書」は、従業員と企業の双方が、給料や勤務時間、勤務形態、福利厚生、就業場所などの雇用条件に同意したことを証明するための書類です。「同意していること」を証明するため、従業員と企業の双方が署名・捺印を行い、1部ずつ同じ書面を保有しておきます。ただし、書面での締結は法律で義務付けられていないため、当事者間が合意すれば口頭での契約も可能です。
「労働条件通知書」は、上記で解説したように労働基準法第15条1項で締結が義務付けられています。違反した場合は30万円以下の罰金に処される可能性があるため、注意してください。
参照:福岡県公式サイト|事業主のみなさま、人を雇うときには労働条件を知らせていますか?
「雇用契約書」には、法的な締結義務がないため任意で締結できます。
「労働条件通知書」は、雇用条件の通知を目的に交付するため、とくに双方の署名・捺印は必要ありません。次の章で解説している記載項目を満たしていればOKです。交付方法は、書面・FAX・メール・SNSメッセージなどから選べます。
「雇用契約書」は、雇用条件に同意していると示す必要があるため、双方の署名・捺印が必要です。
「労働条件通知書」では、以下のように記載項目が法律で指定されています。
絶対的明示事項(必ず記載すべき項目)
|
相対的明示事項(必要に応じて記載すべき項目)
|
参照:厚生労働省|2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか? p.2
「雇用契約書」に記載項目の指定はありません。ただし、雇用契約書は雇用条件に同意した旨を証明する書類であり、締結後の認識ズレによるトラブルを防ぐためにも、労働条件通知書と同じ項目を使うことが一般的です。
上記で解説したように、労働条件通知書は法律で締結が義務付けられています。一方で雇用契約書は締結が義務付けられていないため、必ずしも作成する必要はありません。
しかし、雇用契約書を締結していない場合、入社前に共有したはずの「雇用条件に対する認識」がズレてしまい、従業員とトラブルが起こる可能性も0ではありません。企業は同意したつもりでも、従業員が騙されたように感じれば今後の信頼関係に支障をきたします。
上記のような意図しないトラブルを回避するためにも、労働条件通知書だけでなく雇用契約書も締結しておいたほうが、お互いにとって安心です。
雇用契約書と労働条件通知書は、締結目的や交付方法などに違いはありますが、記載内容が大きく異なるわけではありません。「従業員に対して労働条件を通知する」という観点では同じ役割を果たしています。
そのため、雇用契約書と労働条件通知書を兼用した書類である「労働条件通知書兼雇用契約書」の活用もオススメです。法律で指定された「労働条件通知書の記載項目」を守れていれば、2つの書類を兼用しても問題ありません。
労働条件通知書と雇用契約書に記載すべき項目を、改めてまとめました。自社で作成した書類をチェックする際に活用してください。
絶対的明示事項(必ず記載すべき項目)
|
相対的明示事項(必要に応じて記載すべき項目)
|
労働条件通知書と雇用契約書は、どちらも同じ4つのステップで作成できます。
労働条件通知書(雇用契約書)のフォーマットは、従業員の雇用形態や業界、勤務時間などによって異なります。また、選考過程から面接官が仕事内容などを正しく候補者へ伝える必要もあります。
上記を考慮し適切なフォーマットで書類を作成できるよう、「どんな雇用形態で・どの仕事に就いてもらうのか」などを中心に、採用目的を明確に定めてください。
採用目的を定めたら、具体的な雇用条件を検討してください。以下の項目に沿って雇用条件を決めていくと、抜け漏れが発生しません。
絶対的明示事項(必ず記載すべき項目)
|
相対的明示事項(必要に応じて記載すべき項目)
|
雇用条件は従業員が快適に働けるかを決める重要な項目です。過去の採用条件や採用予定者のスキル、実績などを踏まえ適切な内容を定めてください。
雇用条件を決めたら、厚生労働省のサイトからフォーマットも活用しつつ書類を仮作成します。フォーマットをベースにしつつ、実際の雇用条件に合わせてカスタマイズすることがオススメです。労働条件通知書と雇用契約書を兼用する場合は、署名・捺印欄も設けてください。
可能であれば、採用活動の開始前に「自社が求める人材」を想定して作成しておくことがオススメです。採用開始後に初めて書類を作成すると、採用タスクの中で埋もれてしまい、通知書に抜け漏れが起きるかもしれません。
契約締結後に記載項目や雇用条件の抜け漏れが発覚すると内定者とのトラブルに発展するため、ミスなく雇用契約を結べるよう前もって記載しながら慣れていくことが大切です。
書類を作成したら、以下のようなポイントを押さえ、実際の運用・管理体制を決めてください。
労働条件通知書および雇用契約書は、「雇用条件を通知した」「双方が合意した」ということを示す重要な書類です。誤って運用して記載漏れが発生したり紛失したりしないよう、社内での運用・管理フローを厳格に決めてください。
労働条件通知書と雇用契約書をスムーズに作成・運用するには、以下のポイントを押さえてください。
繰り返しになりますが、労働条件通知書では以下の項目に抜け漏れがないか、必ずチェックしてください。
絶対的明示事項(必ず記載すべき項目)
|
相対的明示事項(必要に応じて記載すべき項目)
|
とくに「絶対的明示事項」は全企業で必須であるため、自社の雇用条件を細かく確認してください。
書類を作成する際は、以下のように雇用形態に応じたポイントを踏まえてください。
とくに契約社員やパート、アルバイトの記載条件については、法律で定められているため必ず確認してください。
労働条件通知書と雇用契約書は、従業員の入社前に「この雇用条件で採用しますがよいですか」という旨を確認する書類です。そのため、本格的な雇用開始前のタイミングである「内定日」あるいは「入社日」で締結してください。
以下のような運用方法は不適切です。
労働条件は、書面での交付が原則です。ただし、以下の条件を満たしていれば「FAX・Eメール・SNSメッセージ機能」などでの電子管理も可能です。
電子契約は電子帳簿保存法に基づいているため、必ず電子データを残しておく必要があります。電子帳簿保存法について詳しく知りたい場合は、「電子帳簿保存法とは?概要や対象書類、企業に必要な対応および手順をわかりやすく解説」をご覧下さい。
参照:厚生労働省|平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります
労働条件通知書は、発行から5年間は保管しなければなりません。万が一、従業員と雇用条件に関すトラブルが起きた際、スムーズに確認できるようなるべくキレイな状態で保管してください。
「厚生労働省|様式集」には、労働条件通知書や雇用契約書の作成時に使えるテンプレートが用意されています。「有期雇用の一般労働者用」「短時間労働者用」「林業労働者用」など、さまざまなケースで使えるテンプレートが揃っているため、自社の状況を踏まえて最適な様式を活用してください。
労働条件通知書と雇用契約書は、大きく以下の点で違いがあります。
締結目的の違い
|
法的な締結義務の違い
|
交付方法の違い
|
記載項目に関する指定の有無
|
雇用契約書の締結は、法律で義務付けられていません。しかし、雇用条件を明文化し従業員と同意しておくことで、入社後に起こりがちな認識ズレによるトラブルを防止できます。労働条件通知書と雇用契約書は兼用できるため、意図しないトラブルを避けるために一緒に作成しておくことがオススメです。
| Q1.労働条件通知書と雇用契約書はどのように違いますか? | ||||
|---|---|---|---|---|
|
労働条件通知書と雇用契約書の主な違いは、以下の通りです。
|
||||
| Q2.絶対的明示事項とは何ですか? | ||||
|
「絶対的明示事項」は、書面に記載して明示するよう労働基準法15条で定められている事項であり、以下が該当します。
|
||||
| Q3.労働条件通知書と雇用契約書は兼ねてよいですか? | ||||
|
労働条件通知書と雇用契約書は、兼用しても大丈夫です。兼用の際は、法律で指定された「労働条件通知書の記載項目」を遵守してください。 |
||||
| Q4.労働条件通知書と雇用契約書を交付するタイミングは? | ||||
|
「内定日」あるいは「入社日」のタイミングでの締結が望ましいとされています。いずれの書類も雇用条件について確認するものであるため、本格的な入社前に締結してください。 |
||||
| Q5.労働条件通知書と雇用契約書は書面以外でも交付できますか? | ||||
|
書面での交付が原則ですが、以下の条件を満たせば「FAX・Eメール・SNSメッセージ機能」などでも締結可能です。
|