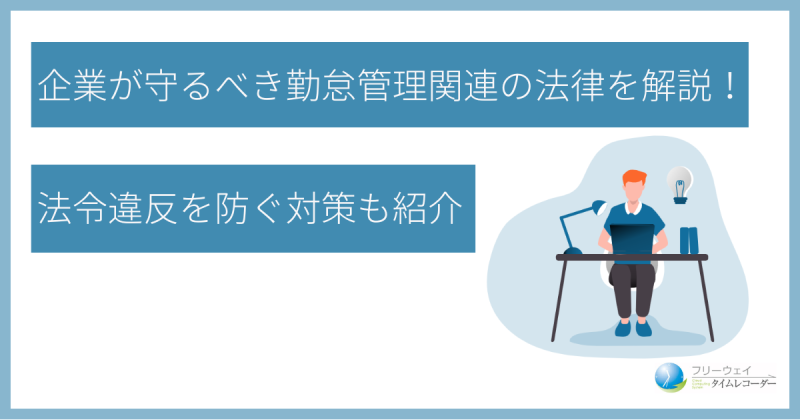
労働基準法や労働安全衛生法など、労働関連の法令違反を避けるには、厳重な勤怠管理を継続して実施しなければなりません。法令違反とみなされると罰則を科されるため、法律の内容や各制度のルールを正確に覚えておく必要があります。
この記事では、企業が守るべき勤怠管理関連の法律や法令違反を防ぐ対策などに関して、紹介します。
勤怠管理を担っている労務担当者の方、従業員との労務トラブル発生にお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
労働基準法や労働安全衛生法など、労働関連の法律で定められている勤怠管理のルールを11個紹介します。
内容を1つずつ見ていきましょう。
労働安全衛生法の改正にともない、2019年4月から従業員の労働時間を客観的な方法で記録することが、各企業に義務付けられました。「客観的な方法」の例にはタイムカードやICカードによる記録、PCのログイン・ログオフ履歴などがあげられます。
やむを得ない理由がない限り、エクセルでの管理や出勤簿への記入など、自己申告制による労働時間の管理は認められません。やむを得ない理由としては、社外からシステムにアクセスできないなど、労働時間を客観的な方法で記録できない場合があげられます。
また、客観的な方法で記録した従業員の出退勤時刻や労働時間は、経営者または労務担当者が確認しなければなりません。記録した勤怠データは賃金台帳に反映し、タイムカードや残業申請、労働者名簿などとともに、5年分保存しておく必要があります。
労働関連の書類や帳簿の保存義務に関しては、労働基準法第108条、109条に定められています。
2024年4月の労働基準法第5条改正にともない、労働者を採用する際に必要な労働条件明示のルールが変更されました。労働者と雇用契約を締結する際、有期雇用契約を更新する際は、就業場所や業務内容の変更有無に関する明示が必要です。
また、パートやアルバイトなどの有期雇用契約者との契約を更新する際、明示が必要な事項を以下の表にまとめました。
| 更新上限 | 更新上限を新設・短縮する場合 | 無期転換申込機会の明示 | 無期転換後の労働条件の明示 |
|---|---|---|---|
| ・有期雇用契約の締結と契約更新の際、更新回数の上限と内容を提示 | ・更新上限回数の設置や契約期間の短縮理由に関して、事前に説明が必要 | 無期転換申込権が発生するタイミングで、申請が可能な旨を説明 | 無期転換申込権が発生するタイミングごとに、労働条件を明示 |
既に、労働者と雇用契約を締結する際には雇用形態を問わず労働条件通知書を交付するよう義務付けられています。労働条件の明示や労働条件通知書の交付を怠った場合は、法令違反とみなされます。
労働者への賃金支払いに関して、労働基準法第24条では以下5つに関する原則を規定しています。
1に関しては従業員本人からの同意が得られない限り、原則日本円で賃金を支払わなければなりません。実務上、一般的に行われている銀行などへの「口座振り込み」も、通貨払いの原則に反する内容であるため、従業員本人からの同意が得る必要があることに注意しましょう。また、同意の内容によっては退職金の小切手支払いや自社株による支払いも認められます。
2に関しては仲介者ではなく、労働者本人に直接給与を支払わなければなりません。仲介者を経由すると、給与や賞与の一部が搾取される可能性があるためです。
3に関しては残業代や手当を含め、全額を支払わなければなりません。ただし、給与・賞与の総支給額から健康保険料や厚生年金、所得税などを差し引き、控除額を支給する行為は法令違反に該当しません。
また、労使協定を締結している場合、社宅費や組合費などの天引きも可能です。
4に関しては従業員が金銭面への不安を感じずに日々の生活を送れるよう、毎月1回は給与を支払わなければなりません。経営状況の悪化を理由に1ヵ月半や2ヵ月に1回の支払いとした場合、法令違反とみなされます。
5に関しては「20日支払い」や「30日支払い」など、毎月決まった日に賃金を支払わなければなりません。ただし、支払日が休日の場合や期日を月末に設定した場合は、別日での支払いが認められます。
労働基準法32条によって、労働者の労働時間は1日8時間、週40時間と上限が定められています。上記の時間は法定労働時間と呼ばれ、経営者が従業員に法定労働時間を超える労働を命じるには、36協定を締結しなければなりません。
36協定とは、時間外労働や休日労働に関する労働者と企業側の取り決めです。36協定を締結せずに時間外労働や休日労働を従業員へ命じた場合、法令違反とみなされます。
また、36協定を締結しても、時間外労働+休日労働の合計時間は月45時間、年360時間以内に収める必要があります。2019年から施行された働き方改革関連法にともない、時間外労働の上限が罰則付きで定められました。
月45時間、年360時間を超える労働を命じるには、特別条項付きの36協定を締結する必要があります。労働基準法36条にもとづき、特別条項付きの36協定を締結した場合、上限を超える労働を命じられます。
ただし、36協定を超える時間外労働を命じるには、以下の要件をすべて守らなければなりません。
「臨時的な特別な事情」とは、決算業務や大規模なクレーム対応など、予測不可能な業務量の増加が発生した場合を指します。「慢性的な人手不足」や「業務上の都合」といった理由では、36協定を超える時間外労働は命じられません。
労働基準法第34条では、1日の労働時間に応じた休憩時間を確保するように定めています。1日の労働時間が6時間超〜8時間以内の場合は、少なくとも45分の休憩時間を確保しなければなりません。
1日の労働時間が8時間を超える場合、休憩時間は最低でも1時間以上確保する必要があります。また、労働基準法第33条には休憩の3原則が定められており、経営者は基本的に以下3つの原則を守らなければなりません。
一斉付与の原則とは雇用形態や職種を問わず、事業場で働くすべての従業員に同じタイミングで休憩時間を与えるという原則です。ただし、運輸交通業や通信業など、業界によっては例外の適用が認められています。
自由利用の原則とは、休憩時間中は従業員を業務から完全に解放するという原則です。
たとえば、来客対応や電話番のためにオフィスに留まるよう、従業員へ指示したとしましょう。
その場合、来客対応や電話番は待機時間に該当するため、休憩時間とはみなされません。別途休憩時間を確保しなければ法令違反とみなされます。また、従業員の休憩時間の使い方に関して、企業側は干渉できません。
そして、途中付与の原則とは、就業時間中に休憩時間を与えるという原則です。始業時間前や終業時間後に休憩時間を与える行為は、禁止されています。
労働基準法第35条では、従業員に毎週少なくとも1日は休日を与えなければならないと定めています。上記の休日を法定休日と呼び、年間換算すると52日の法定休日の確保が必要です。
また、法定休日は法定労働時間とも密接に関連しています。労働基準法第32条では、週40時間を法定労働時間の上限と定め、上限を超える労働は時間外労働として扱われます。
時間外労働の超過による法令違反を防ぐには、法定労働時間内に労働時間を抑えることが重要です。仮に週5日×8時間勤務を従業員に命じる場合、法定休日が52日では法定労働時間内に労働時間が収まりません。
1年間の法定労働時間は2085時間、1日の法定労働時間は8時間です。2085÷8=約260で、260日を労働日として換算すると、年間休日は365-260=105日必要になります。
つまり、労働基準法違反を防ぐには業種を問わず、最低でも105日の年間休日を確保しなければなりません。
法定労働時間を超えた労働を命じる際は36協定の締結とともに、割増賃金の支払いが必要です。労働基準法第37条には、割増賃金の支払いを義務付ける規定が定められています。
割増賃金は、従業員の1時間あたりの賃金×割増率×労働時間によって算出します。割増率は時間外労働や深夜労働、休日労働など、労働の種類によって掛け率が異なるため、注意が必要です。労働ごとの割増率を以下の表にまとめました。
| 労働の種類 | 要件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 法定労働時間を超えて労働を命じた場合 | 25%以上 |
| 36協定を超える時間外労働を命じた場合 | 25%以上 | |
| 1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合 | 50%以上 | |
| 深夜労働 | 22:00~5:00の間に労働を命じた場合 | 35%以上 |
| 休日労働 | 法定休日に労働を命じた場合 | 35%以上 |
| 時間外労働+深夜労働 | 法定労働時間を超える労働に加え、22:00~5:00の間に労働を命じた場合 |
|
| 休日労働+深夜労働 | 法定休日に労働を命じた上、22:00~5:00の間に労働を命じた場合 |
|
たとえば、1時間あたりの賃金が1,500円の従業員がいたとしましょう。週60時間働いた場合、時間外労働は20時間となります。割増賃金は1500×1.25×20=37,500円です。
残業代の未払いは、従業員とのトラブルが起こりやすい内容の1つです。労務トラブルが発生しないよう、勤怠管理と給与計算には細心の注意を払いましょう。
労働基準法第39条にもとづき、雇用形態を問わず一定の要件を満たした従業員には、年次有給休暇を付与しなければなりません。要件は以下の2つです。
有給休暇の付与日数は、雇用形態や勤続年数に応じて変動します。正社員の有給休暇の付与日数に関して、以下の表にまとめました。
| 勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有給休暇の付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
正社員として働く従業員の場合、勤続年数が6年半を超えたとしても、年次有給休暇の付与日数は最大で20日です。
また、有期雇用契約者に関しては勤続年数に加えて、週の所定労働日数や労働時間によって、有給休暇の付与日数が変動します。
有期雇用契約者の有給休暇の付与日数に関して、以下の表にまとめました。
| 週の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 勤続年数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
| 付与日数 | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| 1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
週の所定労働日数が3日以上、勤続年数が5年半を超える有期雇用契約者は、有給休暇の取得状況も注視するようにしましょう。
5日以上の有給休暇取得が義務付けられている対象に、含まれているためです。
労働基準法改正にともない、1年で10日以上の有給休暇を付与されている従業員は、年内に5日以上の有給休暇取得が義務付けられました。有給休暇を付与した日を基準日として定め、対象の労働者は1年以内に5日以上の有給休暇を取得しなければなりません。
また、1年以内に5日以上有給休暇を消化できなかった労働者が、1人でも発生した場合は法律違反とみなされます。
さらに、基準日に有給休暇を付与しなかった場合、有給休暇に関する規定を就業規則に未記載の場合も、法令違反として扱われます。
労働基準法第60条、61条にもとづき、満18歳未満の年少者に対しては時間外労働を命じられません。仮に年少者自身から残業希望があったとしても、経営者は法定労働時間である1日8時間、週40時間以内に労働時間を抑える必要があります。
満1歳未満の子どもを育てる女性従業員から請求があった場合、企業側は最低でも1日に30分×2回の育児時間を確保しなければなりません。労働基準法第67条には女性労働者から請求があった際、休憩時間とは別に育児時間を確保するように定められています。
混同しやすいですが、育児・介護休業法に定められた「育児休業」とは異なりますので注意が必要です。
労働基準法における「育児時間」は、もともと授乳時間を確保することを趣旨として定められたため、対象が女性に限られています。
育児時間の請求を拒否した場合、労働基準法違反とみなされます。また、育児時間の請求は雇用形態を問わず、満1歳未満の子どもを持つ女性従業員であれば、誰でも可能です。
ただし、1日の所定労働時間が4時間以内の従業員に対しては、育児時間が1日に30分×1回に短縮されます。そして、育児時間の用途に関しては子どもへの授乳に加え、保育園の送迎など幅広く活用できます。
労働基準法をはじめ、勤怠管理に関する法令に違反した場合、以下3つの悪影響が生じます。
どのような対応をした場合に罰則が生じるのか、理解しておくことが重要です。
労働基準法や労働安全衛生法などの規定を守らなかった場合、法律違反とみなされます。ただし、すぐに罰金や刑事罰が科されるわけではありません。労働基準監督署による事業場の立ち入り調査がおこなわれ、職場環境を改善するように是正勧告を受けるのが一般的です。
是正勧告に対して素早く対応すれば罰則を避けられるでしょう。また、立ち入り調査で法律違反が深刻と判断された場合、是正勧告を待たずに30万円以下の罰金や6ヵ月以下の懲役が科されます。賃金の中間搾取や従業員の意思に反する強制労働を命じていた場合は、罰金額と懲役刑が重くなります。
さらに、法令違反の実態がマスメディアやSNSで拡散されると、イメージダウンや多額の利益損失は避けられないでしょう。
残業代の支払いや有給休暇の付与など、従業員からの要請を改善しない場合、従業員との労務トラブルに発展する可能性が生じます。最悪の場合は裁判沙汰となり、勤怠管理を厳正に管理していた証拠を示せない限り、敗訴となる可能性が高まります。
労務トラブルや敗訴の実態が報道された場合、社会的信用低下やイメージダウンは避けられないでしょう。
また、「従業員を大切にしないブラック企業」との印象が定着し、求人への応募率も低下します。
上限を超える時間外労働や賃金未払いなどの状態を続けた場合、労働基準監督署から申告調査を受ける可能性が高まります。労働基準監督署は労働基準法をはじめ、企業が労働関連の法律を守っているか、取り締まる機関です。
労働者にとっては上限を超える時間外労働や賃金未払いなど、自身の置かれている状況に関して相談できる機関です。労働者から調査依頼を受けた労働基準監督署は、抜き打ちで事業場の立ち入り調査を実施します。
従業員からの申告をきっかけにおこなわれる調査は、申告監督と呼ばれます。明確な理由がない限り、労働基準監督署からの申告監督を拒否できません。拒否した場合は監督官にネガティブな印象を与え、後日強制捜査に踏み切られます。
監督官は警察官と同様、強制捜査をおこなう権限を持っているためです。監督官の権限に関しては、労働基準法にも定められています。
また、申告監督で法令違反の度合いが酷いと判断した場合、経営者の逮捕や送検に踏み切る場合もあります。
労働関連の法令違反を防ぐには、正確な勤怠管理や業務効率改善に向けた取り組みが必要です。以下5つの対策が選択肢にあげられます。
上記の対策を講じると、従業員が働きやすい職場環境を整備でき、法令違反や労務トラブルのリスクを減らせます。自社に合った対策を講じ、従業員の負担を軽減しましょう。
時間外労働の超過や残業代の未払いなどを防ぐには、クラウド型の勤怠管理システムを導入するのが有効です。勤怠管理システムの導入によって、労働時間や時間外労働、有給休暇の取得状況など、従業員の勤怠データをシステム上で一元管理できます。
勤怠データの集計はシステムに任せられるため、労務担当者が作業する必要はありません。業務の自動化によって、勤怠管理の正確性と効率性を高いレベルで両立できます。
また、給与計算システムと連携した勤怠管理システムも多く、スムーズなデータ取得によって残業代未払いのリスクを抑えられます。さらに、クラウド型の勤怠管理システムは、システムの導入や維持にかかる負担が小さい点も魅力です。
一定のサービス料金を支払う代わりに、サーバーを調達する必要がありません。アップデートやメンテナンスもベンダー側が対応するため、システム管理者の負担を軽減できます。
さらに、法改正が起きても改正内容に応じた自動アップデートでの対応によって、意図しない法律違反も避けられます。
労務管理システムとは、従業員の入退社や社会保険の加入手続きを効率化できるシステムです。個人情報の収集〜雇用契約の締結まで、一連の流れをシステム上で完結できます。
個人情報は従業員自身がスマートフォンやPCから入力するため、労務担当者は収集した情報をシステム上に転記する必要はありません。
仮に誤記や記載漏れがあってもシステム上で修正指示を送れるため、スムーズに手続きを進められます。また、労働条件通知書や雇用契約書など、雇用契約の締結に必要な書類は、システム上にテンプレートが用意されています。
労働条件が詳細に明記された労働条件通知書や雇用契約書を作成しやすくなり、採用後のトラブルや早期離職を防げるでしょう。
さらに、作成した書類の送付〜雇用契約の締結までは、オンライン上で進められるため、紙書類の印刷や配布は必要ありません。労務管理システムの導入によって、雇用契約の効率化とペーパーレス化の促進を図れます。
労務管理システムの導入は、雇用契約締結でのトラブルが多い企業におすすめの選択肢です。
慢性的な長時間労働を従業員に強いている企業は、業務体制の変更をすぐに検討しなければなりません。長時間労働の常態化によって、従業員のモチベーションや帰属意識、業務の生産性が低下します。
状況が改善されないと離職者が相次いで特定の従業員への負担が増し、最悪の場合は違法労働や法令違反を招くでしょう。従業員の労働時間を削減する手段には、ITツールの導入とアウトソーシングの活用があげられます。
ITツールはSaaSを利用するのがおすすめです。SaaSとは、PCにインストールするソフトウェアと異なり、サービス提供事業者が管理するインターネット上のサーバーで稼働しているサービスを指します。
一定のサービス料金を支払う代わりに、サーバーの調達やメンテナンスなどを自社で対応する必要はありません。初期費用や月額料金を比較的安く抑えられます。
一方、アウトソーシングは業務の一部を外部の専門企業に委託できるサービスです。人事労務や経理、営業事務など、バックオフィス業務を中心に業務の代行を依頼できます。実務経験豊富な方が業務を担当するため、素早く正確な仕事ぶりが期待できます。
就業規則は職場内での規律や労働条件などをまとめたルールブックです。労働時間や賃金、安全衛生など、企業側と労働者側が守るべき内容が記載されています。就業規則の記載事項は、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項、大きく2つに分けられます。
双方に該当する事項を以下の表にまとめました。
| 絶対的必要記載事項 | 相対的必要記載事項 |
|---|---|
|
|
相対的必要記載事項の内容は企業ごとに対応が委ねられていますが、ルールを設けた場合は必ず規定を明記しなければなりません。就業規則を作成する目的の1つに、従業員が働きやすい職場環境の整備があげられます。
特に賃金や労働時間など、勤怠管理に関連する規定は、労働者側とのトラブルや法令違反を招きやすい内容です。就業規則の定期的な見直しによって労働条件を可視化し、トラブルの回避に努めましょう。
勤怠管理関連の法令違反を避けるために、どのような対策を講じるべきか、わからない方向けの選択肢です。社労士には法改正の内容解説や賃金制度の再整備、就業規則の見直しなど、さまざまな内容を相談できます。
労務コンサルティングにも対応しており、プロの視点から自社の職場環境の問題点や対策に関してアドバイスが得られます。また、給与計算や勤怠管理、社会保険の加入手続きなど、労務管理の業務代行を依頼できる点も魅力です。
社労士は労働や社会保険関連の法律や制度に精通した専門家です。豊富な知識にもとづく正確かつ素早い仕事ぶりが望めるため、給与の未払いや残業過多による法令違反を避けられます。
さらに、労務管理の業務代行はスポットで対応している社労士事務所も多く、必ずしも雇用契約を締結する必要はありません。
社労士への相談は職場環境の見直しを進めている企業、労務担当者の負担を減らしたい企業に、おすすめの選択肢です。
勤怠管理関連の法令違反を避けるには、クラウド型の勤怠管理システムを導入し、勤怠管理の正確性を高めることが重要です。勤怠管理システムの導入によって、出退勤時刻や労働時間、時間外労働の時間など、従業員の勤怠データを一元管理できます。
勤怠データの集計はシステムが自動でおこなうため、労務担当者が作業する必要はありません。あわせてアウトソーシングの活用や就業規則の見直しなど、自社に必要な対策を講じて、職場環境の改善に努めましょう。
従業員が働きやすい職場環境を整えられると、業務負担増大にともなうモチベーション低下を避けられます。生産性の向上によって残業時間も減り、労務トラブルや法令違反を招くリスクも減らせるでしょう。
また、法令違反の対策をどこから始めるべきか悩んでいる企業は、社労士に相談するのがおすすめです。法改正の解説も含め、就業規則や賃金制度の見直しなど、さまざまな内容を相談できます。
| Q1.労働時間と時間外労働の上限は? |
|---|
|
法定労働時間は1日8時間、週40時間が上限です。36協定を締結した場合、時間外労働は月45時間、年360時間まで命じられます。特別条項付き36協定を締結しない限り、月45時間、年360時間を超える労働は命じられません。 |
| Q2.有給休暇は何日以上取得させる必要がありますか? |
|
年10日以上有給休暇を付与されている従業員は、基準日から1年以内に5日以上の有給休暇を消化しなければなりません。仮に対象の従業員が1人でも5日以上の有給休暇を消化できなかった場合、法律違反とみなされます。 |