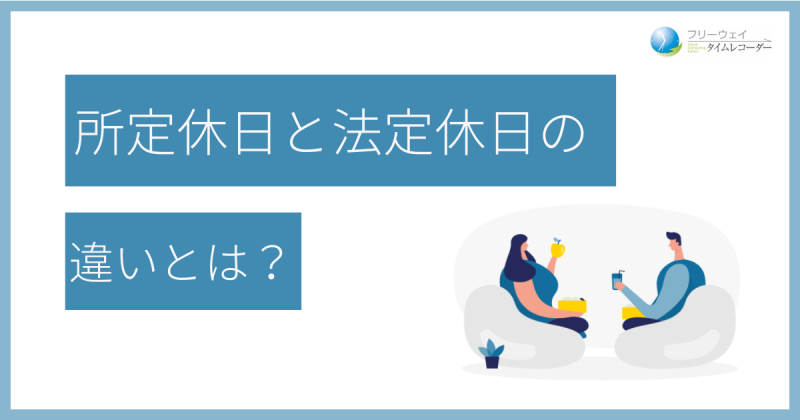
法定休日と所定休日は、どちらも同じ「休み」を意味する言葉です。しかし、実際は「従業員が休日出勤した際に支払う割増賃金率」「振替休日や代休を付与する際の対応方法」に関する扱いが異なります。そのため、企業の担当者は「同じ休日」と考えず、違いを正しく理解することが必須です。
本記事では、法定休日と所定休日の違いやそれぞれの割増賃金率、振替休日・代休の扱い方などについてわかりやすく説明します。
法定休日と所定休日の主な違いは以下の通りです。
法定休日とは、労働基準法第35条で「付与が義務付けられている休日」のことです。具体的には、以下いずれかの要件を満たすことが定められています。
上記の要件を満たしていれば、何曜日に休日を設定しても問題ありません。
もし法定休日に従業員を出勤させた場合は、休日手当として割増賃金を支払う必要があります。残業の有無に関わらず「休日出勤させた段階」で割増賃金が発生するため、間違えないようにしてください。
所定休日とは、法律による付与の義務が定められていない休日のことです。付与の義務はないため、従業員に休日を取らせるかは企業の裁量に任せられています。
しかし、労働基準法第32条で定められた「労働時間は1日8時間および1週間で40時間を超えてはならない」という規定を守るには、法定休日だけでは足りないケースがほとんどです。そのため、多くの企業が所定休日を設けています。
所定休日は法律で定められた休日ではないため、従業員が出勤しても休日手当は発生しません。ただし、残業によって勤務時間が週40時間を超えた場合は、割増賃金の支払いが必要です。
週2日の休日のうち「どちらを法定休日とするか?」は、企業の就業規則によって異なります。一例は以下の通りです。

このように、法定休日と所定休日は「法的に付与が定められているか否か」という点が異なります。
従業員からすると、両者は同じ「休日」であるため、大きな違いを実感できないかもしれません。とくに現在では「平日に働いて土日に休む」というスタイルが浸透しているため、改めて自分の休日の違いを把握する機会もないはずです。
ただし企業視点で見ると、法定休日と所定休日のどちらに該当するかによって「割増賃金率」が異なるため、必ず確認してください。
割増賃金とは、休日出勤した従業員へ支払う賃金に、一定額を上乗せすることです。割増賃金率の違いを把握していなければ、正確な賃金計算ができず「十分な賃金を支払えていない」といった事態にもなりかねません。
賃金の支払いミスは、従業員との関係性に悪影響を与えるため、企業の担当者は必ず確認してください。
参照:厚生労働省 | Q.法定労働時間と割増賃金について教えてください。
法定休日に従業員が出勤した場合の割増賃金率は「通常時の35%」です。残業の有無に関わらず、普段の1日の賃金額に35%を上乗せしてください。
例えば、時給1,400円の従業員が法定休日に8時間働いた場合、支払う賃金は以下の通りです。
(1,400円×8時間)×1.35=15,120円
さらに、もし「法定休日」かつ「深夜帯(22時〜翌5時)」にかけて勤務した場合、割増賃金率は「法定休日にかかる35%+深夜労働にかかる25%=60%」です。
ただし、法定休日に残業したとしても、時間外労働にかかる25%を上乗せする必要はありません。
所定休日に従業員が出勤した場合、通常勤務と同じ扱いになるため、割増賃金は発生しません。
ただし、残業によって「1日8時間・1週40時間」を超過した場合は、超過分に対して「25%」の上乗せが必要です。法定休日と異なり「超過した時間分にのみ」割増賃金が適用されます。
例えば、時給1,400円の従業員が所定休日に働き「1週の労働時間が40時間を6時間超過した」という場合、支払う割増賃金は以下の通りです。
(1,400円×6時間)×1.25=10,500円
もし、「所定休日」かつ「深夜帯(22時〜翌5時)」に勤務した場合、割増賃金率は「所定休日にかかる25%+深夜労働にかかる25%=50%」です。
従業員が法定休日あるいは所定休日のいずれかに出勤した場合、「振替休日を与える」「代休を取ってもらう」といった対応が必要です。
同じ休日ですが、どちらを利用するかによって割増賃金の支払い有無が変わるため、企業の担当者は必ず確認してください。
振替休日とは、本来決まっていた休日と出勤日を入れ替えることです。休日出勤を行う前に、入れ替えておきます。
事前に休日と出勤日を入れ替えているだけであるため、休日出勤扱いとはならず割増賃金も発生しません。
ただし、入れ替えた結果「1週の労働時間が40時間を超えた」という場合、割増賃金として25%の上乗せが必要です。
例えば「日曜(本来の休日)と同じ週の月曜日(本来の出勤日)」を入れ替えて、なおかつ残業などが発生しなかった場合、週の労働時間数は40時間で変わらないため、割増賃金は発生しません。
一方で「日曜(本来の休日)と翌週の月曜日(本来の出勤日)」を入れ替えた場合、日曜があった週の労働時間が40時間を超えるため、残業などが発生しなくても割増賃金は発生します。
振替休日を設定する場合は、就業規則に「休日を入れ替える可能性がある」という旨を明記してください。
代休とは、休日出勤後に従業員へ代わりの休日を与えることです。事前に休日と出勤日を入れ替える振替休日と異なり、すでに発生した休日出勤に対してあとから付与するため、割増賃金が上乗せされます。割増賃金率は、法定休日に出勤した場合は「35%」、所定休日に出勤した場合は「(超過分に対して)25%」です。
代休を設定する場合、就業規則に「休日出勤の可能性がある」という旨を明記したうえで、36協定を締結してください。
法定休日と所定休日の話題に関連して、「休日・休暇の違い」も確認してください。一般生活ではほぼ同じ言葉として使われますが、労務上では以下のような違いがあります。
休暇は、さらに以下の2種類に分けられます。
| 休暇の種類 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 法定休暇 | 法律で従業員への付与が義務付けられている | |
| 法定外(特別)休暇 | 法律の定めが設けられておらず、企業が独自に決められる |
|
最近では、社員が個人的な趣味の活動に使える「推し活休暇」やペットを亡くした社員が使える「ペット慶弔休暇」など、企業独自の法定外(特別)休暇を福利厚生として提供する企業も増えています。
法定休日や所定休日の違いに加えて、休暇の種類も正しく理解することで、従業員へ適切な休みを与えられます。
法定休日と所定休日を理解し、法律に沿って正しく運用するには、以下のポイントを意識してください。
法定休日については、法律で定められた以下いずれかのルールを守って設定してください。
もちろん、ルールに沿っているからといって「1週間に1日だけ休ませればよい」というわけではありません。あくまでも原則であり、従業員の健康を考えると週に2回以上の休日を与えることが理想です。
36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定です。「法定休日に出勤させる」「所定休日に出勤させた結果として時間外労働が発生する」といった場合は、事前に労働基準監督署へ届け出ておく必要があります。休日の種類に関わらず、休日出勤をお願いする可能性がある時点で36協定を締結したほうが安心です。
もちろん、36協定を結んだからといって、決して無制限に働かせてよいわけではありません。36協定を締結しても、時間外に「月45時間・年360時間」を超えて働かせることは禁止です。上限を超えた場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となるため注意してください。
36協定の詳細については、以下の記事をご確認ください。
関連記事:三六協定とは?担当者が押さえたい基礎事項や具体的な締結手順、運用のポイントをわかりやすく
法定休日および所定休日に関わる内容は、必ず就業規則に明記してください。休日に関わるルールを明文化し従業員に浸透させることで、「休日の取り扱い方が自分のイメージと違う」といったトラブルが発生することを防げます。
就業規則に明記すべき内容として、例えば以下が挙げられます。
他にも「休日出勤である旨は前日までに通知する」「振替休日はなるべく週内で設定してもらう」といった細かい点まで明記しておけば、トラブルの発生リスクを減らせます。
就業規則の変更が必要な場合は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:【2023年4月法改正】就業規則の見直しチェックリストと変更時の5ステップ
休日出勤に関して、基本的に一般の正社員やパート、アルバイトの扱いは同じです。ただし、雇用形態によっては休日出勤の取り扱い方が変わるため、必ず明文化してください。
具体的な「従業員の雇用形態ごと」における注意点は以下の通りです。
| 雇用形態 | 主な注意点 |
|---|---|
| パート・アルバイト | 基本的に一般の正社員と同じ |
| 派遣社員 | 基本的に一般の正社員と同じだが、派遣元との36協定の締結が必要 |
| 年俸制 | 「年俸に休日出勤手当を含むか否か」を定める |
| フレックスタイム制 | 休日出勤を想定していないため、別途で支払いが必要 |
休日の単位は、原則として「暦日(午前0時からの24時間)=丸1日」で与える必要があります。連続して1日の休みを与えることが原則であり、以下に該当する場合は休日にカウントされません。
参照:徳島労働局|休憩・休日
勤怠管理システムを活用して、休日を正しく管理することも有効です。勤怠管理システムとは、従業員の出退勤時間や休憩時間などを網羅的に管理できるシステムです。
勤怠打刻や勤怠集計に加え、休日の労働時間や残業時間、具体的な日数などを細かく管理できる製品もあります。そのため、効率的かつ正しく従業員の休日を管理可能です。
具体的な勤怠管理システムの機能や製品の選び方などは、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:勤怠管理システムとは?機能や導入メリット、初めての方でも迷わない選び方のポイントなどを詳しく解説
もし勤怠管理システムを検討しているなら、株式会社フリーウェイジャパンが提供する「フリーウェイタイムレコーダー」も選択肢に入れてみてください。フリーウェイタイムレコーダーは、従業員10名までなら「完全永久無料」で使える勤怠管理システムです。ICカード打刻やスマホ打刻、勤怠集計、位置情報の取得など、勤怠管理に必須の機能に絞ることで、リーズナブルな価格を実現しました。
もちろん、休日の勤怠管理に関わる「所定休日と法定休日の労働時間」「休日出勤の日数」「休日の残業時間」も集計可能です。
自社のコストを抑えつつ、効率的な休日の勤怠管理を実現したい場合は、ぜひご活用ください。
法定休日と所定休日には、大きく以下の違いがあります。
法定休日と所定休日は、従業員からすると同じ「単なる休み」です。しかし、実際は「法的な付与義務の有無」「従業員が休日出勤した際に支払う割増賃金率」が異なります。また、休日出勤時に「振替休日or代休」のどちらを行うかによっても対応が変わります。
そのため企業の担当者は、必ず「法定休日・所定休日」の違いを押さえ、ミスなく従業員の休日を管理できるよう心がけてください。
| Q1.所定休日と法定休日の違いは? |
|---|
|
法定休日と所定休日の違いは以下の通りです。
|
| Q2.法定休日の具体的なルールは? |
|
法定休日では、以下いずれかの要件を満たすことが必要です。
|
| Q3.所定休日と法定休日では割増賃金率は違いますか? |
|
違います。それぞれの割増賃金率は以下の通りです。
|
| Q4.法定休日は土日のどっちで付与すればよいですか? |
|
土日のどちらに付与しても問題ありません。 |
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員10人まで永久無料の勤怠管理システム「フリーウェイタイムレコーダー」を提供しています。フリーウェイタイムレコーダーはクラウド型の勤怠管理システムです。ご興味があれば、ぜひ使ってみてください。