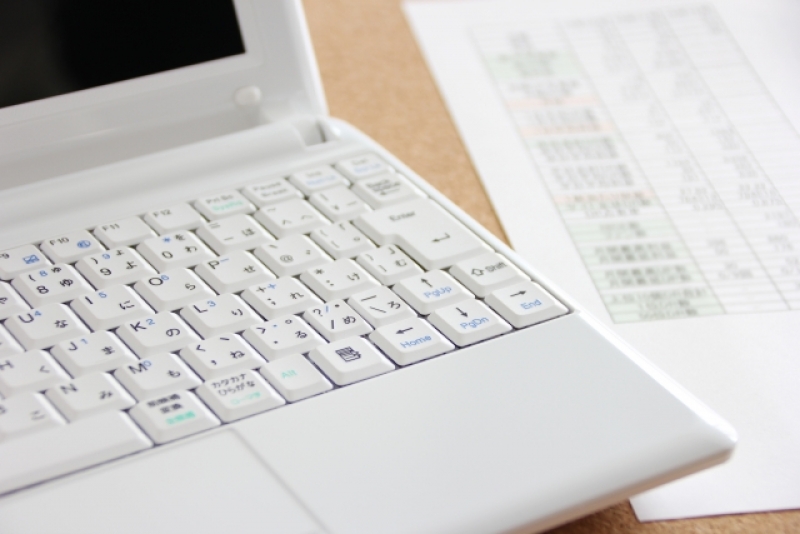
近年、労働時間管理の重要性が高まっています。働き方改革関連法の施行や、テレワークの普及により、企業の労働時間管理はより複雑化し、適切な対応が求められるようになりました。法令違反による罰則強化や労働問題の顕在化は、企業経営におけるリスク要因となっています。
本記事では、労働時間管理の基礎知識から具体的な実践方法、システム選定のポイントまで、企業担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
労働時間管理の基本は、「何を」管理するのかを正しく理解することから始まります。労働時間には主に3つの区分があり、これらを明確に把握することが法令遵守の第一歩です。
労働時間は、所定労働時間・法定労働時間・残業労働時間の3つにわけられます。
これらの時間区分を正確に理解し記録することが、適切な労働時間管理の基盤となります。

昨今の労働時間管理に関する法改正は、主に2つあります。
1つは、2019年4月に施行された働き方改革関連法です。「時間外労働の上限規制をはじめとした労働時間の見直し」「年次有給休暇の取得義務化」などが主な内容でした。
また、2023年4月にも労働基準法を中心とした労務関連の法改正が行われました。 内容としては、「月60時間以上の時間外労働の割増賃金率を、大企業・中小企業問わず一律50%へ」「男性の育児休業取得状況の公表義務化」などです。
どちらにも時間外労働に関する事項が盛り込まれており、重要なトピックであることがわかります。
タイムカードや紙の台帳による労働時間管理は、最も伝統的な方法であり、今でも小規模事業所を中心に利用されています。この方法には長所と短所があり、適切な状況で選択することが重要です。
タイムカード方式のメリットは、導入コストが低く、専門的なITスキルがなくても運用できる点です。特に従業員が少ない小規模事業所では、初期費用を抑えられるため選択肢として検討する価値があります。また、停電やシステム障害の影響を受けにくいという点も魅力です。
一方で、デメリットも存在します。まず、打刻データの集計や給与計算のための転記作業に時間がかかります。また、タイムカードの差し替えやごまかしが技術的に可能であるため、厳密な管理という観点も課題です。さらに、紛失や劣化のリスクもあり、法定保存期間である5年間の記録維持が難しいケースもあります。
効果的な運用例としては、小規模な事務所で、出退勤時刻を記入後に上長が確認サインする運用が挙げられます。また、月末に総務担当者がデータをExcelに転記して保管するという方法も一般的です。
ただし、従業員数が増えたり、複数拠点での管理が必要になったりした場合は、より効率的な方法への移行を検討すべきでしょう。
ExcelやGoogleスプレッドシートを活用した労働時間管理は、中小企業で広く採用されている方法です。この方法は、紙の台帳よりも一歩進んだデジタル管理を実現します。
この方法の最大のメリットは、初期投資を抑えながらも集計作業の効率化が図れる点です。関数やマクロを活用すれば、残業時間の自動計算や月間の集計作業を効率化できます。特にGoogleスプレッドシートでは、クラウド上でのリアルタイム共有や同時編集が可能なため、複数担当者での管理がスムーズです。
一方、デメリットとしては、フォーマットの作成や関数の設定に一定のスキルが必要な点があります。また、データ入力は基本的に手作業のため、入力ミスのリスクは残ります。さらに、従業員数が多い場合はファイルが肥大化し、動作が遅くなるという課題もあります。
効果的な運用例としては、あらかじめ計算式が組み込まれたテンプレートを活用する方法があります。たとえば、出退勤時刻を入力するだけで、所定内労働時間・残業時間・深夜労働時間を自動計算するスプレッドシートを作成し、部署ごとに管理する運用が効率的です。
また、Googleフォームと連携させ、従業員がスマートフォンから出退勤時刻を入力、その情報が自動的にスプレッドシートに反映される仕組みを構築している企業もあります。これにより、テレワーク環境下でも比較的容易に時間管理ができます。
勤怠管理システムは、労働時間管理を包括的に効率化するためのツールであり、クラウド型とオンプレミス型の2種類があります。この方法は、従業員数が多い企業や複雑な勤務形態を持つ企業に特に適しています。
クラウド型のメリットは、初期投資を抑えられることと、サーバー管理やバージョンアップの手間がかからない点です。インターネット環境があれば場所を問わず利用できるため、テレワークやリモートワークとの相性も良好です。また、定期的なアップデートにより、法改正への対応も比較的迅速に行われます。
一方、オンプレミス型は、自社のサーバーに設置するため、セキュリティ面での安心感があります。特に個人情報保護に厳格な企業や、インターネット環境が不安定な工場などの現場では重宝されます。また、カスタマイズ性が高く、既存の社内システムとの連携も柔軟に行える利点があります。
勤怠管理システムの主な機能としては、以下のようなものがあります:
効果的な運用例としては、工場のような固定拠点ではICカードリーダーを設置し、営業職などの外回りが多い従業員にはスマホアプリでの打刻を許可するといった、職種に応じた柔軟な運用が挙げられます。また、管理職には部下の残業状況が一目でわかるダッシュボード画面を提供し、労働時間の適正管理を促すような運用も効果的です。
システム導入の際には、自社の勤務体系や就業規則との整合性を十分に確認し、必要に応じてカスタマイズを検討することが重要です。
労働時間管理において最も頻繁に発生する問題が、打刻漏れや記録ミスです。この問題は単なるヒューマンエラーにとどまらず、複合的な原因があります。
打刻漏れが発生する主な原因は、従業員の意識不足と煩雑な打刻システムにあります。特に朝の混雑時や帰宅急ぎの退勤時には打刻を忘れるケースが多発します。また、客先訪問や外出業務が多い営業職などでは、事業所に戻って打刻する習慣が根付きにくいという背景もあります。
記録ミスについては、手作業による集計や転記が原因となることが多いです。紙のタイムカードからExcelへの転記作業や、複数システム間でのデータ移行時にミスが生じやすくなります。
打刻漏れや記録ミスを減らすためには、従業員教育だけでなく、使いやすい打刻システムの導入や、自動集計機能の活用が効果的です。
多くの企業で見られる問題が、労働時間管理の「属人化」です。
特に、Excelなどによる労働時間管理が行われている場合、担当者だけが複雑な関数やマクロを理解している状態となり、その担当者の不在時や退職時に管理が滞るリスクがあります。
こうした属人化から脱却するためには、クラウド型の勤怠管理システムの導入が有効です。システム化により、誰でも同じ基準で労働時間を管理でき、担当者交代時のリスクも軽減できます。
近年急速に普及したテレワークやフレックスタイム制は、働き方の多様性を促進する一方で、労働時間管理に新たな課題をもたらしています。
テレワーク環境下では、従業員の労働時間を直接目視できないため、「いつ働き始め、いつ終えたか」を客観的に把握することが困難になります。自宅やカフェなど場所を問わない勤務形態では、従来の打刻システムが機能しないケースも多いです。
また、フレックスタイム制では、コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)と、フレキシブルタイム(出退勤時刻を従業員が自由に決められる時間帯)の区別や、清算期間内の総労働時間管理が複雑になります。特に月をまたぐ清算期間を設定している場合、集計作業はさらに煩雑になります。
これらの柔軟な働き方に対応するためには、PCログオン・ログオフ時刻の記録やWEB打刻システムの活用、モバイルアプリでの打刻など、新しい時間管理の仕組みが必要です。労働基準法では、テレワーク下でも客観的な労働時間管理が求められているため、適切なツールの選定が重要となります。
勤怠管理システムを選ぶ際は、「機能と自社課題のマッチング」を重視しましょう。なぜなら、不適切なシステム選定が長期的には大きなコスト増につながるからです。
勤怠管理システムの導入費用は一般的に、初期費用と月額利用料(または保守料)で構成されています。初期費用を抑えすぎて機能が不十分なシステムを選ぶと、運用開始後に様々な問題が発生します。たとえば、テレワーク対応が不十分なシステムを導入した場合、別途ウェブ打刻ツールの追加導入が必要になったり、手作業での補完作業が発生したりするでしょう。
また、自社の課題解決に直結しないシステムを選ぶと、結局は使われなくなり、導入自体が無駄になるリスクもあります。例えば、最大の課題が「36協定の上限管理」であるにもかかわらず、コスト重視で最小限の打刻機能しか備わっていないシステムを選んでしまったとします。
残業時間の条件に対する警告機能などがなければ、結局担当者が毎月手作業によるチェックを続けることになります。
適切なシステム選定のためには、まず自社の課題を明確にすることが重要です。以下のような質問に答えることで、必要な機能が見えてきます:
これらの問いに対する答えをもとに、自社課題を解決できる機能を持つシステムを選定することが、長期的に見て最もコストパフォーマンスの高い選択となります。
勤怠管理システムを比較検討する際には、以下の5つのチェックポイントを重視することで、後悔のない選定が可能になります。

労働基準法や働き方改革関連法への対応状況は重要です。具体的には、36協定の上限管理機能、変形労働時間制への対応、みなし残業制の設定、勤務間インターバル管理機能などが備わっているかをチェックしましょう。また、法改正時のアップデート頻度や対応スピードも重要な判断材料です。
システムがいくら高機能でも、使いづらければ定着しません。特に打刻する従業員と管理者それぞれの視点で使いやすさを評価することが重要です。デモ環境での操作体験や、実際に使用している企業の評判を参考にしましょう。スマートフォン対応の場合は、アプリの操作性も確認が必要です。
自社の勤務体系や就業規則に合わせてシステムをカスタマイズできるかどうかは非常に重要です。特に、複雑なシフト体系や特殊な手当計算がある場合は、柔軟な設定が可能かを確認しましょう。また、将来的な事業拡大や組織変更にも対応できる拡張性も考慮すべきポイントです。
導入時のサポートだけでなく、運用開始後の問い合わせ対応や、トラブル発生時の迅速な解決が可能かどうかを確認します。電話サポートの受付時間や、オンラインマニュアルの充実度、定期的な研修機会の有無なども重要です。特に初めてシステムを導入する企業の場合、手厚いサポート体制は必須条件と言えるでしょう。
勤怠データは給与計算や人事評価など、他の業務システムとの連携が必要なケースが多いです。給与システムとのデータ連携機能や、人事システム・会計システムとの互換性があるかを確認しましょう。また、APIの公開状況や、CSVなどの汎用フォーマットでのデータ出力機能も確認ポイントです。
これらの5つのポイントをバランスよく評価し、自社の優先順位に沿って比較検討することで、最適なシステム選定が可能になります。ベンダー側の営業資料だけでなく、実際の操作感を体験できるトライアル期間の活用もおすすめです。
勤怠管理システムの導入を成功させるためには、段階的なアプローチが効果的です。以下に具体的な導入ステップを紹介します。
システム導入の目的と期待される効果を明確に伝えることから始めましょう。特に経営層には費用対効果を、現場の管理職には業務効率化のメリットを、従業員には使いやすさを強調することが重要です。
この段階では、以下のような準備が必要です:
特に重要なのは、「監視強化が目的ではない」ことを明確に伝え、従業員の不安を払拭することです。法令遵守や働き方改革の推進など、ポジティブな側面を強調しましょう。
全社導入の前に、特定の部署や拠点でのパイロット運用を行うことで、問題点を事前に洗い出せます。
試験運用の要点は以下の通りです:
この段階で発見された問題点や改善要望は、本導入前に解決しておくことが重要です。特に、既存の就業規則との不整合や、運用ルールの曖昧さなどが表面化することが多いので、しっかりと対応しましょう。
試験運用の結果を踏まえ、全社への展開を行います。この段階では以下の点に注意して進めてください:
特に重要なのは、移行期間中のダブルワーク(旧方式と新方式の並行運用)を最小限に抑えることです。明確な切り替え日を設定し、それに向けた準備を徹底することが成功の鍵となります。
導入後も定期的なフォローアップが重要です。以下のような取り組みを継続しましょう:
導入から3〜6ヶ月後に、当初の目的が達成できているかを評価することも忘れないでください。必要に応じて追加機能の検討や、運用ルールの見直しを行うことで、システムの有効活用が促進されます。
自社の労働時間管理体制を客観的に評価するためのチェックリストです。各項目について「はい」「いいえ」で回答し、「いいえ」の項目は優先的に改善に取り組みましょう。
このチェックリストを定期的(半年に1回程度)に実施し、自社の労働時間管理体制の強みと弱みを把握しましょう。特に「いいえ」の回答が多い領域については、優先的に改善計画を立てることをお勧めします。
適切な労働時間管理には、法的知識、現場の課題理解、適切なツール選定、運用ノウハウが必要です。
特に重要なのは、自社の実情に合わせた仕組みづくりと、継続的な改善サイクルの確立です。完璧な制度を一度に作り上げようとするのではなく、まずは現状の課題に対応する基本的な仕組みを整え、その後PDCAサイクルを回しながら改善していく姿勢が大切です。
労働時間管理の取り組みは、最終的には「働きやすい職場環境」の実現につながります。法令遵守はもちろん、従業員の健康と働きがいを大切にする企業文化の醸成を目指しましょう。
| Q1.労働時間管理の方法は何がある? |
|---|
|
労働時間管理の方法は、タイムカードや紙の台帳、ExcelやGoogleスプレッドシート、勤怠管理システム(クラウド型・オンプレミス)などがあります。 それぞれメリット、デメリットがあるので、詳しくは「労働時間管理の方法:選択肢と運用例」の章をご覧ください。 |
| Q2.勤怠管理システムの選び方は? |
|
勤怠管理システムを選ぶ際は、法令対応の充実度、使いやすさ、カスタマイズ性と拡張性などの基準があります。 他のポイントなども含めて、自社の優先順位に沿った比較検討をしましょう。 詳しくは「勤怠管理システムの選び方と導入ポイント」の章をご覧ください。 |