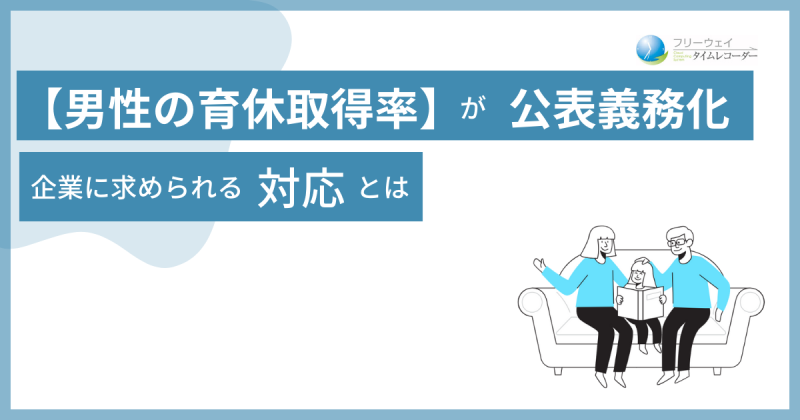
育児休業制度とは、育児・介護休業法で定められた制度のことです。1歳未満(最長で2歳)の子どもを養育する際に申請できます。
現在では男性の育休取得を促進するために、産後パパ育休(出生児育児休業)の創設や育休取得率の公表義務化など、幅広い施策が実行されています。企業には、育休を取得しやすい職場環境の整備や該当従業員への意向確認などが義務付けられているため、法律をチェックし「具体的に自社で何をやるべきか」を把握しておくことが必須です。
本記事では、育休の概要や男性の育休取得促進に向けて企業に義務付けられたポイントなどを紹介します。
目次
最初に、男女を含めて使える「育児休業制度」の全体像を解説します。
育児休業制度とは、育児・介護休業法で定められた「仕事と育児の両立を支援する制度」のことです。原則として1歳未満(最長で2歳)の子どもを養育する際に申請できます。育児休業を申請することで、従業員の「労務提供義務」は一定期間消滅します。
育児休業制度は育児・介護休業法に基づき制定されているため、仮に自社の就業規則に育児休業に関する規定がない場合も、従業員からの申請は拒否できません。
従業員が安心して育児に取り組めるよう整備された法律であるため、企業は必ず詳細を確認してください。
上記の育児・介護休業法は、2024年に大きく改正されています。対象となる子どもの範囲や企業への義務付け内容などが変化しているため、改めて変更点を確認してください。
以下の情報は、2025年1月時点でまとめたものです。
子の看護休暇の見直し(2025年4月1日〜施行予定)
|
| 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(2025年4月1日〜施行予定) 「小学校就学前の子ども」を養育する従業員であれば、所定外労働の制限(残業免除)を受けられるように変更 |
育児のためのテレワーク導入の努力義務化・短時間勤務の代替措置にテレワークを追加(2025年4月1日〜施行予定)
|
| 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大(2025年4月1日〜施行予定) 従業員数が300人を超える企業には、「育児休業等の取得状況の公表」を義務付け |
| 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務に(2025年10月1日〜施行予定) 企業に対し「3歳以上かつ小学校就学前の子どもを養育する従業員」に関して、柔軟な働き方の実現に向けた措置の実行を義務化 |
| 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務に(2025年10月1日〜施行予定) 「妊娠や出産の申出時」「子どもが3歳になる前」のタイミングで、企業は従業員に対し、仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取することを義務付け |
詳細は「厚生労働省|育児休業制度 特設サイト」にまとめられています。
また、この後の「男性の育休取得促進に向けて企業に義務付けられた内容」の章でも、男性の育休義務に関する部分を改めてまとめているため確認してください。
育児・介護休業法の中で、男性向けに創設されたものが「産後パパ育休(出生時育児休業)」です。
産後パパ育休とは、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として、2回に分割して取得できる育児休業のことです。分割取得する場合は、最初の申請時にまとめて申し出ることが必要です。最初に解説した1歳までの育児休業とは、別途で取得可能です。制度自体は2022年10月1日から施行されています。
育児休業を希望する人が多い「子どもの出産直後の時期(出生後8週間以内)」に男性が育児に専念できるよう、より柔軟で取得しやすい制度として創設されました。原則として「育児休業を取得する2週間前まで」に申請が必要です。
また、従来の育児休業制度では、原則として休業期間中に従業員は働けませんでした。しかし産後パパ育休の場合、労使間で労使協定を締結していれば、従業員が合意した範囲で休業中に仕事を行ってもらうこともできます。
このように、男性従業員の希望に合わせて、育児や仕事を柔軟に調節できるようになりました。
参照:厚生労働省|育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説 p.11
従業員がスムーズに育休を取得できるよう、企業には以下の措置の実施が義務付けられています。
男性が育休を取得しない理由として「業務の都合」「職場の雰囲気」などが挙げられることから、企業には育休を取得しやすい雇用環境の整備が義務付けられています。
実施が推奨されている具体的な措置は、以下の通りです。

厚生労働省「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」を基に自社作成
より育休を取得しやすい雰囲気を作るには、複数の施策を同時並行で進めることが大切です。
従業員本人あるいは配偶者が妊娠・出産を申し出た場合、企業は当該従業員へ以下の項目を周知したうえで「育休を取得するか」を確認してください。
従業員への周知や意向確認は「面談(オンライン含む)・書面・FAX・電子メール」のいずれかで行ってください。FAXや電子メール等については、従業員が希望した場合にのみ行います。
当然ですが、育休取得を控えるよう誘導する個別周知と意向確認は禁止です。必ず従業員本人の希望を最優先してください。
有期雇用労働者についても、育児・介護休業の取得要件が以下のように緩和されました。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| (1)1年以上継続して雇用されている (2)子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に、当該従業員との契約が満了しない |
(2)の要件のみを満たせば取得できる |
取得要件が緩和されたことで、雇用期間が1年未満の有期雇用労働者でも育児・介護休業を取得できます。
現在は働き方が多様化してきたことで、男女問わず無期・有期のどちらの雇用形態で働くことも当たり前になってきました。上記の緩和によって、そうした状況に柔軟に対応できるようになったといえます。
ただし、継続して雇用された期間が1年未満の場合、労使協定の締結により除外することも可能です。
2025年1月現在、従業員数が1,000人を超える企業には育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられています。
以下2点のうち、いずれかを公表する必要があります。
それぞれの割合の計算方法は、以下の通りです。

公表時は、自社サイトや厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」などへ掲載し、世間へ広く発信することを心がけてください。
また、公表日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後から「3ヶ月以内」を目安に公表してください。例えば、事業年度末(決算時期)が毎年3月の場合、初回は2025年6月末までに掲載することが必要です。
参照:厚生労働省|2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます
2025年4月1日からは、上記の公表義務が「従業員が300人超1,000人以下の企業」にまで拡大されます。雇用契約の形態を問わず、期間の定めなく雇用されている従業員が300人超1,000人以下であれば適用されるため、必ずチェックしてください。公表すべき内容や計算方法などは上記と同じです。
「男性向けの育休義務」に焦点を当てて解説しました。ここでは改めて、男女問わず育休取得を促すために行うべき措置について、簡単に紹介します。
| 短時間勤務等の措置 3歳に達するまでの子どもを養育している従業員が利用できる「短時間勤務の措置(1日原則6時間)」を義務付け |
| 子の看護休暇制度 小学校就学前までの子どもが「1人なら年5日」「2人以上なら年10日」を限度として、看護休暇を取得できる。時間単位での取得も可能 |
| 時間外労働の制限 小学校就学前までの子どもを養育する従業員が希望した場合、「1ヶ月24時間・1年150時間」を超える時間外労働を制限 |
| 転勤についての配慮 従業員を転勤させる際、育児の状況について配慮することを義務付け |
| 所定外労働(残業)の制限 3歳に達するまでの子どもを養育する従業員が希望した場合、所定外労働を制限 |
| 不利益取扱いの禁止 育児休業等の申出や取得を理由とする解雇、その他の不利益取扱いを禁止 |
| 深夜業の制限 小学校就学前までの子どもを養育する従業員が希望した場合、深夜業を制限 |
| 育児休業等に関するハラスメントの防止措置 上司や同僚による育児休業等の制度や措置の申出、利用に関するハラスメントを防止する措置を義務付け |
育休は、必要な従業員が必要なタイミングで利用できることが必須です。上記を参照して、性別に関係なく従業員がスムーズに育休を取得できる体制を整備してください。
男性の育児休業取得状況の公表義務化を含め、育休取得の促進に向けた制度の整備が進められている背景として「男性の育休取得率の低迷」が挙げられます。
以下が男女の育休取得率の推移を比較したグラフです。

画像引用:厚生労働省|令和5年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について p.3
上図からわかるように、男性の育休取得率は年々伸長傾向にあるものの、女性の育休取得率と比較すると、まだまだ改善が必要です。とくに男性が育休を取得できないと、必然的に女性ひとりに育児の負担が偏ります。
こうした育児の負担を解消し、男女両方が積極的に取り組めるよう、育休取得の促進に向けた雇用環境の整備が実施されています。
男性の育休取得を促進することで、企業は「法律で決められた義務を果たせる」というだけでなく、以下のメリットも受けられます。
育休取得を促すことで、従業員が育児をしやすい環境が整います。育児に時間を割けるようになれば、従業員は「子どもと触れ合える時間を作り成長を間近で実感できる」「空いた時間で自分のキャリアを見つめ直せる」といったメリットを受けられます。
従業員が上記のようなメリットを実感して組織への満足度や信頼度が高まり、仕事のモチベーションもアップすれば、最終的な定着率の改善まで実現可能です。人材が定着すれば、企業は人手不足で悩む必要もなくなります。
男性の育休取得を促進し実際の取得率まで向上すれば、対外的に「育児を応援している企業だ」「従業員のプライベートにも配慮している」というメッセージを発信できます。こうしたメッセージが浸透すれば、企業のイメージアップにつながり、消費者が自社製品やサービスを選ぶきっかけになるかもしれません。
さらに自社のイメージアップによって、採用活動で応募者数が増えることも期待できます。応募の母数が増えれば、優秀な人材を確保できる可能性も高まります。
上記のような「従業員の仕事へのモチベーションアップ」「優秀な人材の確保および定着の促進」を実現できれば、自然と企業の業務効率は高まり、最終的な生産性向上につながります。現場の従業員が自発的に「どうしたら効率化できるか」「成果を出して貢献するために何をやるべきか」などを考え行動してくれるというのは、企業からすると理想の状態です。
育休取得の促進に向けた環境整備には時間とコストがかかりますが、長期的な企業の売上アップにもつながるため、ぜひ取り組んでください。
男性が育児に参加できるようになれば、子育ての負担が女性に偏りません。子育ての負担が解消すれば、「出産したらもう一度働きたい」と希望する女性が企業に復帰しやすくなります。
とくに女性の中には、「育児をきっかけに職場を離れそのまま離職してしまう」といったパターンもあります。能力と意欲があるにも関わらず、一度ブランクが生じただけで働きにくくなるというのは、本人はもちろん企業にとっても機会損失です。
男女が平等に育児に時間を割けるようになれば、子育てがひと段落した後に希望のキャリアを再び歩みやすくなります。
企業が男性従業員の育休取得を促進する際は、以下のポイントを押さえてください。
従業員に育休を取得してもらうには、まず制度自体を知ってもらうことが必須です。
以下のような内容を中心に周知することで、必要なタイミングで従業員がスムーズに申請できる体制を整えてください。
周知の際は「社内研修を実施する」「独自の資料でわかりやすくまとめる」などを行うことがオススメです。
とくに育休中は、原則として給与が支払われないため、社会保険料や生活費といったお金に関する面が気になる従業員も多いはずです。そうした従業員の不安を解消するため、必要な情報を積極的に周知してください。
企業が男性向けの育休制度を整備しても、現場で運用されなければ意味は半減します。従業員が積極的に育休を活用できる風土を作り上げられるよう、以下のポイントを意識してください。
育休が正しく運用されれば、従業員が働きやすい職場環境が整備されるだけでなく、企業も法律で定められた義務を果たせます。
従業員が育休を使って休むと業務に支障をきたすため、企業は人員配置や割り振りなどの見直しを行う必要があります。
とはいえ、こうした業務内容の見直しは、育休が決まってからすぐ実行できるわけではなく、「部署間の擦り合わせ」「顧客への説明」などの準備が必要です。そのため、配偶者の妊娠がわかった段階で企業に知らせる仕組みを構築し、なるべく早めに社内で準備ができる体制を整備してください。早めに妊娠の事実を共有できれば、育休利用日から逆算し、前倒しで人員配置や業務の割り振り直しなどを実施できます。
具体的には「社内システムで育休を簡単に申請できる仕組みを導入する」「対象者へ自動で育休の案内が届くようなフローを作る」などがオススメです。
上記で解説したように、従業員が育休を取得し人員が減れば、少なからず業務に影響を与えます。そのため、従業員から配偶者の妊娠報告を受けた時点で、育休取得を見据えて早めに以下のような対応策を実行してください。
こうした企業の対応が早いほど、育休取得者も仕事のことを気にせず、心置きなく育児に専念できます。
育休取得を促進することで、企業は以下のように事業主向けの助成金や税制優遇などを活用できます。
各種制度を活用することで、手続きの手間を減らしたりコスト負担を軽減したりして、スムーズに育休を運用できます。厚生労働省の「仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方へ」では、上記を含め育休取得を促進したい企業へのサポート制度がまとまっているため、ぜひ確認してください。
男性従業員の育休取得を促進するために、産後パパ育休の創設や育休取得率の公表義務化など、さまざまな施策が行われています。2025年4月1日からは公表義務の対象企業の拡大が予定されており、従業員が育児と仕事をスムーズに両立できる環境を整備することは企業の急務です。
さらに育休取得を促すことで、企業は従業員のモチベーションアップや生産性向上などのメリットを受けられます。自社の成長を強化するためにも、今回の記事を参考に男性の育休義務について把握し、適切な対応策を実行できるよう準備を進めてください。
| Q1.男性の育休取得率の公表義務化とは何ですか? |
|---|
| 常時雇用する労働者が1,000人を超える企業(大企業)は、「男性の育児休業等の取得状況」あるいは「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」を年に1回公表することを義務付けられています。これは、男性の育休取得率の低迷を打破するために義務化されたものです。2025年4月1日からは、上記の公表義務が「従業員が300人超1,000人以下の企業」にまで拡大されます。 |
| Q2.男性の育休取得率が公表義務化されたことで、企業に求められる対応とは? |
企業には以下2つの対応が求められるようになりました。
|
| Q3.男性の育休取得は義務化されましたか? |
| いいえ、「男性の従業員は必ず育休を取得しなければいけない」という義務はありません。義務化されたのは、「企業は従業員の育休取得を促すための措置を実施する必要がある」というものです。従業員に何らかの義務が課されたわけではありません。 |
| Q4.男性の育休取得の義務化はいつからですか? |
| 2025年1月時点で、従業員に対し「育休を取得しなければいけない」という義務は課されていません。一方で企業に対しては、2025年4月1日から「育児休業取得状況の公表義務付け」などを含め、男性従業員の育休取得を促すための措置の実施が義務付けられています。 |
| Q5.企業は男性の育休を拒否できますか? |
| 企業は従業員からの育休申請を拒否できません。いつ従業員から育休を申請されても対応できるよう、企業は法律の内容を事前にチェックしてください。 |