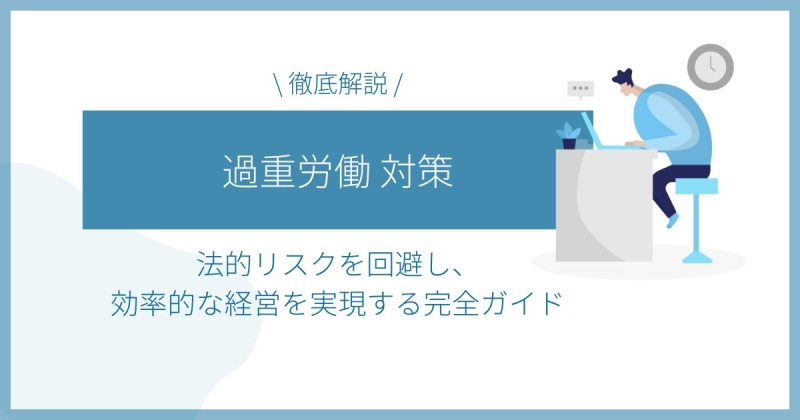
過重労働は従業員の健康を害し、企業に深刻な法的・経営リスクをもたらします。厚生労働省の最新統計によると、令和5年度の精神障害労災認定件数(支給決定件数)は883件と過去最多を記録。
働き方改革関連法の施行により、企業には適切な対策が求められています。この記事では、過重労働の定義から具体的な対策まで、中小企業が実践できる解決策を体系的に解説します。
過重労働対策の全体像を理解するには、まずその法的定義と実務上の判断基準を正確に把握することが不可欠です。これにより、自社の現状を客観的に評価し、適切な対策を講じるための土台を築くことができます。
「過重労働」とは、長時間の時間外労働や休日勤務が慢性的に重なり、従業員の心身に過度な負担がかかる「働きすぎ」の状態を指します。
厚生労働省の定義では、
が、過重労働であると判断されます。これらの数値は、過労死等の労災認定基準にも関連する重要な指標です。
一般的に「過労死ライン」と呼ばれるのは、以下の状態です。
が目安とされます。
これらの基準を超える労働は、脳・心臓疾患や精神障害の発症リスクを著しく高めることが示されています。企業が具体的な数値を認識することは、法令遵守をするだけでなく、従業員の生命と健康を守るという社会的責任を意識することにつながります。
過重労働と混同されがちな「長時間労働」は、その定義が異なります。
長時間労働:
過重労働:
長時間労働は心身のストレスを引き起こし、その結果として過重労働につながり得ます。長時間労働は過重労働の「原因」や「兆候」となりかねません。
この違いを明確に理解することは、企業が自社のリスクレベルを正確に把握し、適切な対策を講じるための前提知識となります。
概念の混同は、誤った対策や対策の遅れを生む可能性があります。正確な知識の提供は企業の信頼獲得に直結しています。
企業は、過重労働を防止するために複数の法的義務を負っています。労働基準法では、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働を行わせる場合、労働組合または労働者の過半数代表者との間で36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
2019年4月に施行された働き方改革関連法により、36協定における時間外労働の上限は厳格化されました。原則として月45時間・年360時間以内であり、臨時的・特別な事情がある場合の特別条項を締結したとしても、以下の上限を遵守する必要があります。

企業は、従業員一人ひとりの労働時間を客観的な方法で正確に把握し、記録する義務があります。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、タイムカード、ICカード、PC使用時間記録などが原則的な方法として示されています。
過重労働に関する法的義務は多岐にわたり、特に36協定の上限規制は複数の時間軸と回数制限が絡むため、非常に複雑です。複雑な要件を手作業やExcelで正確に管理し続けることは、人的ミスを誘発しやすく、労務担当者の大きな負担となります。
また、年次有給休暇の確実な取得も義務化されており、2019年改正労働基準法により、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対しては、毎年5日間の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられています。
過重労働を放置することは、従業員の健康を害するだけでなく、企業に多大な法的リスク、経済的損失、そしてブランドイメージの毀損という深刻な影響をもたらします。
これらの悪影響を深く理解することは、対策の緊急性を認識し、経営戦略として過重労働対策に取り組む上で不可欠です。
過重労働は、従業員の心身に甚大な影響を及ぼします。身体的な健康障害としては、過度なストレスや身体的負荷が原因で、脳出血、くも膜下出血、心筋梗塞、狭心症などの脳・心臓疾患を発症するリスクが高まります。
厚生労働省の「令和5年度の過労死等の労災補償状況」によると、脳・心臓疾患による労災補償請求件数は1,023件に上り、前年度より220件増加しています。
精神的な健康障害としては、不規則な生活、仕事や人間関係による強いストレス・プレッシャーが、うつ病、不眠、不安障害などの精神障害を引き起こすことがあります。
上記の調査では、精神障害による労災補償請求件数は3,575件で、前年度より892件増加しており、特に「1ヶ月に80時間以上の時間外労働」が主な原因として挙げられています。
精神障害の労災請求件数が脳・心臓疾患の3倍以上であるという事実は、現代の労働環境における精神的負荷の増加を示してます。最悪の場合、これらの健康障害が原因で過労死(心筋梗塞や脳卒中など)や過労自殺につながるリスクも存在します。
過労死防止対策推進法では、過労死を「業務における過重な身体的若しくは精神的な負荷による疾患を原因とする死亡(自殺による死亡を含む)又は当該負荷による重篤な疾患」と定義しています。
過重労働は、企業に直接的な法的リスクをもたらします。
労働基準法に違反して過重労働をさせた場合
これらの直接的な金銭的・刑事的罰則に加え、労働基準法に違反し、労働基準監督署から是正勧告を受けた場合、厚生労働省によって企業名が公表されることがあります。
これは企業イメージを著しく毀損し、社会的信用を失墜させ、人材採用や取引先との関係にも悪影響を及ぼします。
罰金は一時的なコストですが、企業イメージの毀損や採用難は、企業の持続的な成長を阻む深刻な問題です。SNS時代においては、一度失墜した企業イメージの回復は困難です。
過重労働対策は、単に「罰則を避ける」という守りの姿勢だけでなく、「企業ブランドを守り、高める」という攻めの経営戦略の一部と捉えるべきです。
過重労働が常態化する企業では、従業員の心身の状態が不安定になり、仕事へのモチベーションや集中力が低下します。
すると、ミスが発生しやすくなり、生産性も著しく低下。睡眠不足や疲労の蓄積は、精神的なゆとりを奪い、創造性や判断力も奪います。
従業員の不満が蓄積すると、結果として離職率が高まり、優秀な人材の流出を招きます。企業が「ブラック企業」というイメージをもたれることで、新規採用が困難になってしまいます。
人材は企業の最も重要な資産であり、その確保と定着が企業の競争力を左右します。過重労働は、企業の資産を損なう直接的な要因となってしまうのです。
過重労働対策は、単なるコスト削減やリスク回避に留まらず、企業の持続的な成長と競争力強化のための「人材戦略」の一環として位置づけられるものです。「働きやすい職場環境」は、優秀な人材を引きつけ、定着させるための差別化要因となるでしょう。
過重労働は、単一の原因で発生するものではなく、複数の要因が複雑に絡み合って引き起こされます。自社の過重労働問題の根本原因を特定し、効果的な対策を立てるためには、これらの要因を深く理解することが重要です。
厚生労働省の調査*によると、時間外労働が発生する主な原因の43%が「業務量が多い」、31%が「人員が不足している」とされています。
企業が利益を優先し必要最低限の人材しか雇っていない、あるいは少子高齢化による労働力人口の減少が、従業員一人あたりの業務量を増加させている現状があります。
*厚生労働省「平成27年度過労死等に関する実態把握のための社会面の調査研究事業」
特定の時期に業務が集中する繁忙期と閑散期の差が大きい業種では、人員配置の難しさが過重労働を助長します。また、業務が特定の「仕事ができる人」や「残業を断れない人」に集中する傾向も、業務過多の一因となります。
組織内の業務配分が不均衡であること、および従業員の性格や立場が過重労働に影響を与えるという、より深い問題を示しています。属人化は、その人が休むと業務が滞るだけでなく、その人に過度な負担をかけることになります。
無駄な会議の常態化、慣例的な資料作成、部門間の情報共有不足、役割の曖昧さなど、非効率な業務プロセスは、不要な残業を常態化させる根本原因となります。
明確な指示や目的がないまま「前例踏襲」や「なんとなく」で行われており、従業員が「なぜこれをするのか」疑問を感じつつも行っていることも。
タイムカードの手作業集計やExcelでの複雑な勤怠管理では、集計ミスがあったり、法改正対応に遅れたり、担当者に大きな負担がかかります。
非効率な業務プロセスは単に時間がかかるだけでなく、従業員のモチベーション低下や「やらされ感」を助長し、結果的に生産性も低下します。
管理職が部下の業務量や健康状態を把握していないと、適切な人員配置や業務配分のバランスが悪くなります。
一方で、管理職自身が実務を抱え込む「プレイングマネージャー」となり、過重労働を招くことも 。管理職が自身の業務に追われ、部下の状況を十分に把握できていないケースは少なくありません。
「残業が美徳」とされる古い企業風土や、長時間働く従業員が評価される文化も改善が必要です。従業員が定時で帰りにくい雰囲気があるなら要注意。
単に「業務が多い」という物理的な問題だけでなく、組織の価値観が従業員自身に「過重労働しなくてはいけない」と心理的なプレッシャーを与えてしまいます。
経営トップからの強いメッセージ発信と、組織全体、特に管理職層の意識改革が過重労働対策には不可欠です。
企業風土は、過重労働対策の成否を左右する最も根深い要因の一つです。システム導入や制度変更だけでは不十分で、経営層からの改革する意思とそれを現場に浸透させる管理職のリーダーシップが必要です。
過重労働対策は、一朝一夕に完了するものではありません。体系的なアプローチと継続的な改善が求められます。ここでは、企業が実践すべき5つのステップを具体的に解説します。
過重労働対策の第一歩であり、法遵守のベースとなるのが、従業員一人ひとりの実労働時間を正確に把握することです。タイムカード、ICカード、PC等の電子計算機の使用時間の記録など、客観的な方法で労働時間を把握することが重要です。
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、自己申告制の場合でも、実態調査を行い、記録と乖離がある場合は修正することが求められています。
労働時間を記録するだけでなく、その記録が「客観的」かつ「正確」であること、そして「リアルタイム」に状況を把握することで過重労働を防げます。
自動データ化や残業アラート機能の活用します。これにより、過重労働のリスクが高い従業員を早期に特定し、未然に健康被害や法的リスクを防ぐことが可能となります。
従業員の健康状態を早期に把握し、健康障害を未然に防ぐための重要な制度が、医師による面接指導制度です。
労働安全衛生法に基づき、時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり80時間を超える長時間労働者に対しては、医師による面接指導を申し出る機会を与えることが義務付けられています。
面接指導の結果に基づき、就業場所や業務内容の変更、労働時間の短縮、深夜業務の回数削減など、就業上の措置を講じる必要があります。
産業医や保健師といった専門家との連携を通じて、従業員の健康リスクを早期に発見し、適切な対応を行う体制を整備することが重要です。特に、健康診断結果やストレスチェック結果を加味した対応が求められます。
参照:厚生労働省『長時間労働者への医師による面接指導制度について』
面接指導は、単に義務を果たすだけでなく、従業員の健康状態が悪化する前に「早期に介入」し、より深刻な事態(労災認定、過労死)を「予防」するための大切な機会となります。
企業は労働時間データだけでなく、健康診断やストレスチェックの結果も統合的に管理し、リスクの高い従業員に対して積極的にアプローチする視点をもつことが求められます。
従業員一人あたりの業務負担を軽減し、根本的な労働時間削減を実現するためには、業務効率化が不可欠です。業務の棚卸しを行い、不要な業務を廃止して従業員一人あたりの業務量を削減します。
会議時間の短縮、資料作成の簡素化、メールの効率的な利用など、日々の業務改善につながる具体的な工夫を行うことで「属人化」も防げます。
ワークフローシステム、グループウェアなどのデジタルツールの導入による自動化・効率化に取り組んでみるのもいいでしょう。人的リソースをより付加価値の高い業務に集中させることを促します。
業務効率化は単に残業を減らすだけでなく、従業員がより創造的で戦略的な業務に時間を費やせるようになります。それが、従業員のエンゲージメント向上にもなります。
従業員の健康をケアし、過重労働による健康リスクを防ぐために、健康管理体制の構築が必要です。ストレスチェック制度の実施、定期健康診断の徹底は、従業員の健康状態を把握し、健康障害を未然に防ぐために大切なことです。
労働安全衛生法に基づき設置が義務付けられている衛生委員会や安全委員会(一部義務なし)を積極的に活用してみましょう。
厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」も過重労働対策の情報を豊富に提供しています。
<安全委員会>
主に「労働者の危険防止のための基本的対策」など、安全に関する事項を調査・審議し、必要に応じて意見を述べて対策を実行します。委員は、事業者側と労働者代表(過半数)から構成され、議長は事業の統括者などが担います。
<衛生委員会>
常時50人以上の労働者を有する事業場に設置が義務付けられています。労働者の健康保持・増進のための環境整備や制度運用に関して調査・審議を行い、事業者に提言する役割を担います。構成・運営方式は安全委員会と同様です。
過重労働対策は、一度実施すれば終わりではありません。労働時間、残業時間、有給休暇取得率、従業員の健康状態(ストレスチェック結果など)、離職率などのデータを継続的にモニタリングし、効果の測定を継続していきます。
測定結果に基づき、課題を特定し、改善策を立案・実施し、その効果を再度評価するというPDCAサイクルを回すことが不可欠です。勤怠管理システムが提供するデータ分析機能は、客観的なデータに基づいて改善するために役立ちます。
経営層は感覚的な判断ではなく、データに基づいた経営判断を行うことができます。過重労働対策は、単なる労務管理の範疇を超えて企業の「データドリブン経営」を推進する重要な要素となります。
過重労働対策を効果的かつ効率的に進める上で、勤怠管理システムや人事労務ソフトの活用はまさに「切り札」となります。手作業やExcel管理の限界を乗り越え、企業の労務管理を効率化できます。
従業員の出退勤時刻を客観的に記録し、残業時間や休日労働時間をリアルタイムで正確に把握することが可能。これにより、過重労働のリスクが高い従業員を早期に特定し、アラートを出すことで、未然に健康被害や法的リスクを防ぐことできます。
労働基準法や働き方改革関連法の改正にシステムが自動で対応し、36協定の上限規制や年次有給休暇の取得義務化などを確実に遵守できます。企業は常に最新の法令に準拠した管理が可能となり、法的なリスクを大幅に軽減できます。
勤怠データの自動集計、給与計算システムとの連携、各種申請(残業申請、有給申請など)の電子化などにより、人事・労務担当者の手作業による負担を劇的に軽減。より戦略的な業務や従業員ケアに集中できます。
蓄積された勤怠データを分析し、部署ごとの残業傾向、業務の偏り、生産性などを可視化。経営層は感覚的な判断ではなく、客観的なデータに基づき、人員配置の最適化や業務改善策を立てることができます。企業の生産性向上と持続的な成長につながります。
システムは、単なるバックオフィスツールではなく、企業の「健康経営」と「データドリブン経営」を実現する戦略的な武器となり得るのです。
人事労務ソフトは、勤怠管理だけでなく、給与計算、人事評価、社会保険手続き、年末調整など、人事労務業務全般を統合的に管理できるソリューションです。
これらの機能が連携することで、従業員情報の分散を防ぎ、労務管理を効率的に行えます。例えば、勤怠データが給与計算に自動連携されることで、残業代の計算ミスを防げます。
統合的な管理は、過重労働対策をより包括的に支援します。例えば、人事評価システムと連携することで、長時間労働ではなく生産性や成果を評価する制度への移行をサポートし、企業風土の改革を後押しできます。
具体的な成功事例は、システム導入や対策による効果を実感し、自社での実現可能性を検討する上で大きなヒントとなります。ここでは、実際に過重労働対策で成果を上げた企業の事例を紹介します。
株式会社サティライズ:クラウド型業務支援システムの導入で専門家と連携
中部地区を拠点とするIT企業である株式会社サティライズは、企業と社会保険労務士事務所をつなぐクラウド型業務支援システムを導入。これにより、勤怠・給与・手続き依頼などで社労士事務所と連携し、バックオフィス業務の効率化を行いました。
特に、勤怠管理システムの導入により、新たに導入した3ヶ月単位のフレックスタイム制の管理も容易になり、結果として時間外労働の削減につながっています。
単に勤怠管理システムを導入しただけでなく、他の労務業務や外部の専門家との連携までスムーズにするという、システム連携による相乗効果を得られた事例です。
引用:厚生労働省『働き方特設サイト CASE STUDY』株式会社サティライズ
株式会社クラフト:システム導入+企業風土変革で有給休暇取得率約98%
看板、サインの企画・製作・施工を行う株式会社クラフトは、システム導入だけでなく、企業文化や環境整備に積極的に取り組むことで成果を出しました。同社は「年次有給休暇全員100%取得」をトップメッセージとして掲げ、時間単位年休制度や有給休暇管理表の掲示などで取得を促進。
また、業務日報による「仕事の見える化」と、社長自身が相談窓口となるなど「社内コミュニケーションの強化」にも取り組みました。
2020年度には年次有給休暇取得率97.71%、残業時間は2014年度比で50%削減(1人あたり約12時間/月)を達成。紙ベースだった業務日報もデジタル化し、個々人の労務費を算出・共有することで、従業員のやりがいにもつながっています。
制度を導入するだけでなく、経営層の強いコミットメントと、それを支える「意識改革」、業務の「見える化」が一体となって効果を発揮した事例です。
引用:厚生労働省『働き方特設サイト CASE STUDY』株式会社クラフト
信州ビバレッジ株式会社:週休3日のシフト制に。年収を下げずに残業を大幅減
キリンビバレッジグループの信州ビバレッジ株式会社は、固定観念にとらわれない多様な働き方を導入することで、過重労働対策に成功しました。同社は製造部門で週休3日となるシフト体制を導入し、残業の大幅削減を実現。年間約400時間あった残業時間が、年間約60時間と大幅に削減されました。
改革は労使間の1年間の協議を経て実現し、残業代削減分は基本給引き上げや賞与で補填され、従業員の年収が下がらない賃金体系が構築されました。事務部門でもスーパーフレックスタイム制(コアタイム撤廃)を導入し、より柔軟な働き方を推進しています。
休憩室の整備やトレーニングルーム設置など、従業員の健康維持とワークライフバランス向上にも積極的に取り組んでいます。
引用:厚生労働省『働き方特設サイト CASE STUDY』信州ビバレッジ株式会社
労働基準監督署の監査(臨検)は、企業の労働環境が法令に準拠しているかを確認するために行われます。監査時の適切な対応と事前の準備は、法的リスクを回避し、企業の信頼性を維持するために不可欠です。
<労働基準監督署とは?>
厚生労働省の出先機関で、全国に321か所あります。労働基準法などの法律に基づき、労働条件、職場の安全や健康、労災保険などに関する相談対応や指導、監督します。労働基準法に関する手続きを行う部署(監督課)、職場の安全衛生を指導する部署(安全衛生課)、労災保険を扱う部署(労災課)、その他事務を行う部署(業務課)などで構成されています。
労働基準監督署の監査では、主に労働時間管理、賃金支払い、安全衛生管理、雇用契約、就業規則などが確認されます。特に、労働時間の適正な把握が重視され、タイムカードやPCログと申告時間の乖離がないか、36協定の範囲内で労働が行われているかなどが厳しくチェックされます。
監査時には質問への誠実な回答と、求められた書類の速やかな提出が重要です。不備があった場合は、是正勧告や指導を受けることになります。手作業やExcel管理では、これらの書類を迅速かつ正確に準備することが困難で、監査対応が大きな負担となります。
勤怠管理システムや人事労務ソフトは、必要なデータを一元管理し、いつでも出力可能な状態にすることで、監査対応の「効率性」を高め、提出するデータの信頼性を高くします。
労働基準監督署の監査で事前に提出を求められる主な書類は以下の通りです。これらの書類は、日頃から正確に作成し、適切に保管・管理しておくことが大切です。
<主な必要書類>
紙ベースの管理では、紛失、破損、保管スペースの問題などがあり、監査時に必要な情報を迅速に探し出すのが非常に大変です。
勤怠管理システムや人事労務ソフトを導入することで、これらの書類の多くをシステム上で自動生成・管理することが可能になり、監査時の準備負担を大幅に軽減できます。管理データの「ペーパーレス化」と「データの一元化」は、コスト削減だけでなく、情報管理の「正確性」「検索性」「セキュリティ」を高めます。労務管理体制を「監査に強い」ものに変えられる利点もあります。
過重労働対策の現状を把握し、改善点を特定することは、次の具体的なアクションを明確にする上で極めて重要です。以下のチェックリストを活用し、対策状況を診断してみましょう。
企業が法的に求められる最低限の対策を講じているかを確認します。

法的要件だけでなく、実務上の運用が効果的に行われ、従業員の健康と生産性向上に貢献しているかを確認します。

上記のチェックリストで「いいえ」と回答した項目や、「不十分」と感じた項目を特定します。
法的義務に関わる項目(法的要件充足度チェック)で「いいえ」があった場合は、最優先で改善に取り組む必要があります。
次に、従業員の健康や生産性に直結する項目(実務運用レベルチェック)で課題がある場合は、中長期的な視点で改善計画を立てましょう。
この自己診断を通じて自社の「弱点」を明確に認識し、その弱点を補うための具体的な解決策を考えることができます。
過重労働は、従業員の健康、企業の法的遵守、持続的な成長に直結する、現代企業にとって避けられない課題です。過重労働、無用な長時間労働を未然に防ぐための方策は、業務を属人化させず、効率化するためにも有効なものが多いため、取り組むに値するものです。
勤怠管理システムや人事労務ソフトの導入は、労働時間の正確な把握、法改正への迅速な対応、業務効率の大幅な改善などができる効率的な手段です。働きやすい職場環境を構築し、従業員のエンゲージメントを高め、結果として企業価値を向上させるための第一歩となります。
| Q1. 勤怠管理システムを初めて導入する企業が注意すべきポイントは? |
|---|
|
自社の規模や業種に合ったシステムを選ぶことが重要です。初期費用だけでなく、月額費用やサポート体制も比較検討しましょう。また、従業員への説明会や操作研修を必ず実施し、システム導入の目的とメリットを理解してもらうことがスムーズな移行につながります。 |
| Q2.業務効率化を進める上で、管理職が注意すべきことは? |
|
管理職は、部下の業務量や進捗状況を常に把握し、偏りがないか、無理がないかを確認する必要があります。また、無駄な業務や慣例的な作業がないかを見直し、積極的に改善提案を促すことも大切です。自ら、長時間労働を美徳とするような古い価値観を改め、メリハリのある働き方をするのが大切です。 |
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員10人まで永久無料の勤怠管理システム「フリーウェイタイムレコーダー」を提供しています。フリーウェイタイムレコーダーはクラウド型の勤怠管理システムです。ご興味があれば、ぜひ使ってみてください。