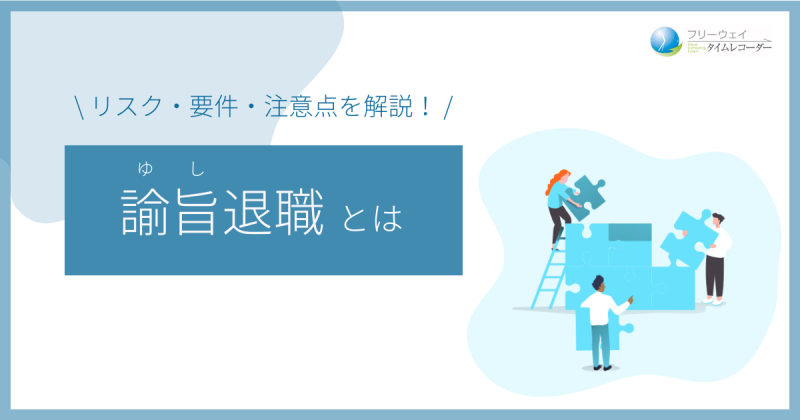
「諭旨退職(ゆしたいしょく)」とは、企業が従業員に対して行う懲戒処分の1つで、企業からの退職勧告に対し、従業員自身が退職届を提出することによって実質的に解雇を行う処分です。
諭旨退職は最も重い処分である「懲戒解雇」に次ぐ処分とされ、一般的には、従業員の能力・適性・成績などに問題がある場合や、問題行動・トラブル・不祥事などがあった場合などに適用されます。
形式上は退職届による自主的な退職に見えますが、実質的には従業員に選択権のない解雇処分であるため、のちのちのトラブルにならないよう、客観的・合理的な判断やプロセスが重要です。
この記事では、諭旨退職の概要や適用時の注意点、対応方法について解説します。もしもの時に備えて、人事担当者または経営者にぜひ読んでいただきたい内容です。
「諭旨(ゆし)」とは「趣旨や理由をさとし告げること」を意味します(デジタル大辞泉)。
その言葉の通り、諭旨退職(ゆしたいしょく)とは、企業が従業員に対して退職を促し、従業員自身が退職届を提出することによって成立する懲戒処分の1つです。企業側から退職を勧告する形をとりますが、形式上は「自己都合退職」として扱われます。
懲戒処分にはいくつか種類があり、一般的には重い順番に「懲戒解雇」「諭旨処分」「降格」「出勤停止」「減給」「けん責」「戒告」とされ、諭旨退職は2つ目に重い処分となっています。

懲戒解雇は企業が従業員に科す最も重い懲戒処分であり、労働者保護が重視される日本では容易に行われるものではありません。適用には、従業員に由来する重大な不祥事や、勤務態度の著しい不良、会社に損害を与える行為、犯罪行為などの重大な事情が必要です。
諭旨退職は、懲戒解雇に次いで重い処分であり、こちらも同様に、特別な事情によって行われます。
諭旨退職と類似する用語として、諭旨解雇(ゆしかいこ)があります。ここでは、これらの言葉を整理しておきます。
諭旨退職も諭旨解雇も明確な定義のある法律用語ではないため、各企業の就業規則によって定義や運用が異なります。実際には、両者を明確に区別している企業は少なく、基本的にはほぼ同じ意味だと考えて問題ありません。
厳密には、諭旨解雇は従業員に退職届を提出させたうえで「解雇」として処理するのに対し、諭旨退職は従業員に退職届を提出させたうえで「自己都合退職」として処理する手続きと位置付けられることもあります。
この記事では、用語を「諭旨退職」に統一して解説を行います。
「退職」とは企業の一方的な意思表示ではなく、労働契約関係を終了させる手続き全般を指します。
退職は、本人の事情で従業員が申し出る「自己都合退職」と、企業の事情で退職させる「会社都合退職」に大きく分かれます。これらの違いによって、失業保険の給付条件(待機期間や給付日数など)の受給条件に違いが生まれますが、諭旨退職は、「自己都合退職」として処理されるのが一般的です。

なお、「解雇」とは企業が一方的に労働契約を終了させる処分であり、原則として「会社都合」として扱われます。
自己都合退職の種類
混同されやすい「諭旨退職」と「懲戒解雇」について、あらためて整理しておきましょう。
懲戒解雇は、重大な不正行為や就業規則違反などを理由に企業が一方的に労働契約を終了させる処分であり、基本的には、退職金や解雇予告、解雇予告手当の支給はありません。解雇通知を受けたら即日解雇となるうえ、離職票の離職事由にも懲戒解雇であることが明記される、厳しい処分です。
一方、諭旨解雇は本来なら懲戒解雇に相当する理由があっても、過去の功績や貢献度などを考慮して処分を緩やかにする措置です。形式上も「自己都合退職」として扱われる場合が多く、離職票にもそのように記載されます。
なお、諭旨解雇とするか懲戒解雇とするかは、労働基準法で明確に定められておらず、それぞれの企業の就業規則や労働契約の内容にそって決定されます。
諭旨退職は、懲戒解雇に該当するほど重大ではないものの、単なる減給や出勤停止では不十分と判断される場合に適用されます。具体的な例としては以下のようなケースが考えられます。
諭旨退職は懲戒解雇よりも企業側のリスクは少ないとされますが、従業員の問題行動があったことを認める点では同様です。
諭旨退職を実施する際には、客観的・合理的な判断とプロセスが重要です。理由に対して処分が過重であったり、脅迫や精神的な追い込みにより、従業員が意思に反して退職届を提出していたりということが明らかになれば、企業に複数のリスクが生じます。具体的には以下の3つです。
処分が不適切であった場合、従業員から不当解雇訴訟や損害賠償請求訴訟が提起される可能性があります。
訴訟に発展すれば、企業は多大な時間・コスト・労力を要するだけでなく、敗訴するリスクも抱えることになります。
企業の諭旨退職処分が無効と判断された例
事件の概要
東京メトロの従業員が職務外で痴漢行為を行ったとされ、諭旨解雇処分を受けた。これに対し、従業員が処分の無効を訴えた。
裁判所の判断
裁判所は、着衣の上から触っただけで「処罰の対象となり得る行為の中でも、悪質性の比較的低い行為である」と指摘した。
さらに、事件がマスコミなどで報道されなかったことや、駅係員に懲戒処分歴がなかったことを踏まえ、企業が鉄道事業者として痴漢行為撲滅への取り組みを積極的に行っていた点を考慮しても、諭旨解雇処分は過重であるとして無効と判断した。
参考:全基連
法的リスクを恐れるあまり必要な処分を躊躇することは本末転倒ですが、処分の理由が処分の程度に対して相当であるかについては、弁護士等の第三者の意見も仰ぎながら慎重に判断すべきと言えます。
処分の対象となった従業員が、諭旨退職に不服があっても個人での対応が困難であると判断した場合、労働組合が代理となって企業に団体交渉を申し入れるケースがあります。
このような状況への対応を誤ると、他の従業員からの信頼を損ない、職場全体の士気や人材流出など、組織運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
諭旨処分が公になると、企業イメージの悪化を招くリスクがあります。
処分理由によっては、コンプライアンス体制や内部統制の不備が指摘されることもあるでしょう。また、適切なプロセスで処分が行われていなかった場合には、さらに批判が強まりイメージ悪化が進行し、消費者や株主、従業員、取引企業、採用応募者などからの信頼を失う恐れもあります。
諭旨退職は法律用語ではないため、企業によってその運用方法は異なります。ただし、過去の判例などから、労使間のトラブルを避けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があると考えられています。
諭旨処分に求められる3つの要件
このうち、3つ目の「懲戒権・解雇権の濫用」は具体的なイメージがわかりにくいと感じる方も多いでしょう。
企業には、職場の秩序を保つために従業員に懲戒処分を与えたり、解雇したりする権限(懲戒権・解雇権)があります。ただし、これらの権限は無制限ではなく、就業規則に則った運用が求められ、企業内の秩序維持という目的を越えて濫用されることがあってはなりません。
もし行われた処分が「懲戒権の濫用」や「解雇権の濫用」に該当していると判断された場合、たとえ明記・周知された就業規則に基づいていたとしても、裁判で無効とされる可能性があります。
どのような場合に懲戒権・解雇権の適用が相当であると認められるかはケースバイケースであり一概に言うことは難しいですが、以下に具体例を挙げます。
諭旨退職で争った例
| 諭旨退職が認められたケース |
|
|---|---|
| 諭旨退職が認められなかったケース |
前章で説明したとおり、諭旨退職を円滑に実施するためには「あらかじめ就業規則上の定めがあること」「就業規則が従業員に対して周知されていること」「懲戒権や解雇権の濫用に該当しないこと」の3つの要件を満たしていることが重要です。
これらを踏まえ、企業が従業員に諭旨退職を実施する具体的な手順は、以下の通りです。

まず、就業規則に以下の事項が明記されていることを確認してください。
また、就業規則が従業員に周知されていることも併せて確認しましょう。これらの記載がない場合や、周知が不十分な場合、諭旨退職を行うための法的要件を満たさず、後に処分の有効性が否定される可能性があります。
諭旨退職を正しく行うためには、従業員の問題点を裏付ける証拠が必要です。よく使われる資料には、以下があります。
具体的な証拠が不足しているにもかかわらず諭旨退職の処分を行うと、トラブルに発展した場合に企業に不利に働く可能性があります。
処分の前に、諭旨退職の対象となる従業員の意見を聞く場を設けます。
対象となった従業員が自由に弁明できる環境を確保し、面談を行いましょう。従業員の弁明内容については面談記録を作成し、保存します。
具体的な証拠と該当の従業員の意見を踏まえ、再度、就業規則の規定に照らし合わせ諭旨退職が適切か判断します。
この際、以下の点も確認します。
諭旨退職の理由や、処分に至った経緯を第三者にも詳しく説明できることがポイントです。
検討の結果、諭旨退職が妥当と判断した場合は、懲戒処分通知書を交付して、従業員に諭旨退職を通達しましょう。
懲戒処分通知書には以下の内容を明記します。
従業員の納得が得られれば、退職手続きを実行します。
基礎的なものになりますが、退社手続きについては「社員の退社手続きマニュアル|退社前から退社後までの手順とポイント」にも詳しくまとめていますので、不安な方は合わせてご覧ください。
諭旨退職は懲戒解職と比べて軽いとはいえ、従業員の経歴や転職活動に影響を及ぼす可能性のある懲戒処分です。諭旨退職の合意プロセスや条件交渉において想定される従業員からの主な反論や要求は以下の3つです。
対策すべき従業員の反応
これまでに解説したように、諭旨退職が有効と判断されるためには明確な要件が存在します。就業規則にあらかじめ記載されていること、その規則が従業員に周知されていること、そして処分理由が合理的かつ客観的に妥当であることです。
これらの要件を満たし、適切な手続きを踏んでいれば、処分の無効や損害賠償請求に対しても、法的リスクは低減されるでしょう。
ただし、退職金については各企業の制度によって取り扱いが異なるため、一概には言えません。就業規則に諭旨退職における退職金の規定を明確に記載し、満額支給するかどうかなども含めて、あらかじめルールを明確にしておくことが重要です。
注意すべき点として、諭旨退職であることだけを理由に、退職金を減額・不支給とすることはできません。過去の判例において退職金減額が認められているのは、それまでの勤続の功を覆すほどの著しい問題行動があった場合に限られます。この法的解釈を踏まえて、退職金の取り扱いを検討しましょう。
諭旨退職は労働法上で明確に定義された制度ではなく、企業の就業規則や社会慣行として運用されている処分方法です。そのため、以下のような法的な注意点があります。
諭旨退職を実施するためには、あらかじめ就業規則に諭旨退職に関する規定を明確に設けておく必要があります。就業規則に規定がない場合、労働者が諭旨退職を拒否すれば、企業側は懲戒解雇か、もしくは処分の軽減を選択せざるを得なくなります。
諭旨退職は、形式上は従業員の自己都合退職となるため、本人の同意が前提となります。従業員が諭旨退職を拒否した場合、企業は懲戒解雇に切り替えるか、より軽い処分に変更するかを判断する必要があります。
同意のないまま処分を行うと、不当解雇と見なされるおそれがあるため慎重な対応が求められます。
どのような懲戒処分も、社会通念上相当と認められる範囲内でなければなりません(労働契約法第15条)。処分が過重であると判断されれば、諭旨退職が裁判で無効となる可能性があります。
諭旨退職を適切に実行するためには、以下の3つのポイントに特に注意が必要です。
諭旨退職の適用にあたっては、処分対象者の過去の貢献や反省の様子などから、情状酌量の余地を総合的に検討します。
多くの企業では諭旨退職の前提となる就業規則に「情状によって処分を加重または軽減する」といった文言を記載しています。
従業員が問題行動やトラブルを起こしていたとしても、その背景に健康上の問題などの特別な事情がある場合には、情状酌量の対象となることがあります。
諭旨退職は、適用する理由を従業員に対して明確に説明する必要があります。就業規則や労働契約書に明記されている事項に沿って、書面と口頭の両方で従業員に伝えることが重要です。
諭旨退職は、懲戒解雇に相当する事由に対して処分を軽減したものであるため、相応の重大な理由が必要です。
諭旨退職は、後に退職処分した従業員が訴訟を起こすなど法的トラブルに発展する可能性があることを念頭に置く必要があります。
企業が従業員の将来を考慮して懲戒処分ではなく諭旨退職を選択したとしても、従業員が納得できないと感じる場合もあります。
その場合、裁判での復職の要求や不当解雇による損害賠償を要求されることもあるでしょう。過去の判例では、判断基準の曖昧さや解雇の手続きに不備があったとして、解雇が無効とされた事例もあります。自社のみでの対応に不安がある場合は、事前に弁護士等の専門家に相談し、法的にも適切な対応ができる状態にしておくと良いでしょう。
ここまでで諭旨退職の全体像を説明してきました。ここからは諭旨退職処分の実施過程で実務担当者が直面しやすい具体的な疑問点について解説します。
諭旨退職処分であっても、従業員は退職日または解雇日までは、有給休暇を取得する権利があります。
そのため、諭旨処分に応じて従業員が退職届を出して退職した場合は、その退職日までは有給休暇の申請があれば、企業はこれを認める法的義務があります。
ただし、即日解雇の場合は当日に雇用契約が終了するため、有給休暇の消化はできません。この場合、企業は30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。また、法的義務ではありませんが、未消化の有給休暇分を買い取る(有給休暇相当分の賃金を支払う)企業もあります。
「雇用保険被保険者離職証明書」は、退職が決まった従業員が失業給付の手続きをするため離職票を請求できるようにする書類です。
3枚綴りの複写式となっており、1枚目が事業主控え、2枚目がハローワーク提出用、3枚目は退職者に渡す「離職票-2」です。
離職票-1と離職票-2


引用:厚生労働省「ハローワークインターネットサービス - 雇用保険の具体的な手続き」
これらの書類はWebサイト上でのダウンロードができません。書類をハローワークの窓口で受け取って記載・提出するか、電子申請(e-Gov)で提出することになります。
基本的には企業の担当者が必要事項を記載しますが、下記項目は従業員に記載を依頼します。
| 離職票-1 |
|
|---|---|
| 離職票-2 |
|
離職票には事実に基づいて記載することが基本です。諭旨退職は制度上、自己都合退職として扱われるため、離職理由欄には「労働者の個人的な事情により離職」、具体的事情記載欄は「自己都合(諭旨退職)」と明記した上で、従業員に署名を依頼してください。
諭旨退職とは、企業が従業員に対して行う懲戒処分の1つで、企業からの退職勧告に対し、従業員自身が退職届を提出することによって実質的に解雇を行う処分です。
諭旨退職は特別な事情があるときに行われる処分であり、適用にあたってはあらかじめ就業規則への記載や周知、また処分理由の合理性や客観性も必要です。適切な手続きが行われない場合、訴訟などに発展することも考えられます。
企業としては、諭旨退職を検討する段階から以下の実践的なステップを踏むことをお勧めします。まず、就業規則の内容を専門家と共に確認し、必要に応じて諭旨退職に関する規定を明確化しましょう。次に、問題行動が発生した際には、その都度詳細な記録を残し、証拠を適切に保管することが重要です。そして何より、従業員との対話の機会を十分に設け、説明責任を果たすプロセスを徹底することが、後のトラブル防止に直結します。
自社のみの対応で不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しながら、のちのちのトラブルにならないように慎重に手続きを行いましょう。諭旨退職は単なる退職手続きではなく、企業の信頼性や労使関係にも影響を与える重要な意思決定であることを常に念頭に置いて対応することが大切です。
| Q1.諭旨退職とは? |
|---|
| 諭旨退職(ゆしたいしょく)とは、企業が従業員に対して行う懲戒処分の1つで、企業からの退職勧告に対し、従業員自身が退職届を提出することによって実質的に解雇を行う処分です。 懲戒処分の中でも、懲戒解雇の次に重い処分となります。 詳しくは「諭旨退職とは、懲戒処分のうち自己都合扱いになる退職」の章をご覧ください。 |
| Q2.諭旨退職を行う手順は? |
| 諭旨退職を行う際は、諭旨退職に関する規定が就業規則に盛り込まれているか、社内の周知が十分であったかを確認したうえで、対象従業員が本当に処分に値するかを十分に検討する必要があります。 諭旨退職が円滑に行われるためには「あらかじめ就業規則上の定めがあること」「就業規則が従業員に対して周知されていること」「『懲戒権の濫用』と『解雇権の濫用』に該当していないこと」の3つの要件を満たしていなければなりません。 詳しくは「諭旨退職を行う手順」の章をご覧ください。 |
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員10人まで永久無料の勤怠管理システム「フリーウェイタイムレコーダー」を提供しています。フリーウェイタイムレコーダーはクラウド型の勤怠管理システムです。ご興味があれば、ぜひ使ってみてください。