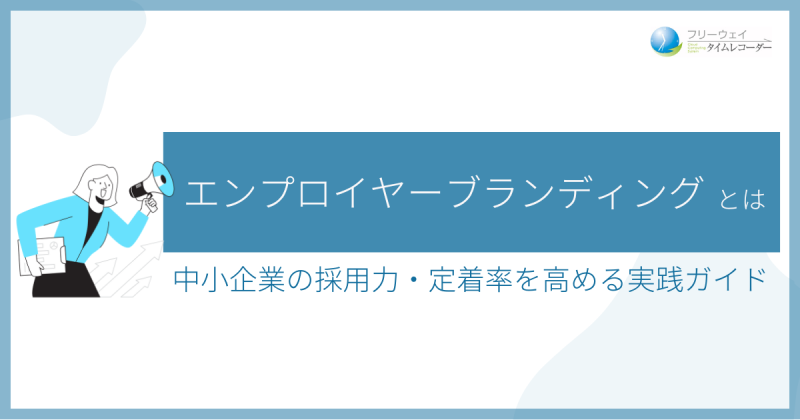
近年、多くの企業が人材確保に苦戦しています。少子高齢化による労働人口の減少、働き方の多様化、転職市場の活性化などを背景に、特に中小企業にとって優秀な人材の採用と定着は大きな経営課題となっています。
このような状況下で注目されているのが、企業のブランディング戦略の1つである「エンプロイヤーブランディング」です。本記事では、エンプロイヤーブランディングの基本概念から、中小企業が実践できる具体的な戦略まで、採用力と従業員定着率の向上につながる実践的な解説をします。
まず、エンプロイヤーブランディングについて基本的な定義について説明します。
エンプロイヤーブランディングとは、一般的に、企業が「雇用者(エンプロイヤー)」として持つブランドを戦略的に構築・強化する活動を指します。より具体的には「求職者や従業員に対して『働きたい会社』『働き続けたい会社』としての価値を高め、発信していく取り組み」と言えるでしょう。
一般社団法人エンプロイヤー・ブランディング協会では、エンプロイヤーブランドを以下の3つの要素で構成されている「働く価値」と位置付けています。
引用:一般社団法人エンプロイヤー・ブランディング協会『働く場の価値を創造し、伝える』
重要なのは、単なる採用広報やPRではなく、企業文化や価値観、働き方、人材育成など、組織の本質的な部分を基盤としたブランディングであるという点です。つまり、「見せかけ」ではなく「実態」に基づいたブランディングが求められます。単にことばとして「エンプロイヤーブランディング」をしても、それが見せかけのものでは意味がありません。口コミサイトなどを活用すれば、実情がわかるためです。
昨今の労働市場を取り巻く環境の変化により、エンプロイヤーブランディングの重要性は高まっています。
例えば、少子高齢化による労働人口の減少による企業間の人材獲得競争激化がそれに当たります。
また、働き方や働く人の価値観が多様化し、企業側の選ばれる努力も必要となってきました。特に若い世代を中心に、給与だけでなく福利厚生や職場の雰囲気、リモートワークの可否などを重視する風潮が広まっており、やりがいや成長機会などと合わせて、企業選びのポイントが多様化しています。
こうした背景から、企業が提供する働きやすさ、キャリアの多様性や成長機会、企業文化を従業員や求職者に伝えるエンプロイヤーブランディングは、人材確保と定着のために重要な戦略となっています。
エンプロイヤーブランディングと混同されやすい概念として、「インナーブランディング」や「採用ブランディング」があります。
インナーブランディングは、企業内部の従業員に対して企業理念や価値観を浸透させ、帰属意識やモチベーションを高める活動です。
また、採用ブランディングは、主に採用活動のための企業ブランディングを指し、求職者に対して「良い就職先」としてのイメージを構築する活動です。
つまり、両者はエンプロイヤーブランディングの一種であり、対象者を絞って実行されるものになります。
エンプロイヤーブランディングには、以下のようなメリットがあります。
まず、採用力の向上やそれに伴う採用コストの削減といった、採用面でのメリットが挙げられます。
企業文化や人材育成制度など、強固なエンプロイヤーブランドを持つ企業は、採用市場での競争力が高まります。具体的には以下のような効果が期待できます。
社内においては、従業員のエンゲージメント向上が見込め、それに付随したメリットがいくつかあります。
エンゲージメントとは、従業員の企業に対するやりがいや信頼、貢献志向などを指し、エンゲージメント向上は働きがいに転じえます。
また、働きやすさや価値観への共感により、離職率が低下し、人材定着率の向上達成も見込めるかもしれません。
企業に合った人材の採用、従業員のパフォーマンスや定着率向上は、企業の業績にも影響を及ぼします。
厚生労働省の令和元年版「労働経済の分析」からは、ワーク・エンゲージメントスコアが高いほど生産性が向上する傾向があるとわかっています。
このことから、従業員に対する自社ブランディングによるエンゲージメント向上が、企業にとって高い影響力をもつことがわかります。

引用:厚生労働省『令和元年版 労働経済の分析 – 人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について – 』
エンプロイヤーブランディングを効果的に構築するためには、以下の3つの柱に取り組むことが重要です。
エンプロイヤーブランディングの第一歩は、自社の魅力や価値を客観的に分析し、明確化することです。ここでは、以下のような要素を分析・整理します。
企業が目指す方向性や存在意義は、人材を惹きつける重要な要素です。「なぜこの企業が存在するのか」「何を実現しようとしているのか」という本質的な問いに対する答えを明確にしましょう。
具体的な方法としては、経営陣へのインタビューや創業ストーリーの整理などがあります。創業の想いや企業が大切にしている価値観を言語化することで、共感を呼ぶメッセージを作ることができます。
企業文化は、組織の個性や特徴を表す重要な要素です。自社らしさとは何か、他社と何が違うのかを明確にしましょう。
具体的な方法として、以下のようなアプローチがあります。
具体的な働き方や人事制度も、自社の魅力を構成する要素です。以下のような点を整理しましょう。
SWOT分析などを用いて、自社の強みと弱みを客観的に分析しましょう。強みを活かし、弱みを改善することで、より魅力的な職場環境を作ることができます。
また、退職者インタビューや従業員満足度調査の結果も、改善点を見つけるための重要な情報源となります。
このような内部分析を通じて、「自社ならではの魅力」を明確にし、それを言語化することが重要です。ただし、この過程では「ありたい姿」ではなく「ありのままの姿」を把握することを大切にしてください。実態とかけ離れたブランディングをすると、口コミサイトなどを通じて実態がわかってしまうため、かえって不信感を招くリスクがあります。
エンプロイヤーブランディングを効果的に行うためには、ターゲットとなる人材像を明確にし、競合との差別化ポイントを把握することも重要です。
「どのような人材に来てほしいのか」を具体的に定義しましょう。以下のような観点から整理できます。
例えば、「責任感があり、新しいことに挑戦する意欲が高く、チームでの協力を大切にする人材」といった形で具体化します。
ターゲット設定は「誰にでも来てほしい」という曖昧なものではなく、自社の価値観や文化に合う人材像を明確にすることが大切です。それによって、より効果的なメッセージングが可能になります。
採用市場での競合を分析し、自社の位置づけを理解しましょう。競合は必ずしも同業他社だけでなく、同じ人材層にアプローチしている企業も含まれます。
以下のような点を調査・分析します。
これにより、市場での自社のポジショニングや差別化ポイントを明確にすることができます。
内部分析と競合分析を踏まえ、自社の差別化ポイント(EVP:Employer Value Proposition)を特定します。EVPとは「なぜこの会社で働くべきか」を表す価値提案です。
例えば以下のような差別化ポイントが考えられます。
差別化ポイントは、単なるキャッチフレーズではなく、実際の企業文化や制度に裏付けられたものであることが重要です。また、ターゲットとなる人材にとって魅力的なものであることも大切です。
内部分析と外部分析を踏まえ、一貫性のあるメッセージとコミュニケーション戦略を構築します。
自社の魅力や差別化ポイントを踏まえ、核となるメッセージを作成します。このメッセージは以下の要素を含むと効果的です。
例えば「地域の健康を支える企業として、従業員一人ひとりが専門性を活かしながら成長できる環境を提供します」といったメッセージです。
エンプロイヤーブランディングで最も重要なのは、内部(従業員)と外部(求職者)に対して一貫したメッセージを発信することです。内部と外部で異なるメッセージを発信すると、入社後のギャップから早期離職や不満につながるリスクがあります。
例えば、「働きやすさ」をアピールするなら、実際に働きやすい制度や文化が社内に存在していなければなりません。「成長機会が豊富」と謳うなら、実際に研修制度やキャリアパスが整備されている必要があります。
構築したメッセージは、様々なチャネルを通じて発信します。主なチャネルとしては以下があります。
特に中小企業の場合、大規模な広告展開は難しいため、既存従業員を通じた発信や地域でのプレゼンス向上など、コストを抑えながら効果的なアプローチを選ぶことが重要です。
この章では、エンプロイヤーブランディングの導入ステップとして、より実践的な内容を解説します。
まずは自社の現状を客観的に把握し、どのような課題をエンプロイヤーブランディングによって解決したいのかを明確にします。
たとえば採用に関する課題を解決したいのであれば、社内のニーズを調査したり、人事と連携することで課題が見えてくるかもしれません。
また、従業員のエンゲージメントや人材定着率といった社内の問題であれば、まず従業員アンケートや面談などを通じて、職場環境や働きがい、経営陣との距離感などを可視化し、改善すべき点を見つけます。
これにより、エンプロイヤーブランディングの方向性を正しく定めることができます。
次に、自社が採用・定着させたいターゲット人材像を定めます。スキルや経験だけでなく、価値観や働き方の志向といった"カルチャーフィット"も重視することが重要です。明確なターゲット像があることで、採用施策やブランディング施策の一貫性が生まれ、メッセージの精度も高まります。
EVP(Employer Value Proposition)とは、「自社で働く魅力」を言語化したもので、エンプロイヤーブランディングの核となる要素です。給与や福利厚生だけでなく、成長機会、働きがい、企業理念との共感といった無形の価値も含めて、自社独自の魅力を整理・言語化します。社内外の調査をもとに策定するのが望ましいでしょう。
EVPを策定した後は、従業員全体にその価値観を浸透させることが不可欠です。具体的には、評価制度や研修プログラム、人事制度の見直しなどを通じて、EVPと組織運営が一貫したものになるよう体制を整えます。従業員が共感し、行動に移せるような内部コミュニケーションも重要です。
社内での土台が整ったら、いよいよ外部への発信を行います。採用サイトやSNS、求人票など、あらゆる接点でEVPを反映させ、ターゲット人材に響くメッセージを届けましょう。現場従業員の声を活用するなど、リアルで共感性のあるコンテンツを意識することがポイントです。
導入後は、応募者数や定着率、従業員満足度などの指標をもとに効果を測定します。結果を分析し、必要に応じてEVPや施策内容を見直していくことで、ブランドとしての魅力を持続的に高めていくことが可能です。エンプロイヤーブランディングは一度で完成するものではなく、継続的な改善が鍵となります。
エンプロイヤーブランディングは、単なる採用広報ではなく、「働きたい・働き続けたい」と思ってもらえる企業になるための戦略的な取り組みです。少子高齢化や価値観の多様化が進む中、企業にとっては、自社の魅力を正しく伝え、共感してくれる人材と出会うための重要な手段となります。
自社の価値を言語化し、社内外へ一貫して発信することで、採用力と定着率を高めるだけでなく、企業文化の醸成や業績向上にもつながります。まずは現状を見つめ直し、小さな一歩から取り組んでいきましょう。
| Q1.エンプロイヤーブランディングとは? |
|---|
| エンプロイヤーブランディングとは、企業が「雇用者(エンプロイヤー)」として持つブランドを戦略的に構築・強化する活動を指します。 単なる広報やPR活動ではなく、実態に基づいたブランディング戦略である点に注意してください。 詳しくは「エンプロイヤーブランディングの基本概念と重要性」の章をご覧ください。 |
| Q2.エンプロイヤーブランディングのメリットは? |
| エンプロイヤーブランディングを導入することで、採用活動における満足度向上やコストの削減、また従業員のエンゲージメント向上による人材定着率改善や企業パフォーマンスの向上が期待できます。 詳しくは「エンプロイヤーブランディングのメリット」の章をご覧ください。 |