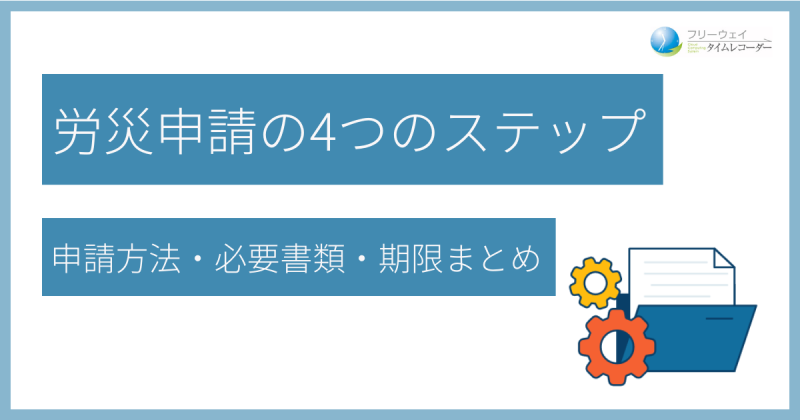
業務中の事故やストレスなどを原因として従業員が怪我を負ったり疾病を患ったりした場合、企業は労災申請を行い、正しい補償を受けられるよう手続きする義務があります。労災申請は補償内容ごとに手続き方法が異なるため、基本の流れと一緒に確認しておくことが必須です。本記事では、基本的な労災申請方法や補償内容ごとの必要書類、注意点などを解説します。
従業員からの労災申請を受ける際は、まず「申請内容が労災の対象であるか?」をチェックしてください。労災の対象であることを確認した後、労働基準監督署長宛てに申請を行います。
具体的な労災の対象は、以下の3種類です。
|
業務災害 業務を理由とする「従業員の負傷・疾病・障害・死亡」を指します。従業員が労災保険の適用事業場に雇用されており、企業の指示下にある状態で業務を原因とした災害が発生した場合に認定されます。就業時間外であっても、「明らかに業務が原因で疾病にかかった」などの場合は労災認定が可能です。 |
|
複数業務要因災害 従業員が「雇用主の異なる複数事業所で勤務している」という場合、その複数事業所でのストレスや労働時間などを総合的に考慮して、労災であるかを決定します。「1つの事業所のみでの負荷が疾病の原因」などと判断された場合は、業務災害が適用されます。 |
|
通勤災害 従業員が通勤時に被った傷病などをもとに判断します。「自宅とオフィスへの移動」など、合理的な理由を持ち適切な経路で通勤していれば、通勤災害に該当します。 |
より具体的な労災認定の基準については、福井労働局の「労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)」をご確認ください。
上記の「業務災害・複数業務要因災害・通勤災害」のいずれかに該当し労災認定された場合は、以下の4ステップで労災申請を実施してください。
上記はあくまでも基本の流れです。具体的な申請方法は補償内容ごとで異なるため、「労災ごとの具体的な「補償内容・申請手続き」を確認しよう」の章で確認してください。
労災が発生したら、まずは従業員に医療機関を受診してもらってください。然るべき医療機関で診断を受けることで、「労災であるか?」を正しく認定できるだけでなく、申請後も専門家の知見をもとに適切な治療を実施できます。
また、以下のうち、どちらの医療機関を受診したかに応じて治療費の支払い有無が異なるため、必ず確認し従業員へ違いを正しく説明できるようにしてください。
それぞれについて、簡単に解説します。
労災病院・労災保険指定医療機関で受診する場合、労災保険から直接医療費が支払われるため、従業員は窓口負担なしで診察や治療を受けられます。従業員には、医療機関の窓口で「労災である旨」を伝えて受診するように伝えてください。
該当の医療機関は「厚生労働省|労災保険指定医療機関検索」のサイトで検索できます。
労災病院・労災保険指定医療機関以外で受診する場合、従業員が一時的に治療費の「全額」を窓口で立て替える必要があります。健康保険が適用されないため、「高額であっても一旦全額負担しなければならない」という旨を必ず従業員へ伝えてください。
後日、労働基準監督署に申請すると立て替えた治療費が全額支給されます。支給の申請時は病院の領収書やレシートが必要になるため、必ず保管するよう伝えてください。
労災の申請書類は、以下のように具体的な「補償の種類」によって変わります。
| 労災補償の種類 | 必要書類 | 提出先 |
|---|---|---|
| 療養(補償)等給付 |
|
(病院や薬局などを経由して)所轄労働基準監督署長 |
|
所轄労働基準監督署長 | |
| 休業(補償)等給付 |
|
|
| 障害(補償)等給付 |
|
|
| 遺族(補償)等給付 |
|
|
| 葬祭料等(葬祭給付) |
|
|
| 介護(補償)等給付 | 介護補償給付・複数事業労働者介護給付・介護給付支給請求書(16号の2の2) | |
| 二次健康診断等給付 | 二次健康診断等給付請求書(16号の10の2) | (病院または診療所を経由して)所轄労働局長 |
各必要書類については「厚生労働省|主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」よりダウンロードできます。申請書類は、原則として「従業員自身」に労働基準監督署へ提出してもらってください。しかし、従業員が自力で提出できない場合、企業が代理で提出することも可能です。
給付申請内容に基づいて、労働基準監督署による以下のような調査が行われます。
必要に応じて従業員本人や企業への聞き取り調査が実施されるため、労災が起きた状況を正確に把握しておくことを心がけてください。
労働基準監督署の調査結果を受けて、労災の支給の有無が決まります。
給付が認められた場合、以下のいずれかが実施されます。
調査の結果として不支給だった場合、労働保険審査官への審査請求が可能です。ただし「労災保険給付の決定があったと知った日の翌日」から起算して3ヶ月を経過した場合、審査請求はできません。
上記の労災保険審査官の決定にも不服がある場合、労働保険審査会への再審査請求ができます。ただし「労災保険審査官の決定書送付日の翌日」から起算して2ヶ月を経過した場合、再審査請求はできません。
労災申請の流れは、基本的に上記のステップを踏んでください。ただし、あくまでも上記は基本の流れです。詳細な補償内容や申請手続きは労災の種類ごとに異なるため、必ず事前に確認してください。
ここでは、補償内容と申請手続きの概要をまとめました。
| 労災補償の種類 | 補償内容の概要 | 詳細な申請手続きの説明 |
|---|---|---|
| 療養(補償)等給付 |
|
療養(補償)等給付の請求手続 |
| 休業(補償)等給付 | 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額を給付 | 休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続 |
| 障害(補償)等給付 |
|
障害(補償)等給付の請求手続 |
| 遺族(補償)等給付 |
|
遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)の請求手続 |
| 葬祭料等(葬祭給付) | 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額を給付 | 遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)の請求手続 |
| 傷病(補償)等給付 | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金を給付 | 休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続 |
| 介護(補償)等給付 | (常時介護の場合)17万7,950円を上限として、介護費用の支出額を給付 | 介護(補償)等給付の請求手続 |
| 二次健康診断等給付 | 二次健康診断および特定保健指導の給付 | 二次健康診断等給付の請求手続 |
合わせて、以下のページも参照してください。
ここまでの解説を踏まえ、労災申請時に企業がチェックすべきポイントは以下の3点です。
労災申請は、原則として従業員本人が行います。ただし、「事故の影響で申請が困難」「手続きが複雑で正しく申請できない」といったこともあります。そのため企業は、従業員がスムーズに申請できるようサポートしてください。
補償内容にもよりますが、おおよその目安期間は以下の通りです。
労災申請の手続き期限は、以下のように補償内容ごとで異なります。
| 補償内容の種類 | 申請期限 |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 療養費用を支出した日の翌日から2年 |
| 休業(補償)等給付 | 賃金を受けない日の翌日から2年 |
| 遺族(補償)等年金 | 労災によって従業員が亡くなった日の翌日から5年 |
| 遺族(補償)等一時金 | 労災によって従業員が亡くなった日の翌日から5年 |
| 葬祭料等(葬祭給付) | 労災によって従業員が亡くなった日の翌日から2年 |
| 傷病(補償)等年金 | 申請期限は無し |
| 障害(補償)等給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |
| 介護(補償)等給付 | 介護を受けた月の翌月1日から2年 |
| 二次健康診断等給付金 | 一次健康診断の受診日から3ヶ月以内 |
参照:厚生労働省|7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。
最後に、労災申請時における企業の注意点を確認してください。
前提として、企業は従業員からの労災申請を拒否できません。労災申請は従業員を守るための大切な手続きであるため、労災によって怪我や疾病が発生したら、必ず申請を受け入れてください。
万が一、「手続きが面倒なので従業員からの申請を放置した」といった行為をした場合、労働安全衛生法第120条に基づき50万以下の罰金が科されます。
参照:神奈川労働局|「労災かくし」は犯罪です【労災補償課・労働保険徴収課】
従業員からの申請受付拒否だけでなく、明確な悪意を持って労働基準監督署へ偽装報告した場合も罰則対象です。偽装内容の例としては、以下が挙げられます。
企業には「従業員の労災申請手続き」をサポートする義務があります。労働者災害補償保険法の第23条でも、以下のように明記されています。
保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
引用:e-GOV法令検索
労災申請は、補償の種類ごとで必要書類が異なります。そのため、日頃から労災申請業務に関わっていない従業員が、1人で申請を終わらせることは困難です。とくに、深刻な怪我や精神障害を患った場合、サポートなしで手続きを完了させることはできません。
期限内にスムーズに手続きを終えられるよう、企業は必ず従業員の労災申請をサポートしてください。
雇用契約を結んでいる場合は、正社員や契約社員、アルバイト、パート、日雇いなどの雇用形態に関わらず、全従業員が労災申請の対象です。
派遣契約の場合は、派遣元および派遣先企業の両方が労働基準監督署長へ報告しなければなりません。
参照:
愛媛労働局|労災保険の適用者について
厚生労働省|派遣労働者にかかる労働者死傷病報告の提出について
労災は、以下の申請期限を経過すると手続きできません。
| 補償内容の種類 | 申請期限 |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 療養費用を支出した日の翌日から2年 |
| 休業(補償)等給付 | 賃金を受けない日の翌日から2年 |
| 遺族(補償)等年金 | 労災によって従業員が亡くなった日の翌日から5年 |
| 遺族(補償)等一時金 | 労災によって従業員が亡くなった日の翌日から5年 |
| 葬祭料等(葬祭給付) | 労災によって従業員が亡くなった日の翌日から2年 |
| 傷病(補償)等年金 | 申請期限は無し |
| 障害(補償)等給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |
| 介護(補償)等給付 | 介護を受けた月の翌月1日から2年 |
| 二次健康診断等給付金 | 一次健康診断の受診日から3ヶ月以内 |
期限を守って申請できるよう、企業は従業員へ呼びかけてください。
健康保険は本来、労災と無関係な怪我や疾病などの診察および治療を行う際に使うものです。そのため、労災対象の治療に健康保険を使ってしまうと、治療費を全額自己負担しなければなりません。
そのため、労災の可能性がある場合、企業は従業員へ「健康保険を使わないように」と呼びかけてください。
もし誤って健康保険を使ってしまった場合、必ず労災保険へ切り替えてください。具体的な切り替え手続きは「厚生労働省|お仕事でのケガ等には、労災保険!」で解説しています。
役員や経営者は従業員に該当しないため、労災保険を利用できません。しかし、一定要件を満たしていれば、特別加入制度を利用したうえで労災申請ができます。
最後に改めて、基本的な労災申請方法を確認してください。
原則として、労災申請は従業員本人が行います。しかし、補償内容ごとで必要書類が変わるため、すべてを1人で終わらせることは難しいかもしれません。
そのため、企業は従業員がスムーズに申請できるよう、必ず手続きをサポートしてください。とくに労災申請には期限があるため、従業員が確実に給付を受けられるようサポートすることが必須です。
| Q1.労災申請の具体的なやり方は? |
|---|
|
労災申請の基本的な方法は以下の通りです。
具体的な申請方法は補償内容ごとで異なるため、「労災ごとの具体的な「補償内容・申請手続き」を確認しよう」の章で確認してください。 |
| Q2.労災申請の手続きは誰が行うの? |
|
原則として従業員本人が行います。企業には、従業員がスムーズに申請できるよう、サポートすることが義務付けられています。 |
| Q3.労災申請の手続き期限は? |
|
申請期限は以下の通りです。
|
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員10人まで永久無料の勤怠管理システム「フリーウェイタイムレコーダー」を提供しています。フリーウェイタイムレコーダーはクラウド型の勤怠管理システムです。ご興味があれば、ぜひ使ってみてください。