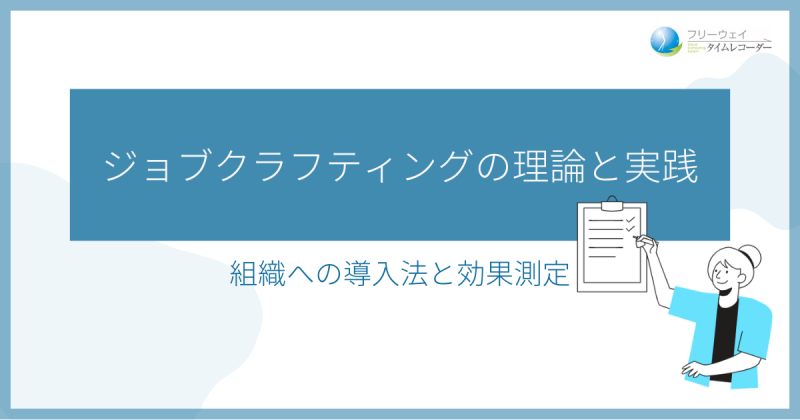
働き方や価値観の多様化が進む現代において、従業員のワークエンゲージメント向上や主体的なキャリア開発を促進する取り組みとして注目されているのが、仕事のやりがいや充実感に着目した「ジョブクラフティング」です。
この記事では、ジョブクラフティングの理論的背景から実践方法、組織への導入法、そして効果測定に至るまで体系的に解説します。
ジョブクラフティングとは、従業員が自らの仕事内容・仕事の進め方・人間関係などを主体的に創造(クラフト)していくことを指します。
米国の組織心理学者レズネスキー教授とダットン教授が2001年に提唱した概念で、従来のように組織から与えられた仕事の枠組みをそのまま受け入れるのではなく、個人が自律的に仕事に意味を見出し、より良いパフォーマンスと満足感を得られるよう調整していくプロセスです。
近年、さまざまな社会的・経済的変化を背景に、ジョブクラフティングへの注目が高まっています。以下に、その主な要因を解説します。
終身雇用や年功序列といった従来の日本型雇用システムが変化し、転職をする人も増え、フリーランス、副業・兼業など働き方も多様になっています。厚生労働省の「令和3年版労働経済の分析」によれば、労働市場の流動性は徐々に高まり、働く人々のキャリア観も「組織主導」から「自律的キャリア開発」へとシフトしています。
働き方が多様で人材流動性が高い社会では、従業員が勤務先の仕事に意味を見出せなくなれば、すぐに転職先や副業を見つけるなど、その企業にとどまらなくなる可能性が高くなります。
したがって、従業員に自社で働き続けてほしいと願う企業には、従業員に仕事の価値を見出し、意欲的に働いてもらうことを促すことが必要です。
世界的に見ても、従業員のワークエンゲージメント低下は多くの組織が直面する課題となっています。これは、従業員が前向きに・貢献意識をもって仕事に取り組めなくなっているということです。
ギャラップ社の調査によれば、日本の従業員エンゲージメント率は世界的に見ても低い水準にあり、この状況を改善するための新たなアプローチとしてジョブクラフティングが注目されています。仕事に対する主体性や意義を高めるジョブクラフティングは、従業員エンゲージメント向上の有効な手段として期待されています。
少子高齢化による労働人口の減少や、専門的スキルを持つ人材の不足により、企業間の人材獲得競争は激化しています。優秀な人材を引きつけ、維持するためには、従業員が自律的に成長し、やりがいを感じられる環境づくりが不可欠です。ジョブクラフティングを推進する組織は、「自分のキャリアを主体的に形成できる場所」として、人材にとって魅力的な選択肢となります。
ジョブクラフティングは主に以下の3つの側面から構成されています。
業務内容や範囲を変更することを指します。例えば、自分の強みを活かせる業務に注力したり、新たな業務に挑戦したりすることです。
職場での人間関係を見直し、再構築することです。より多くの同僚と協働したり、特定の人との関係を深めたりすることが含まれます。
自分の仕事の意義や目的の捉え方を変えることです。例えば、単調な作業も「社会に貢献している」という視点で捉え直すことがあります。
ジョブクラフティングを実践することで、個人は以下のようなメリットを得られることが研究で示されています。
個人だけでなく、組織にとっても以下のようなメリットがあります。
ジョブクラフティングを組織に根付かせるためには、適切な組織文化の醸成が不可欠です。
ジョブクラフティングを促進するうえでは、マネージャーの役割も重要となってきます。
ジョブクラフティングを促進するための具体的な制度や施策を紹介します。
ジョブクラフティングの取り組みが実際に効果を上げているかを測定することは、継続的な改善と組織への定着のために不可欠です。適切な効果測定によって、以下のようなメリットがあります。
ジョブクラフティングの効果を測定するために活用できる指標を紹介します。
効果測定を実践するための具体的な方法を紹介します。
この章では、ジョブクラフティングを導入・推進する際によく直面する課題と、その対策を紹介します。
ジョブクラフティングの意義や効果を管理職が十分に理解していないと、「勝手に仕事を変えるのは問題」と捉えられることがあります。
対策:管理職向けの研修を実施し、ジョブクラフティングが組織にもたらす価値や、適切なサポート方法を学ぶ機会を設けます。
従来の評価制度が柔軟な働き方や主体的な取り組みを評価する仕組みになっていないことがあります。
対策:評価項目に「主体性」や「改善提案」などを追加し、ジョブクラフティングの取り組みによる働き方の変化や、成果が適切に評価される仕組みを整えます。
業務プロセスや役割分担が厳格に定められた組織では、ジョブクラフティングの余地が限られます。
対策:組織の一部から試験的に柔軟な業務設計を導入し、成功事例を作ることで徐々に組織全体に広げていきます。
導入にあたって、企業は従業員個人のリスクも把握しておきましょう。
日常業務に追われ、ジョブクラフティングに取り組む余裕がないと感じる従業員が多いです。
対策:小さな変化から始めることを奨励し、業務時間内にジョブクラフティングに取り組める時間を確保します。
新たな取り組みに必要なスキルや知識が不足していると、挑戦を躊躇することがあります。
対策:学習機会の提供や、メンター制度などを通じてスキル獲得をサポートします。
ジョブクラフティングは、単なる一時的な取り組みではなく、組織と個人が共に成長し続けるための持続的なプロセスです。
ジョブクラフティングは、従業員一人ひとりが自分の仕事に意味を見出し、主体的に取り組むことで、個人の成長と組織の発展を両立させる可能性を秘めています。理論的知見に基づきながらも、自組織の特性に合わせたアプローチで、ぜひジョブクラフティングの導入・推進に取り組んでみてください。
| Q1.ジョブクラフティングとは? |
|---|
| ジョブクラフティングとは、組織から与えられた仕事の枠組みをそのまま受け入れるのではなく、個人が自律的に仕事に意味を見出し、より良いパフォーマンスと満足感を得られるよう調整していくプロセスです。 詳しくは「ジョブクラフティングとは」の章をご覧ください。 |
| Q2.ジョブクラフティングの種類は? |
| ジョブクラフティングは、主にタスククラティング、関係性クラフティング、認知クラフティングに分けられます。それぞれ、業務、人間関係、個人の考え方に関するものです。 詳しくは「ジョブクラフティングの3つの側面」の章をご覧ください。 |