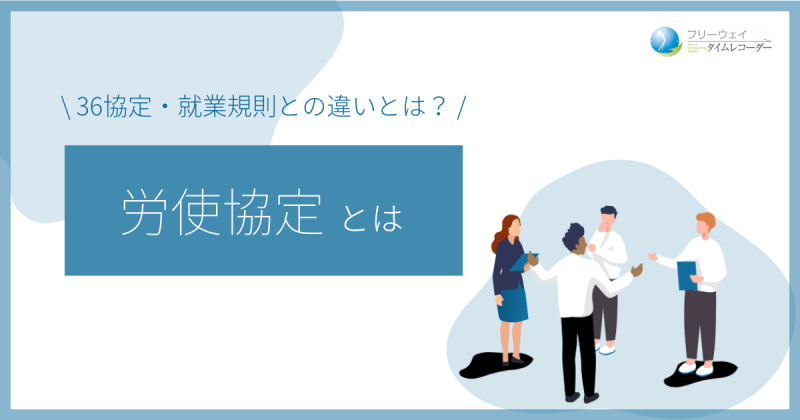
労使協定とは、企業と従業員間で合意して結ぶ「労働環境に関する取り決め」のことです。協定を締結することで「やむを得ず残業してほしい」といった場合でも、法律違反になることがありません。
労使協定で締結できるものには、36協定や事業場外労働のみなし労働など、さまざまな種類があります。協定の種類ごとで対象者や届出の義務の有無、有効期限などが異なるため、事前に確認することが大切です。
本記事では、労使協定の内容や具体的な種類、届出の義務の有無、締結手順などを詳しく解説します。
労使協定とは、企業と従業員間で結ぶ「労働環境に関する取り決め」のことです。
基本的に企業は、労働基準法を元に就業規則や社内ルールを定めます。しかし、業界・業種などによっては「繁忙期に残業してほしい」「従業員の事情に合わせてコアタイムをずらしたい」といったケースも発生するため、労働基準法のみですべてのパターンに対応するのは限界があります。
このような現場にとって不都合がある業務や働き方に対し、企業と従業員が双方同意したうえで例外的に設けられる規則が「労使協定」です。
労使協定には複数の種類があり、労働時間を考える上でよく聞く36協定は「数ある労使協定」の中の1つです。労使協定には、36協定を含め代表的な種類がいくつかあるため、確認してください。
36協定とは、従業員が時間外労働や休日出勤を行う際に必要な協定です。以下の条件を満たす場合は、36協定を締結しなければなりません。
36協定を書面で締結したら、「時間外・休日労働に関する協定届」として、所轄の労働基準監督署長へ提出してください。
ただし、36協定を締結しても、無制限に働かせてよいわけではありません。以下の条件は守る必要があります。
もし、36協定で許容されている以上に働いてもらう場合は、「特別条項付き36協定」の締結が必要です。
36協定の詳細については、以下の記事で解説しています。
関連記事:三六協定とは?担当者が押さえたい基礎事項や具体的な締結手順、運用のポイントをわかりやすく
事業場外労働のみなし労働とは、従業員が業務のすべて(あるいは一部)を事業場外で行った際に適用される協定です。「出先なので企業の指揮下に置くことが難しく正確な労働時間を求めにくい」といった場合に、特定の時間は事業場外労働で働いたと見なすことができます。外回りの営業担当者などに適用することが一般的です。
ただし、事業場外で業務を行っても、以下のケースでは該当しません。
事業場外労働のみなし労働の詳細については、以下の記事で解説しています。
関連記事:事業場外みなし労働時間制とは何か~適用されない場合に注意
まず専門業務型とは、業務のやり方の大半を従業員の裁量に任せる必要があり、企業が遂行手段や時間配分などを具体的に指示することは難しいと認定された職種のことです。以下を含め、全20業務が該当しています。
専門業務型裁量労働制を適用すれば、上記に該当する専門業務型を行う場合、「労使協定で事前に決めた時間分は労働したもの」とみなせます。
従業員ごとに個別で労働契約を締結したり就業規則を整備したりする必要があるため、導入する場合は必ず手続きを確認してください。
専門業務型裁量労働制については、以下の「裁量労働制」に関する記事内で詳しく解説しています。
関連記事:裁量労働制とは?仕組みや対象職種、メリット・デメリット、導入方法などをわかりやすく解説
フレックスタイム制とは、一定期間内で定めた総労働時間の範囲内なら、従業員が始業・終業時刻や労働時間を自由に決定できる制度のことです。総労働時間を満たしていれば毎日の勤務時間を自由に決定できるため、育児や介護、緊急の用事など、従業員自身の都合に合わせて柔軟に働けます。
フレックスタイム制を導入する際は、以下の要件を定めることが必要です。
フレックスタイム制では、従業員自身が労働時間を決定します。そのため、「1日8時間・週40時間」という法定労働時間を超えても、即座に時間外労働とみなされるわけではありません。また、1日の労働時間に満たなくても、欠勤扱いとならないケースもあります。
このように、フレックスタイム制では労働時間に関するルールが変わるため、詳細は「厚生労働省|フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」で必ず確認してください。
変形労働時間制とは、業務の繁忙期に合わせ、労働時間を「1ヵ月単位・1年単位」で調整できる制度のことです。以下の基準を満たして労働時間を調整できれば、特定の日および週に法定労働時間の「1日8時間・週40時間」を超えても問題ありません。
繁忙期の労働時間を長めに設定しても残業時間としてカウントする必要がないため、企業は残業代を削減できます。
変形労働時間制については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:変形労働制導入のメリット・デメリットから導入方法まで
労使協定の中には、締結時に「労働基準監督署への届出が不要なもの」もあります。以下で届出が不要な主な労使協定をまとめました。
| 届出が不要な労使協定 | 参照リンク | 備考 |
|---|---|---|
| フレックスタイム制 | 厚生労働省|フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き | 清算期間が1ヵ月を「超えた場合」は届出が必要 |
| 年次有給休暇の計画的付与 | 厚生労働省|年次有給休暇の計画的付与制度とは | - |
| 年次有給休暇の時間単位付与 | 厚生労働省|年次有給休暇の時間単位付与 | - |
| 休憩の一斉付与の例外 | 厚生労働省|やさしい労務管理の手引き | - |
| 事業場外労働のみなし労働時間制 | 東京労働局|「事業場外労働のみなし労働時間制」の適正な運用のために | 事業場外のみなし時間が「1日8時間を超える」場合は、届出が必要 |
| 育児・介護休業等に関する「育児および介護休業・子の看護休暇・介護休暇・所定外労働の制限・短時間勤務」の対象制限 | 厚生労働省|育児・介護休業等に関する労使協定の例 | - |
| 賃金への「法定控除以外の控除」の実施 | 群馬労働局|賃金支払いに関する事項のあらまし | - |
| 年次有給休暇の賃金を「標準報酬日額」で支払う | 愛知労働局|年次有給休暇のポイント | - |
| 代替休暇制度 | 代替休暇制度とは|制度の概要と中小企業に必要な対応を解説 | - |
フレックスタイム制や事業場外労働のみなし労働時間制など、状況によっては届出が必要なケースもあるため注意してください。
労使協定と似ている言葉としては、主に以下の4つが挙げられます。
上記の用語は「契約者・適用対象・労働基準法との関係」の3つの観点から整理すると、違いを把握しやすくなります。
| 契約者 | 適用対象 | 労働基準法との関係 | |
|---|---|---|---|
| 労働基準法 | - | 日本国内すべての労働者 | - |
| 労使協定 | 「企業」と「従業員の代表」 | 従業員全体 | 労働基準法を超える場合のみ結ぶ |
| 労働協約 | 「企業および使用者の団体」と「労働組合および連合団体」 | 労働組合に加入している労働組合員 | 労働基準法の範囲内で結ぶ |
| 就業規則 | 企業(実情に合わせて決められる) | 従業員全体 | 原則、労働基準法の範囲内で規定する(※) |
| 労働契約 | 「企業」と「1人の従業員」 | 契約した従業員 | 労働基準法の範囲内で結ぶ(就業規則・労働組合に加入している場合は労働協約にも従う) |
※就業規則の中に「労働基準法を超える内容」を含む場合は、その項目について労使協定を締結する必要があります。
労使協定は労働基準法で禁止されている内容の契約も可能であるため、「特例のような位置付け」と捉えてください。
労使協定以外については、「労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約」という優先順位が付けられています。

それぞれについて簡単に解説します。
労働基準法とは、労働条件の「最低限守るべき基準」を定めた法律です。正社員や契約社員、アルバイト、パート、派遣社員に対しても同様に適用されます。
労働基準法は、日本の労働環境を守るために作られた「大原則」です。そのため、労働基準法に違反すると罰せられます。
確かに上記で解説した労使協定は、労働基準法の例外的な立ち位置にある制度です。とはいえ「労使協定を締結したら無制限に働かせてよい」といったルールがないように、ベースは労働基準法をもとに作られているため、働き方の大原則であることは間違いありません。
労働協約とは、賃金や労働時間、団体交渉をはじめとした労使関係のルールについて、企業と労働組合が書面で締結するものです。労働基準法を超えない範囲で、就業規則と異なる労働条件を定められます。原則として、労働協約に反する就業規則および労働契約は無効です。
例えば、労働協約で「解雇や懲戒の際に労働組合との事前協議を義務付ける」といった内容を定めれば、有効期間中は一定の労働条件を確実に維持できます。
ただし、労働協約が適用されるのは「労働組合に加入している労働組合員のみ」という点に注意してください。
就業規則は、労働時間や賃金などの雇用条件や職場のルールをまとめた規則のことです。労使協定と異なり、従業員の合意は不要で原則として企業の意向のみで作成できます。「常時10人以上の従業員がいる事業所」については、就業規則の作成・届出が必須です。
就業規則はあくまでも、「職場内のルールブック」といえるものです。そのため、労働基準法の定めを下回るような雇用条件や従業員が極端に不利になる規定を記載した場合、大原則である「労働基準法」が優先されます。例えば、就業規則に「年次有給休暇は設定しない」と記載しても、法律では有給取得を義務付けているため効力を発揮しません。
就業規則については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:就業規則、社員10人未満でも作成するべき?作成のメリットやポイントを解説
労働契約は、就業規則や労働協約に基づいて、企業と1人の従業員が交わす「労働条件に関する合意契約」のことです。例として、入社時に結ぶ雇用契約書が挙げられます。契約は書面で行うことが原則です。ただし「就業規則で明文化されている」といったケースでは、必ずしも書面を交わす必要はありません。
労使協定を締結する際の5ステップは、以下の通りです。
最初に「企業・従業員の代表者間」で労使協定の内容を協議してください。
労使協定の内容によっては、従業員の働き方に大きな影響を与えます。例えば36協定なら、締結することで法定労働時間の制限が一部取り払われます。そのため「なるべく定時で帰りたい」と考える従業員が多ければ、締結に乗り気ではないかもしれません。
こうした不安や疑問を解消するには、双方が納得するまで話し合うことが必須です。決して企業の都合を押し付けるのではなく、現場の従業員の声をヒアリングしてください。
協議を行い企業と従業員の双方が納得したら、労使協定を締結してください。協定は「企業の代表」と「労働組合の代表者など従業員側の過半数代表」の間で結びます。この場合における「従業員」とは、正社員や契約社員、パート、嘱託社員、再雇用者、アルバイトなど、その企業で働くすべての人を指しています。
過半数代表者については、以下いずれかに該当していることを確認してください。
労使協定の種類によって、労働基準監督署への「届出の義務の有無」が異なるため、必要な場合は必ず提出してください。届出が必要な労使協定としては、主に以下が挙げられます。
上記の労使協定については、従業員と書面で合意を交わした時点ではなく、「労働基準監督署への届け出が認められた時点」で効力を発揮するため注意してください。
届出に必要な書類は、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」からダウンロードできます。また、同じく厚生労働省が「作成支援ツール」を提供しているため、併せてご確認ください。
労使協定を締結したら、就業規則へ記載してください。就業規則で明文化し従業員に確実に周知することで、「聞いていた条件と違う」といったトラブルを防ぐことにつながります。
上記で解説したように、労使協定が効力を発揮するには「労働基準監督署に労使協定の届出を提出して認められた時点」です。そのため、書面で合意を交わした直後に就業規則へ反映させないよう、注意してください。
また、労使協定や就業規則は、労働基準法のもとで認められている取り決めです。そのため、労使協定に含まれていない項目を就業規則に定める場合も、労働基準法を超える内容を含むことはできません。
就業規則の変更方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:【2023年4月法改正】就業規則の見直しチェックリストと変更時の5ステップ
労働基準法第106条で「企業は従業員に労使協定および就業規則の内容を周知する義務がある」と定められているため、必ず確認してください。以下のような方法での周知がおすすめです。
労使協定に違反し以下4パターンのいずれかに該当すると、違反とみなされ罰則が科されます。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 労使協定を締結せずに該当の行為を行った | 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 労使協定を届け出なかった | 30万円以下の罰金 |
| 締結した労使協定を破った | 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 従業員へ労使協定を周知しなかった | 30万円以下の罰金 |
事案によっては、送検されて社名が公表されるケースもあるため、十分に注意してください。例えば「従業員3名に36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた」「36協定を締結せず労働者11名に違法な時間外労働を行わせた」といった企業は、実際に社名が公表されました。
参照:
厚生労働省|職場のあんぜんサイト
厚生労働省|現行の裁量労働制について p.6
厚生労働省|事業主・労働者の皆さまへ
厚生労働省労働基準局監督課
労使協定を正しく運用するためには、以下のポイントを押さえてください。
労使協定の種類ごとで「届出義務の有無」が異なるため、必ず確認してください。届出義務の有無ごとに、改めて代表的な労使協定の種類を紹介します。
【届出義務がある】
【届出義務が無い】
届出義務があるにも関わらず規定の書類を提出しないと、30万円以下の罰金が科される可能性もあるため注意してください。
労使協定を結ぶ際は、必ず現場の従業員の意見をヒアリングし、実情にマッチした内容を締結してください。現場の意見を聞かず、「繁忙期に残業してほしいので36協定の締結を進めよう」「フレックスタイム制を導入した方がみんな働きやすくなるだろう」といったイメージだけで労使協定の締結を進めると、従業員が反発するおそれがあります。
労使協定は企業と従業員の代表間で合意を取ることが必要なため、スムーズに締結するためにも、面談やアンケートなどを通じ、現場の意見をしっかり吸い上げることを意識してください。
労使協定の対象者は、協定の種類や内容によって異なります。そのため、自社で結びたい労使協定の内容と対象者が合っているか、事前に確認してください。
例えば「1ヵ月単位の変形労働時間制に関する労使協定」の場合、法令上は対象範囲に制限がありません。
一方で「事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定」の場合、以下を満たす必要があります。
このように、締結できる対象範囲が異なるため、必ず事前に確認してください。
労使協定によっては有効期限を定める必要があります。主要な労使協定のうち、有効期限を定める必要があるものは以下の4つです。
| 1ヶ月単位の変形労働時間制 | 3年以内程度 |
|---|---|
| 1年単位の変形労働時間制 | 1年程度 |
| 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定) | 1年程度 |
| 専門業務型裁量労働制 | 3年以内程度 |
締結している企業が多いであろう「36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)」は、期限を1年間で定めることが一般的です。有効期間内に労働基準監督署への届出が必要となるため、注意してください。
有効期限が切れた場合は、再度「労使協定を締結する5ステップ」を踏んで締結することが必要です。
労使協定とは、企業と従業員間で結んだ「労働環境に関する取り決め」のことです。
もちろん、原則としては労働基準法に沿って働いてもらう必要があります。しかし、労使協定を締結することで「繁忙期に法律の定めを超える残業を認める」などが可能です。
労使協定にはいくつかの種類があるため、以下のような代表的なものは押さえてください。
労使協定を締結する際は、「届出義務の有無をチェックする」「現場の従業員の意見を反映させる」といった点を意識することが必須です。
労使協定締結に関わる法律に違反すると、罰金が科されたり社名を公表されたりするケースもあるため、必ずルールに則り正しい方法で運用してください。
| Q1.労使協定とはどんなものですか? |
|---|
|
企業と従業員の代表者間で交わされる契約のことです。「労働基準法では禁止されているが現場では不都合が発生する」といった場合に、両者の同意があれば条件を変更して働けます。 |
| Q2.労使協定と36協定の違いは何ですか? |
|
「36協定」は労使協定の1つです。労働基準法36条に基づいて結ばれる「時間外・休日労働をさせる場合の労使協定」の通称です。 |
| Q3.労使協定を結ばないと罰則はある? |
|
あります。違反内容によって罰則が変わるため、必ず確認してください。
|
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員10人まで永久無料の勤怠管理システム「フリーウェイタイムレコーダー」を提供しています。フリーウェイタイムレコーダーはクラウド型の勤怠管理システムです。ご興味があれば、ぜひ使ってみてください。