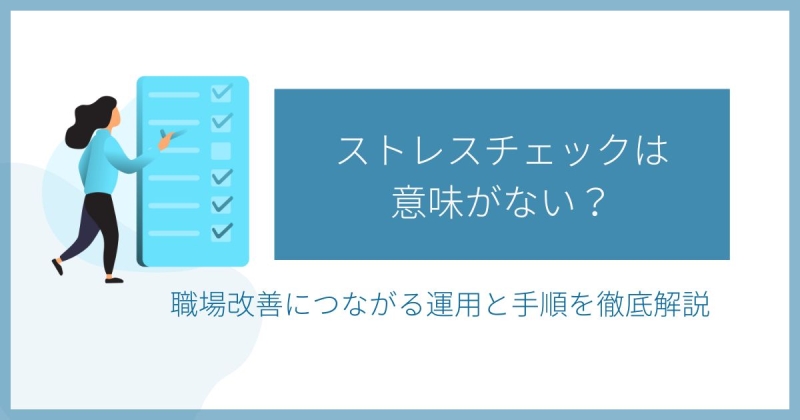
従業員50名以上の企業に義務化されているストレスチェック制度。しかし「意味がない」「何から始めればいいかわからない」と感じている担当者も多いのではないでしょうか。ストレスチェック制度を単なる義務と捉え、形骸化しているケースもあるようです。
この記事では、ストレスチェックの制度の基本から具体的な実施方法、効果的な職場改善への活用法まで詳しく解説します。
「意味がない」と言われがちな状況を改善し、従業員の健康と企業の成長を両立させるため、実践的な運用方法を見つけましょう。
近年、職場のメンタルヘルス不調が社会問題化し、精神障害による労災認定件数は増加の一途をたどっています。ハラスメントが精神障害の労災認定の主要な要因となるケースも多く見られます。
企業にとって従業員の心の健康管理は早急に手をつけなくてはいけない課題であり、法的義務だけでなく、経営戦略としても重要性が高まっています。
「ストレスチェック制度」は、課題に対応するためのツールとして導入されましたが、「義務だから仕方なく実施している」と感じている企業や担当者も少なくありません。
制度の背景には、従業員の心身の健康悪化という深刻な社会問題があります。従業員の健康状態が悪化することは、生産性の低下、休職者の増加、離職率の上昇、さらには労災リスクの増大といった形で現れます。ストレスチェック制度は、法令遵守するためのものだけでなく、「潜在的なリスクへの対策」として捉えるべきです。
この記事では、ストレスチェック制度を単なる「義務」ではなく、従業員の活力向上と生産性向上につながる「戦略」として活用するためにどんなことができるのかを考えます。
ストレスチェック制度の導入を検討する、あるいは既存の運用を見直す際に重要なのが、定義と法的根拠を理解し、基礎知識を固めることです。制度の目的や義務化の背景を深く知ることで、重要性を正しく認識し、適切な運用を行うことができます。
ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する質問票に回答し、集計・分析することで、自身のストレス状態を把握する簡単な検査です。
制度の主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」と、不調の早期発見・早期対応を促す「二次予防」です。一次予防では、職場環境の改善やストレスマネジメントを通じて健康の維持・増進を目指し、二次予防では不調の早期発見と適切な対応により重症化を防ぎます。
「予防」という概念は、単に個人の健康状態を確認するだけでなく、企業が従業員の健康に対し、より「積極的に関与する責任がある」ことを示しています。
特に一次予防は、個人の努力だけでなく「職場環境の改善」に焦点を当てており、企業が能動的に介入し、健康リスクを低減する「安全配慮義務」の延長線上にあります。
ストレスチェックは、単なる「診断」ではなく、職場全体のストレス要因を特定し、職場環境の改善につなげることです。従業員が健康で働きやすい環境を構築する重要な役割があります。
ストレスチェック制度は、2015年12月1日に施行された労働安全衛生法改正により、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場に対し、年1回の実施が義務付けられました。
精神障害による労災認定件数の増加など、社会的なメンタルヘルス課題の深刻化に対応するための国の施策です。
令和5年度の実施状況調査によると、義務対象事業場での実施率は81.7%となっており、多くの企業で制度の定着が進んでいます。
企業がストレスチェックの実施義務を怠っても、直接的な罰則はありません。しかし、実施状況を所轄の労働基準監督署へ報告しなかった場合は、労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
報告義務が罰則の対象となっているのは、国が形式的な実施を求めるだけでなく、企業が制度を適切に運用することを重視しているということです。企業は実施の正確性と透明性を確保せざるを得ず、結果的に制度の信頼性を高めることになります。
常時50人未満の事業場については努力義務とされていますが、現時点でも自主的な取り組みが推奨されています。
ストレスチェックの質問票には、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を基本として、以下の3つの領域に関する項目を含める必要があります。
仕事の量や質、コントロール度、職場環境、人間関係など、ストレスの原因となりうる外部要因を評価します。例えば、過剰な業務量やハラスメントの有無などが含まれます。
憂鬱感、倦怠感、身体症状(めまい、頭痛、腰痛など)といった、ストレスによって生じる心身の自覚症状を把握します。個人の健康状態への影響を直接的に示す指標となります。
上司、同僚、家族、友人などからのサポート状況を評価し、ストレスを緩和する社会的資源の有無を確認します。サポート体制の有無は、ストレスへの対処能力に大きく影響します。
ストレスは、単一の原因でなく、職場環境、個人の心身状態、そして社会的支援という複数の要素が複雑に絡み合って生じています。
特に「仕事のストレス要因」と「周囲のサポート」は、企業が直接的に改善できる領域であり、ストレスチェックの結果が具体的な職場改善策につながる可能性が高いものです。
「ストレスを測る」だけでなく、「ストレスの原因と対策の方向性を示す」のがこの制度の意義でもあります。
ストレスチェック制度を実際に導入・運用する人事労務担当者が最初に抱える課題は、「何から取り組んでいいかわからない」ということです。制度をスムーズに実施するための具体的なステップを準備段階から最終報告まで網羅的に解説します。
まず最初に「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」という基本方針を明確に示し、社内規程として明文化することから始めます。
方針を従業員に周知することで、制度への理解と協力を促し、安心して実施できる土壌を築きます。次に、実施者(医師、保健師など)や実施事務従事者(人事権を持たない担当者)の選任を含む実施体制をつくり、それぞれの役割分担を明確にします。
実施事務従事者は質問票の回収やデータ入力、結果通知の準備など、個人情報を取り扱う重要な役割を担うため、人事権をもつ者が従事することは禁止されています。
さらに、従業員全員が安心して受検できるよう、制度の目的、プライバシー保護の方針、結果の取り扱いなどを丁寧に周知することが重要です。
ストレスチェックの質問票は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を基本としますが、より詳細な分析を求める場合は80項目版も検討できます。
80項目版は、57項目版に比べて設問数が多く、従業員の情緒的負担やワークエンゲージメントなど、より詳細な尺度でストレス状況を把握できます。
質問票の配布・記入・回収は、従業員の負担を考慮し、ITシステムを活用したオンライン方式で行うことをおすすめします。
回収された質問票は、実施者が評価基準に基づいて集計・分析し、個人のストレス状態を判定します。
参考:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト(厚生労働省)『新職業性ストレス簡易調査票(80項目)』
ストレスチェックの結果は、実施者から直接本人に通知されます。この際、本人の同意なく事業者に結果が開示されることはありません。従業員のプライバシー保護を最優先し、従業員が安心して受検できるようにします。
高ストレスと判定された従業員は、医師による面接指導の申し出が推奨されます。面接指導は従業員の任意で強制はできません。申し出があった場合は、事業者は応じる義務があります。
面接指導では、産業医などの専門家が労働者の心身の状態やストレスの原因を詳しく聴取し、適切なアドバイスや医療機関への受診を勧めます。医師の意見を聴取した上で、必要に応じて就業上の措置(労働時間の短縮、配置転換など)を検討し、実施します。
ストレスチェックの結果は、個人が特定されない形で部署やグループなどの集団ごとに集計・分析します。集団分析は努力義務とされていますが、職場全体のストレス要因を把握し、具体的な職場環境を改善するために重要なステップです。
集団分析の結果に基づいて、長時間労働の是正、ハラスメント対策、コミュニケーションの活性化など、具体的な改善活動を行います。何らかの対応をすることで、企業側、従業員双方にとって、ストレスチェック制度が「意味のある」ものになります。
集団分析の際には、数値データだけでなく、現場の管理監督者の見解や産業保健スタッフからの質的な情報も合わせて検討しましょう。集団分析結果を各部署にフィードバックする際は、部署の評価や批判にならないよう配慮し、改善提案として伝えることが大切です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、ストレスチェックの実施状況を所轄の労働基準監督署へ報告する義務があります。報告書には、ストレスチェックを実施した労働者数や、医師による面接指導を受けた労働者数などを正確に記載する必要があります。
報告書の提出期限は明確に定められていませんが、年1回の実施頻度に合わせて事業年度終了後などに提出するのが一般的です。報告を怠った場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、個人のストレスチェック結果や面接指導の記録は、法令に基づき適切に保存する必要があります。個人情報保護の観点から厳重な管理が求められ、情報漏洩は企業の信頼を大きく損ねるだけでなく、法的責任を問われる可能性があります。
ストレスチェック制度は多くの関係者がそれぞれの役割と責任を果たすことで、効果的に機能します。各関係者の役割を明確に理解し、スムーズな制度運用を行いましょう。
労働安全衛生法に基づき、事業者はストレスチェック制度の実施義務を負う最終責任者です。制度を実施するだけでなく、制度の基本方針を策定し、適切な実施体制を整備することが含まれます。
また、従業員が安心して受検できる環境を整え、ストレスチェックの結果に基づいた職場環境改善に努めることも事業者の重要な責任です。
高ストレス者から面接指導の申し出があった場合には、面接機会を提供し、面接指導の結果を踏まえて就業上の措置を検討することも事業者の義務です。
ストレスチェックの実施者になれるのは、医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師といった専門資格をもつ者です。
質問票の選定、労働者のストレス状態の評価、高ストレス者の判定、医師による面接指導の要否判断など、専門的な知識と判断が求められます。
個別の労働者の健康状態だけでなく、職場全体の状況を理解している産業医が実施者となることが望ましいとされています。実施者は労働者の機微な個人情報を取り扱うため、厳格な守秘義務が課せられています。
実施事務従事者は、実施者の指示のもとストレスチェックの実務をサポートする役割を担います。
業務内容は、質問票の配布・回収、データ入力、結果の集計・評価、高ストレス者の選定、結果通知の準備、未受検者への受検勧奨、集団分析結果の出力と事業者への提供などが含まれます。
実施事務従事者は労働者の個人情報を取り扱うため、人事権を持つ者(経営者、人事部長、当該部署の管理職など)は従事することができません。
個人情報が人事上の不利益な取り扱いに利用されることを防ぎ、従業員が安心して制度を利用できるようにするためです。実施事務従事者にも厳格な守秘義務が課せられ、違反した場合は罰則の対象となります。
高ストレスと判定され、面接指導を申し出た労働者に対し、医師(産業医など)が面接指導を行います。産業医は労働者の心身の状態やストレスの原因を詳しく聴き取り、適切なアドバイスや医療機関への受診勧奨を行います。
面接指導は、メンタルヘルス不調の重症化を防ぎ、労働者の健康回復を支援するための個別ケアの要となります。
また、産業医は面接指導の結果に基づいて、事業者に対し就業上の措置(労働時間の短縮、配置転換など)に関する意見を出します。また、集団分析の結果を踏まえ、職場環境改善に向けた具体的な助言を行います。
ストレスチェック制度は、その目的が明確であるにもかかわらず、多くの企業で「意味がない」と感じられることがあります。背景にある課題を掘り下げ、制度を価値あるものにするための具体的なポイントを解説します。
ストレスチェックが「意味がない」と感じられる主な原因は、受検率の低さ、高ストレス者への面接指導の利用率の低さ、そして集団分析結果が具体的な職場環境改善に繋がらない点にあります。
従業員が企業に対して「個人情報が適切に扱われるか」「面接指導を受けることで不利益な扱いを受けないか」という信頼がないという問題が根底にあります。
個人情報保護への不安から受検をためらったり、面接指導を受けることで不利益な扱いを受けるのではないかという懸念が、制度の形骸化を招いています。
ストレスチェックを実施するのみで、分析結果から具体的な改善を行なっていないと、制度の価値は低下します。
「意味がない」と感じるのは制度の設計そのものではなく、「行動への転換」のプロセスが不十分であるためです。回収した結果をどう改善につなげるのかを考えるのが、制度を効果的に活用する第一歩となります。
ストレスチェックを真に「意味のある」ものにするためには、以下のポイントを重視し、制度を活用することが大切です。
従業員へ丁寧に制度の説明を行い、プライバシー保護の徹底と匿名性の担保を明確にすることで、安心して受検できる環境を整えます。
結果が本人の同意なく事業者に開示されないこと、面接指導の申し出を理由に不利益な取り扱いをしないことを、繰り返し周知していきましょう。
集団分析結果を単なるデータとして終わらせず、具体的な改善計画と実行につなげることが大切です。労働時間や健康診断結果など他の人事データと連携して分析することで、具体的なストレス要因を特定し、職場環境改善策を考えられます。
集団分析結果を各部署にフィードバックする際は、部署の評価や批判にならないよう配慮し、あくまで改善提案として伝えます。
ストレスチェック制度を運用する際、法的義務の遵守だけでなく、従業員の信頼を確保し、潜在的なリスクを回避するためにいくつか注意すべき点があります。
特に「個人情報の取り扱い」と「不利益な取り扱いの禁止」は、制度を健全に運用するために非常に重要です。
ストレスチェックの結果は、労働者の重要な個人情報であり、取り扱いには細心の注意を払わなくてはいけません。本人の同意なく事業者に結果を開示することはできません。
従業員が安心して制度を利用できるための最も重要な原則であり、この原則が守られなければ、制度そのものへの信頼が失われます。実施者および実施事務従事者には厳格な守秘義務が課せられ、違反した場合は刑罰の対象となります。
集団分析を行う際にも注意が必要です。集団規模が10人未満の場合、個人が特定される恐れがあるため、全員の同意がない限り、結果を事業者に提供してはなりません。
厳格なルールを遵守し、個人情報保護を徹底することは、制度を健全に運用するための絶対条件です。
ストレスチェックの受検や面接指導の申し出、その結果を理由として、労働者に対して解雇、不当な配置転換、減給などの不利益な取り扱いをすることは固く禁じられています。
従業員が自身の健康状態に向き合い、必要なサポートを安心して受けられる環境を保障するためです。就業規則に受検義務や受検しないことに対する懲戒規定を設けることも認められていません。
「面接指導が必要とされた労働者が、面接指導を申し出をしないこと」を理由に不利益な取り扱いをすることも禁止されています。
禁止事項を徹底することで、従業員は「ストレスチェックを受けると会社に何か不利益があるかもしれない」という懸念を抱くことなく、制度を利用できるようになります。結果として、受検率の向上や面接指導の利用促進にもつながります。
こういった原則を従業員に明確に周知し、安心して制度を利用できる企業文化を醸成することが大切です。
多様な働き方が普及する現代において、派遣労働者に対するストレスチェックの取り扱いも重要な注意点です。ストレスチェックの実施義務の対象になる「常時50人以上の労働者」にはパートタイマー、派遣労働者も含まれます。
派遣労働者に対するストレスチェックの実施義務は、直接雇用契約を結んでいる派遣元事業者(派遣会社)にあります。しかし、派遣先事業場においても、職場環境改善の観点から派遣元と協力して派遣労働者のストレス状況の改善に努めなくてはいけません。
派遣労働者は新しい職場やチームに頻繁に変わることが多く、それに伴う不安や適応の問題がストレスの原因となる可能性があります。そのため、派遣元・派遣先双方の連携と配慮が必要です。
ストレスチェックの結果の取り扱いは、派遣元・派遣先間の情報共有ルールを明確にし、細心の注意を払う必要があります。
ストレスチェックの実施にはさまざまな費用が発生します。主な費用と相場を把握し、効率的な運用方法を検討しましょう。

費用は利用する外部サービスや受検方法(Webか紙か)によって大きく変動します。厚生労働省が無料で提供するプログラムもありますが、質問内容の変更ができない、システム環境の整備を自社で行う必要があるなどの制約があります。
費用を抑えつつ効率的に運用するためには、Web受検の導入が有効です。また、ストレスチェック実施後の職場環境改善活動に対して、助成金が利用できる場合もあります。
価格を基準に安価なサービスを選ぶだけでなく、自社のニーズに合ったサービス内容を見極め、見積もりを比較検討しましょう。
引用:厚生労働省『団体経由産業保健活動推進助成金のご案内』(令和7年5月23日更新)
人事労務担当者が兼任で業務を行うことが多い中小企業にとっては、ストレスチェック制度の運用は大きな負担となりがちです。
そこで、ぜひ利用したいのが人事労務ソフトです。どのようにストレスチェック運用を効率化できるかを紹介します。
ストレスチェックの運用には、質問票の配布・回収、結果の集計・評価、高ストレス者への通知、労働基準監督署への報告書作成といった、多岐にわたる煩雑な業務が伴います。
これらを手作業や汎用ツール(Excelなど)で行う場合、膨大な時間と労力がかかり、ヒューマンエラーのリスクも高まります。
人事労務ソフトを導入することで、業務を一連の流れで自動化できます。例えば、オンラインでの質問票配布・回収、自動集計・評価機能、高ストレス者の自動抽出と通知、さらには労働基準監督署への報告書フォーマットの自動生成などが可能です。
導入によって担当者の時間と労力を大幅に削減し、本来のコア業務、従業員との対話や具体的な職場改善策の検討などに集中できるようになります。
ストレスチェックが「意味がない」と感じられる大きな理由の一つに、集団分析結果が具体的な職場環境改善につながらない点があるとお伝えしました。そこで、人事労務ソフトを使うことで、課題を解決できる可能性があります。
人事労務ソフトはストレスチェックの結果だけでなく、勤怠データ(労働時間)や健康診断データなど、他の人事労務データと連携して集団分析を行うことができます。
単一のデータだけでは見えなかった、より多角的な見解を得られます。例えば、ある部署でストレスが高い傾向にある場合、その部署の残業時間が長いなどの要因を特定できるのです。その分析をふまえ、効果的な職場環境の改善策を考えられます。
従業員の健康状態と勤務状況を結びつけることで、改善すべき点が明確になります。そして、早期の問題発見と対処ができ、離職や休職の予防にもつながります。
人事労務ソフトを使うことで、ストレスチェック運用の「義務」がデータに基づいた「経営戦略」になり、価値が高まります。
ストレスチェックデータは、労働者の重要な個人情報であり、管理には厳格なセキュリティ対策が必要です。情報漏洩は企業の信頼を大きく損ねるだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。
人事労務ソフトは厳格なセキュリティ対策とアクセス権限管理により、ストレスチェックデータを安全に管理します。担当者個人の管理ミスによる情報漏洩リスクを軽減できます。
また、法改正への自動対応機能をもつソフトも多く、常に最新の法令に準拠した運用をサポートし、コンプライアンス違反のリスクを最小限に抑えられます。ソフトの導入は、業務効率化だけでなく、企業のガバナンス強化にも貢献します。
精神障害による労災認定件数が増加し続ける現代社会において、従業員のメンタルヘルスの対策は企業の存続と成長に直結する課題となっています。
ストレスチェック制度は、単なる法的義務として行うだけではなく、人的投資戦略の一環としても捉えることができます。従業員の心の健康を守り、生産性を向上させることは、事業を持続して成長させることにつながるからです。
適切な知識と人事労務ソフトなどのツールを活用することで、制度運用の負担を軽減し、「意味のある」ストレスチェック運用を実現できます。データ分析を有効活用して職場環境改善につなげることで、ストレスチェックは単なるコストではなく、従業員のエンゲージメントと生産性を高めるための戦略になり得ます。
| Q1.ストレスチェックを行わないとどうなりますか? |
|---|
|
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、ストレスチェックの実施を怠っても直接的な罰則はありません。しかし、実施状況を所轄の労働基準監督署へ報告しなかった場合は、労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。 また、ストレスチェックを実施しないことは、従業員の心の健康管理を怠ることにつながり、生産性の低下、休職者の増加、離職率の上昇、さらには労災リスクの増大といった形で企業に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| Q2.ストレスチェックの結果を職場改善に活かすにはどうすればよいですか? |
|
ストレスチェックの結果を個人が特定されない形で集団ごとに分析し、長時間労働の是正、ハラスメント対策、コミュニケーションの活性化など、具体的な改善活動につなげることが重要です。数値データだけでなく、現場の管理監督者の見解や産業保健スタッフからの質的な情報も合わせて検討し、改善提案として各部署にフィードバックしましょう。 |
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員10人まで永久無料の勤怠管理システム「フリーウェイタイムレコーダー」を提供しています。フリーウェイタイムレコーダーはクラウド型の勤怠管理システムです。ご興味があれば、ぜひ使ってみてください。